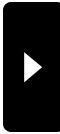小さな花の
何と、3月も最終日、明日は4月「う~ん」 唸った所で時が戻る訳でもないが・・・早い。
唸った所で時が戻る訳でもないが・・・早い。

せめて4月らしい気温になってくれる事を願いたい。
今日はお地蔵さんの下の藪を川上に歩いてみました。
『ニワトコ』が小さな花のかたまりをいくつも付けている、「ニワトコ」の名前の由来はよく解りませんが、別名の「セッコツボク」は「接骨木」で枝や幹を煎じて水飴状にしたものを骨折などの患部にあてて湿布すると効果が有る、と云う伝承によるらしい。
またこの木の髄は顕微鏡観察用の切片を作る時、材料を挟んで切るのに利用される。
明日は「エイプリルフール」罪の無い嘘をついても良い日らしい、 そうは言っても中々ウイットに富んだ嘘をつくのも難しいものだ
そうは言っても中々ウイットに富んだ嘘をつくのも難しいものだ

小さな花が数え切れない程集まって塊の様に見えます。

花は直径3~5ミリ、花弁は反り返って目立たない。雄しべは5本で放射状、真ん中の小さなあずき色が雌しべの先端(柱頭)
 唸った所で時が戻る訳でもないが・・・早い。
唸った所で時が戻る訳でもないが・・・早い。

せめて4月らしい気温になってくれる事を願いたい。
今日はお地蔵さんの下の藪を川上に歩いてみました。

『ニワトコ』が小さな花のかたまりをいくつも付けている、「ニワトコ」の名前の由来はよく解りませんが、別名の「セッコツボク」は「接骨木」で枝や幹を煎じて水飴状にしたものを骨折などの患部にあてて湿布すると効果が有る、と云う伝承によるらしい。

またこの木の髄は顕微鏡観察用の切片を作る時、材料を挟んで切るのに利用される。
明日は「エイプリルフール」罪の無い嘘をついても良い日らしい、
 そうは言っても中々ウイットに富んだ嘘をつくのも難しいものだ
そうは言っても中々ウイットに富んだ嘘をつくのも難しいものだ 
小さな花が数え切れない程集まって塊の様に見えます。

花は直径3~5ミリ、花弁は反り返って目立たない。雄しべは5本で放射状、真ん中の小さなあずき色が雌しべの先端(柱頭)
タグ :植物
2010年03月31日 Posted by 松ぽっくり at 20:59 │Comments(0) │フィールド
ちょっと嬉しい
上空に寒気が入り込んでいるとの事で、角度の変わって来た日差しとは裏腹に空気は真冬並みに冷たい。
そんなフィールドでちょっと嬉しい出会いが、『ゴヨウアケビ』の花に初めてお目にかかりました。
「ゴヨウアケビ」は「アケビ」と「ミツバアケビ」の自然雑種で両方の特徴を見せてくれます。
アケビの様に5枚の小葉には波状の鋸歯が有り、花はミツバアケビの様に濃紫色でかなり小さい。
以前にもそれらしい葉は目にした事が有りますが、花とは初対面です。 この「ゴヨウアケビ」残念ながら実は結ばないようです。
この「ゴヨウアケビ」残念ながら実は結ばないようです。
土手の桜に「メジロ」や「ヒヨドリ」が蜜を求めて集まっていました。
ゴヨウアケビの雌花は大きく見えますが直径15ミリ程です

雄花、白く見える所は花粉を出し始めた所です

ゴヨウアケビの葉、5小葉に波状のキョシが有る

メジロ


そんなフィールドでちょっと嬉しい出会いが、『ゴヨウアケビ』の花に初めてお目にかかりました。

「ゴヨウアケビ」は「アケビ」と「ミツバアケビ」の自然雑種で両方の特徴を見せてくれます。
アケビの様に5枚の小葉には波状の鋸歯が有り、花はミツバアケビの様に濃紫色でかなり小さい。
以前にもそれらしい葉は目にした事が有りますが、花とは初対面です。
 この「ゴヨウアケビ」残念ながら実は結ばないようです。
この「ゴヨウアケビ」残念ながら実は結ばないようです。土手の桜に「メジロ」や「ヒヨドリ」が蜜を求めて集まっていました。
ゴヨウアケビの雌花は大きく見えますが直径15ミリ程です

雄花、白く見える所は花粉を出し始めた所です

ゴヨウアケビの葉、5小葉に波状のキョシが有る

メジロ

タグ :植物
2010年03月30日 Posted by 松ぽっくり at 16:53 │Comments(5) │フィールド
延び出して
ラジオでは「花冷え」と言っていました。いつまでも冷たい日が続きます。
そんな中「ヒバリ」は天に昇り絶え間なくテレトリーを主張しています。
東向きの斜面では『ムラサキサギゴケ』が花を付けていました。
先日取り上げた「トキワハゼ」と花が非常によく似ていますが、こちらは根元から匐枝が延び出して広がる点が異なります。
画像でも右側と左下に延びだしているのが分かると思います。
花の色は環境によっても異なり、かなり色の濃いものもあります。
白花品を「サギゴケ」と呼びます。
空模様は照ったり降ったり、雪アラレのオマケ付きでめまぐるしい!
ムラサキサギゴケ


ヒバリのぼやけたシルエット

そんな中「ヒバリ」は天に昇り絶え間なくテレトリーを主張しています。
東向きの斜面では『ムラサキサギゴケ』が花を付けていました。
先日取り上げた「トキワハゼ」と花が非常によく似ていますが、こちらは根元から匐枝が延び出して広がる点が異なります。
画像でも右側と左下に延びだしているのが分かると思います。

花の色は環境によっても異なり、かなり色の濃いものもあります。
白花品を「サギゴケ」と呼びます。
空模様は照ったり降ったり、雪アラレのオマケ付きでめまぐるしい!
ムラサキサギゴケ


ヒバリのぼやけたシルエット

タグ :植物
2010年03月29日 Posted by 松ぽっくり at 16:00 │Comments(0) │フィールド
微毛が
風は北寄り、午後には雨も降りだし、冬の様な冷たさです。
土手の下で「花見」を決め込んでいた方々は酒盛りに水を差されて、大騒ぎ
かく言う私もUターン!
と云う訳で今日の出会いは雨の降る前に顔を合わせた『ノジスミレ』です。「ヒメスミレ」から2週間ほど遅れての出会いです。去年の例からすると、これから次々に咲き始める事でしょう。
全体に微毛が有りますが、側弁の基部は普通無毛です。
この個体はまだ咲き始めたばかりであまり葉が目立ちませんが、もう少し季節が進みますと、葉も大きくなり大分様相が変わってきます。
このスミレも人里近くの日当たりのよい乾き気味の環境が好きで、山の中では見かけません。
 ノジスミレ
ノジスミレ
土手の下で「花見」を決め込んでいた方々は酒盛りに水を差されて、大騒ぎ

かく言う私もUターン!

と云う訳で今日の出会いは雨の降る前に顔を合わせた『ノジスミレ』です。「ヒメスミレ」から2週間ほど遅れての出会いです。去年の例からすると、これから次々に咲き始める事でしょう。
全体に微毛が有りますが、側弁の基部は普通無毛です。
この個体はまだ咲き始めたばかりであまり葉が目立ちませんが、もう少し季節が進みますと、葉も大きくなり大分様相が変わってきます。
このスミレも人里近くの日当たりのよい乾き気味の環境が好きで、山の中では見かけません。
 ノジスミレ
ノジスミレ タグ :植物
2010年03月28日 Posted by 松ぽっくり at 15:45 │Comments(0) │フィールド
釣り糸が
所用が有ってフィールドに出れませんでしたので、昨日対面した「ウラシマソウ」を取り上げます。
昨年も丁度同じ頃に確認していまして、場所的にも同じ球茎から出たものです。
普通地中の球茎は多数の子球を作り、盛んに栄養繁殖するので周囲に若い葉が出るのですが、この株は今年も一人きりです(栄養状態が今いちなのかも知れません)
何かが当ったのか、浦島さんの釣り糸が途中で切れかかっていました。
今度は一度仏炎苞の中を確認してみたいと思います。
今日も風の冷たい一日でした。
 ウラシマソウ
ウラシマソウ
昨年も丁度同じ頃に確認していまして、場所的にも同じ球茎から出たものです。
普通地中の球茎は多数の子球を作り、盛んに栄養繁殖するので周囲に若い葉が出るのですが、この株は今年も一人きりです(栄養状態が今いちなのかも知れません)
何かが当ったのか、浦島さんの釣り糸が途中で切れかかっていました。

今度は一度仏炎苞の中を確認してみたいと思います。
今日も風の冷たい一日でした。
 ウラシマソウ
ウラシマソウタグ :植物
2010年03月27日 Posted by 松ぽっくり at 22:01 │Comments(0) │フィールド
黄金色の
3日見ぬ間の・・・では無いが、2日間降り続いた雨の後のフィールドはその様相を変えていました。
ヤナギはその梢を新緑で装い、お地蔵さんの下の「ヤマブキ」は黄金色の花が春の日にまぶしい程でした。
ただ、風はそんな春模様とは裏腹にそこそこ冷たい。
もう姿の無い「ジョウビタキ」 旅立ちも近い「ツグミ」 どちらも北に帰る日が近づくと、そばに寄れる距離が短くなるのはなぜだろう?私の顔を覚えた訳でもあるまいし・・・?
土手の「ソメイヨシノ」は3分咲き、と云った所でしょうか?


ヤマブキ
ヤナギはその梢を新緑で装い、お地蔵さんの下の「ヤマブキ」は黄金色の花が春の日にまぶしい程でした。
ただ、風はそんな春模様とは裏腹にそこそこ冷たい。
もう姿の無い「ジョウビタキ」 旅立ちも近い「ツグミ」 どちらも北に帰る日が近づくと、そばに寄れる距離が短くなるのはなぜだろう?私の顔を覚えた訳でもあるまいし・・・?

土手の「ソメイヨシノ」は3分咲き、と云った所でしょうか?


ヤマブキ
タグ :自然
2010年03月26日 Posted by 松ぽっくり at 17:41 │Comments(0) │フィールド
別名は
雨も無ければ困るが2日続くと、河原の巡回員 としてはついつい「しかめっ面」になる。
としてはついつい「しかめっ面」になる。
フィールドに限らず、畑の隅や庭先でこの頃よく目に付くのは『オオアラセイトウ』の薄紫色です。
と云う事で、22日に家庭菜園の隅に咲いていたものをアップしてみます。
この花は中国原産で江戸時代に渡来し、鑑賞用に栽培されますが野生化しているものも多い。
別名は多くて「諸葛菜」「花大根」「紫花菜」や「紫金草」とも呼ばれますが、一番使われているのは「ショカッサイ」でしょうか?
「諸葛菜」は漢名で、三国志の諸葛孔明が食用に栽培を推奨した為だとする説が有ります。
オオアラセイトウ

 としてはついつい「しかめっ面」になる。
としてはついつい「しかめっ面」になる。フィールドに限らず、畑の隅や庭先でこの頃よく目に付くのは『オオアラセイトウ』の薄紫色です。
と云う事で、22日に家庭菜園の隅に咲いていたものをアップしてみます。
この花は中国原産で江戸時代に渡来し、鑑賞用に栽培されますが野生化しているものも多い。
別名は多くて「諸葛菜」「花大根」「紫花菜」や「紫金草」とも呼ばれますが、一番使われているのは「ショカッサイ」でしょうか?
「諸葛菜」は漢名で、三国志の諸葛孔明が食用に栽培を推奨した為だとする説が有ります。
オオアラセイトウ

タグ :植物
2010年03月25日 Posted by 松ぽっくり at 18:04 │Comments(0) │近所
なつかしき名の
朝から冷たい雨、フィールドはお休みです。
そこで、22日に田んぼで出会った『ハハコグサ』を取り上げて見ました。
野の草たちとの出会いを一年以上楽しんできたのに、春の七草の一つでもあるこの草をもらしていました。
茎や葉に白い綿毛が有り、冠毛がほうけ立つ様子から「ホウコグサ」と呼ばれ、それが訛って「ハハコグサ」になったそうです。
春の七草の方では「オギョウ(人形の意味)」と呼ばれます。
昔は草餅に使われていましたが、色がよく出る等の理由で「ヨモギ」に取って代わられました。
「老いて尚なつかしき名の母子草」 虚子
地味ながら、野の草の愛おしさを感じさせてくれる草です。
ハハコグサ

そこで、22日に田んぼで出会った『ハハコグサ』を取り上げて見ました。
野の草たちとの出会いを一年以上楽しんできたのに、春の七草の一つでもあるこの草をもらしていました。
茎や葉に白い綿毛が有り、冠毛がほうけ立つ様子から「ホウコグサ」と呼ばれ、それが訛って「ハハコグサ」になったそうです。
春の七草の方では「オギョウ(人形の意味)」と呼ばれます。
昔は草餅に使われていましたが、色がよく出る等の理由で「ヨモギ」に取って代わられました。
「老いて尚なつかしき名の母子草」 虚子
地味ながら、野の草の愛おしさを感じさせてくれる草です。
ハハコグサ

タグ :植物
2010年03月24日 Posted by 松ぽっくり at 14:41 │Comments(0) │田んぼ
においは・・・
曇り空の下、土手の桜は枝先にポツリポツリと色を見せ始めました。
ツバメが斜面すれすれに飛んでいる、そう言えばツバメは今日が初見になる。証拠写真を、と思ったがこれが至難の業、なんとかやっとシルエットだけ

土手の下に降りて見ると枯れススキの根元から「ニオイタチツボスミレ」が顔を出していた。顔を近づけて見たがやっぱり私の鼻にはにおいは届かない
東側の斜面に「トトキ」の若葉が目に付くようになった。先日は「ギシギシ」の新芽を頂きましたが、
春の味第2弾として今日は「トトキ」を少々頂いて胡麻和えにして頂く事に・・

ニオイタチツボスミレ

初燕

トトキの胡麻和え
ツバメが斜面すれすれに飛んでいる、そう言えばツバメは今日が初見になる。証拠写真を、と思ったがこれが至難の業、なんとかやっとシルエットだけ


土手の下に降りて見ると枯れススキの根元から「ニオイタチツボスミレ」が顔を出していた。顔を近づけて見たがやっぱり私の鼻にはにおいは届かない

東側の斜面に「トトキ」の若葉が目に付くようになった。先日は「ギシギシ」の新芽を頂きましたが、

春の味第2弾として今日は「トトキ」を少々頂いて胡麻和えにして頂く事に・・


ニオイタチツボスミレ

初燕

トトキの胡麻和え
タグ :旬の味
2010年03月23日 Posted by 松ぽっくり at 17:28 │Comments(0) │フィールド
さまざまな顔
今日の風は又冷たい、行きつ戻りつ春は中々一筋縄ではいかない!
近所の田んぼで「コオニタビラコ」が盛りを迎えていた。咲き始めの頃に取り上げたが、この時季になると又、様相が異なる。
様相が異なると云えば先日は地面すれすれで咲く「クサボケ」の画像をアップしたが、いつもより少し上流の手の入らない土手で今日出会った「クサボケ」も又様相を異にしていた。
時季、環境により、草木は様々な顔を見せてくれて楽しい。
「ヤマザクラ」の薄紅色が遠目にも山肌にその存在を教えている。
草刈りされない土手のクサボケ


最盛期のコオニタビラコ
近所の田んぼで「コオニタビラコ」が盛りを迎えていた。咲き始めの頃に取り上げたが、この時季になると又、様相が異なる。
様相が異なると云えば先日は地面すれすれで咲く「クサボケ」の画像をアップしたが、いつもより少し上流の手の入らない土手で今日出会った「クサボケ」も又様相を異にしていた。
時季、環境により、草木は様々な顔を見せてくれて楽しい。
「ヤマザクラ」の薄紅色が遠目にも山肌にその存在を教えている。
草刈りされない土手のクサボケ


最盛期のコオニタビラコ
タグ :植物
2010年03月22日 Posted by 松ぽっくり at 16:37 │Comments(0) │フィールド
編み笠を
雨は早々に上がったが強風が、その強風に乗って黄砂がすごく、山が見えなかった!
そろそろ『オドリコソウ』の咲く頃と思い以前見た農道に行って見ました。
農道の横の一角を被いつくすように白とピンクのタイプが分かれて咲いています。思っていたより早い!
この草も以前は農村の藪かげなどに普通に見られた様ですが最近は随分と少なくなりました。
「踊り子草」の名前は花の形が編み笠をかぶって踊っているように見える所から付けられたようです。
先日取り上げた外来種の「ヒメオドリコソウ」と比べると花も大きくてずっと見栄えがします。
大分風も収まって来たようだ。
 オドリコソウ
オドリコソウ


そろそろ『オドリコソウ』の咲く頃と思い以前見た農道に行って見ました。
農道の横の一角を被いつくすように白とピンクのタイプが分かれて咲いています。思っていたより早い!
この草も以前は農村の藪かげなどに普通に見られた様ですが最近は随分と少なくなりました。

「踊り子草」の名前は花の形が編み笠をかぶって踊っているように見える所から付けられたようです。
先日取り上げた外来種の「ヒメオドリコソウ」と比べると花も大きくてずっと見栄えがします。

大分風も収まって来たようだ。
 オドリコソウ
オドリコソウ

タグ :植物
2010年03月21日 Posted by 松ぽっくり at 17:14 │Comments(0) │花を訪ねて
春を代表する
今日は皆さんと岡部をブラついて来ました。
カツラの素朴な雄花を確認し、クロモジ、キブシなど木の花を愛でて来ました。
春を代表する花の一つ、スミレ類は「タチツボスミレ」「ヒメスミレ」「アリアケスミレ」などが確認出来ました。
その中から『アリアケスミレ』をアップしてみます。
白色から紅紫色まで変化に富む花の色を「有明の空」に見立てて「有明菫」となったようです。
このスミレも人家に近い所が好きなスミレの一つで、一般的には花弁に紫色のスジが入る事が多い。
風の強さと雲ゆきが案じられましたが、予定通り終了出来て一安心 (*^^)v
アリアケスミレ

カツラの素朴な雄花を確認し、クロモジ、キブシなど木の花を愛でて来ました。

春を代表する花の一つ、スミレ類は「タチツボスミレ」「ヒメスミレ」「アリアケスミレ」などが確認出来ました。
その中から『アリアケスミレ』をアップしてみます。
白色から紅紫色まで変化に富む花の色を「有明の空」に見立てて「有明菫」となったようです。

このスミレも人家に近い所が好きなスミレの一つで、一般的には花弁に紫色のスジが入る事が多い。
風の強さと雲ゆきが案じられましたが、予定通り終了出来て一安心 (*^^)v
アリアケスミレ

タグ :植物
2010年03月20日 Posted by 松ぽっくり at 21:52 │Comments(0) │観察会
ほぼ一年中
河原の木々は様々な色の若葉を枝先に灯し始め、土手の斜面もツルボ、ヨモギ、スズメノエンドウなどの若葉でたちまち緑の領分が広がりました。多少の風の冷たさは最早ものの数では無いようだ。
手が入る前の田んぼもレンゲを筆頭にタビラコ等々が元気です。
トキワ(常磐)の名前のようにほぼ一年中花が見られる『トキワハゼ』もこの時季のものが一番きれいに見える。
花の形が似ている「ムラサキサギゴケ」は根元から匐枝を出してふえるので識別できます。
「毎年よ彼岸の入りに寒いのは」と正岡子規がお母さんの言葉をそのまま句にしたと言うが、まさしく今日の風はそこそこ冷たい。
 トキワハゼ
トキワハゼ

手が入る前の田んぼもレンゲを筆頭にタビラコ等々が元気です。
トキワ(常磐)の名前のようにほぼ一年中花が見られる『トキワハゼ』もこの時季のものが一番きれいに見える。

花の形が似ている「ムラサキサギゴケ」は根元から匐枝を出してふえるので識別できます。
「毎年よ彼岸の入りに寒いのは」と正岡子規がお母さんの言葉をそのまま句にしたと言うが、まさしく今日の風はそこそこ冷たい。
 トキワハゼ
トキワハゼ
タグ :植物
2010年03月19日 Posted by 松ぽっくり at 16:58 │Comments(0) │フィールド
地表すれすれで
暑さ寒さも・・・と言われる今日は彼岸の入り、春はいよいよ佳境に入る。
そんなタイミングに合わせるように『クサボケ』がオレンジ色の目立つ花を開いた。
枯草に埋もれて地表すれすれで咲いているがこれでもれっきとした木本です。
普通ほっておけば最高100cm位になりますが、定期的に草刈りが行われるこの様な斜面ではせいぜい20cmがいい所です。
それでも花は直径3センチもある立派な花を付けます。
バラ科のこの木は秋に3~4㌢の黄色い果実を付ける、この果実は素晴らしい香りと酸味があって果実酒に最適、と言われるがまだ試した事は無い (>_<)
昨日、桜の開花宣言は出されたが、土手のソメイヨシノは後ひと押しと云った所です。
クサボケ


そんなタイミングに合わせるように『クサボケ』がオレンジ色の目立つ花を開いた。

枯草に埋もれて地表すれすれで咲いているがこれでもれっきとした木本です。
普通ほっておけば最高100cm位になりますが、定期的に草刈りが行われるこの様な斜面ではせいぜい20cmがいい所です。
それでも花は直径3センチもある立派な花を付けます。

バラ科のこの木は秋に3~4㌢の黄色い果実を付ける、この果実は素晴らしい香りと酸味があって果実酒に最適、と言われるがまだ試した事は無い (>_<)

昨日、桜の開花宣言は出されたが、土手のソメイヨシノは後ひと押しと云った所です。
クサボケ

タグ :植物
2010年03月18日 Posted by 松ぽっくり at 16:09 │Comments(0) │フィールド
並んで
昨日に比べると気温の差はかなりあるが、あまり寒いとは感じなかった。
お地蔵さん下の「ウラシマソウ」の釣り糸が大分伸び出して、その横の「ドクウツギ」に絡んだ『アケビ』の雄花と雌花が並んで咲きました。去年とほぼ同時期です。
去年も花の数は沢山咲きましたが、実を付けたのは一個だけ、その一個も熟す前にいつの間にか消えていました。はたして今年はどうでしょう
ジョウビタキの動きが少しゆったり感じます、そろそろ北の国へ帰る日も近いようだ。
アケビ左雌花、右雄花


ウラシマソウ未完品

お地蔵さん下の「ウラシマソウ」の釣り糸が大分伸び出して、その横の「ドクウツギ」に絡んだ『アケビ』の雄花と雌花が並んで咲きました。去年とほぼ同時期です。
去年も花の数は沢山咲きましたが、実を付けたのは一個だけ、その一個も熟す前にいつの間にか消えていました。はたして今年はどうでしょう

ジョウビタキの動きが少しゆったり感じます、そろそろ北の国へ帰る日も近いようだ。
アケビ左雌花、右雄花


ウラシマソウ未完品
タグ :植物
2010年03月17日 Posted by 松ぽっくり at 18:29 │Comments(2) │フィールド
人家近くが
雨は予想外に早く上がってくれて、用事が事の他はかどりました。
風の方は予想通りかなり強い、そして気温は20℃を超える勢い、まるで初夏!
土手下の水路沿いのコースを行くと敷石の境に『ヒメスミレ』が咲いていました。
このスミレも人家近くが好きなスミレで、山地ではほとんど見かけません。
アスファルトの隙間や空地、鉄道の線路わきなど日当たりのよい、乾き気味の所が好きなようです
「スミレ」とは葉の形で見分ける事ができます(スミレの葉は長く、葉柄に翼があります)
昨夜の雨とこの気温で土手の斜面は一気に緑色が広がりました。
ヒメスミレ


風の方は予想通りかなり強い、そして気温は20℃を超える勢い、まるで初夏!
土手下の水路沿いのコースを行くと敷石の境に『ヒメスミレ』が咲いていました。
このスミレも人家近くが好きなスミレで、山地ではほとんど見かけません。
アスファルトの隙間や空地、鉄道の線路わきなど日当たりのよい、乾き気味の所が好きなようです

「スミレ」とは葉の形で見分ける事ができます(スミレの葉は長く、葉柄に翼があります)
昨夜の雨とこの気温で土手の斜面は一気に緑色が広がりました。
ヒメスミレ

タグ :植物
2010年03月16日 Posted by 松ぽっくり at 17:03 │Comments(0) │フィールド
有毒で
薄曇りだが風も弱く、穏やかな日です。
土手の下の放置されたミカン畑で『ムラサキケマン』が咲き始めました。
野山では普通に見られる草ですが、このフィールドではあまり多くありません。
ケシ科のこの草は「ウスバシロチョウ」の食草ですが、有毒です。
県内での方言に「ネコイラズ」「ハッカケ」などがあり、この方言からも有毒である事がうかがい知れます。
漢字は「紫華鬘」で、華鬘とは仏殿の天井からつるす飾り物の事で、花穂をこれに見立てたようです。
土手の「ソメイヨシノ」の蕾も膨らみが一段と増してきました。


ムラサキケマン
土手の下の放置されたミカン畑で『ムラサキケマン』が咲き始めました。

野山では普通に見られる草ですが、このフィールドではあまり多くありません。
ケシ科のこの草は「ウスバシロチョウ」の食草ですが、有毒です。
県内での方言に「ネコイラズ」「ハッカケ」などがあり、この方言からも有毒である事がうかがい知れます。

漢字は「紫華鬘」で、華鬘とは仏殿の天井からつるす飾り物の事で、花穂をこれに見立てたようです。
土手の「ソメイヨシノ」の蕾も膨らみが一段と増してきました。


ムラサキケマン
タグ :植物
2010年03月15日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(0) │フィールド
端正な
桜の梢で「モズ」が小声でぐぜっている、秋の鋭い高鳴きに比べると別鳥のように可愛らしい。 もう繁殖期に入っているのだろう。
もう繁殖期に入っているのだろう。
茶畑の横の空地に『キュウリグサ』が2㍉程の小さな花を付け始めました。小さな小さな花だがよく見ると中々端正な顔立ちをしています。アップで花の形を見ると分かると思いますが「ワスレナグサ」の仲間です。
葉を揉むとキュウリの匂いがする、と云う事で「胡瓜草」の名前が付きました。しかし私の鼻には感じません
空地や畑のそばで「ギシギシ」の葉が目立ってきました、帰りに新芽を少し摘ませてもらい、酢味噌和えにして、夕食の一品に、
ぬめりと酸味がそこそこ新鮮でした。

キュウリグサ


ギシギシの酢味噌和え
 もう繁殖期に入っているのだろう。
もう繁殖期に入っているのだろう。茶畑の横の空地に『キュウリグサ』が2㍉程の小さな花を付け始めました。小さな小さな花だがよく見ると中々端正な顔立ちをしています。アップで花の形を見ると分かると思いますが「ワスレナグサ」の仲間です。

葉を揉むとキュウリの匂いがする、と云う事で「胡瓜草」の名前が付きました。しかし私の鼻には感じません

空地や畑のそばで「ギシギシ」の葉が目立ってきました、帰りに新芽を少し摘ませてもらい、酢味噌和えにして、夕食の一品に、

ぬめりと酸味がそこそこ新鮮でした。


キュウリグサ


ギシギシの酢味噌和え
タグ :自然
2010年03月14日 Posted by 松ぽっくり at 18:39 │Comments(2) │フィールド
2m足らずの
4月の陽気との事で上着も要らない感じ!その代わり風の強さは相当のものがある。
ウォーキングのお仲間の数も多い。
土手の横のブロック置き場の隙間に生えている、2m足らずの小さな『ヤマモモ』の木が花を付けました。
恐らく鳥が種を運んだものだろうが、しっかり根付いている。
ヤマモモも雌雄別株でこの木は雄株なので花は咲いても実はならない。花と言っても雄花はおしべの集まりで花には見えない。
漢字では「山桃」となり、恐らく紅く熟した実を桃に見立てたものと思われる。
帰りは向かい風、ペダルが重かった。

ヤマモモ雄花

ウォーキングのお仲間の数も多い。

土手の横のブロック置き場の隙間に生えている、2m足らずの小さな『ヤマモモ』の木が花を付けました。
恐らく鳥が種を運んだものだろうが、しっかり根付いている。
ヤマモモも雌雄別株でこの木は雄株なので花は咲いても実はならない。花と言っても雄花はおしべの集まりで花には見えない。

漢字では「山桃」となり、恐らく紅く熟した実を桃に見立てたものと思われる。
帰りは向かい風、ペダルが重かった。


ヤマモモ雄花

タグ :植物
2010年03月13日 Posted by 松ぽっくり at 12:55 │Comments(0) │フィールド
黄色の乳液が
小学校の裏の土手の斜面で『クサノオウ』が咲きだしました。ほぼ去年と同じ時季です。
「クサノオウ」はケシ科、茎や葉を切ると黄色の乳液が出る、この乳液は有毒だが鎮静や鎮痛の作用もあり、尾崎紅葉が胃がんの痛み止めに使ったとも言われている。
名前の由来は薬草の王様と云う意味で「草の王」とか、他にも諸説ある。
ちなみに我が国の生薬の歴史は古く縄文の時代に遡るとの事です。
フィールドも植栽の「ユキヤナギ」が無数の小さな花で真っ白になって、そこそこ冷たい風に揺れています。
クサノオウ


ユキヤナギ
「クサノオウ」はケシ科、茎や葉を切ると黄色の乳液が出る、この乳液は有毒だが鎮静や鎮痛の作用もあり、尾崎紅葉が胃がんの痛み止めに使ったとも言われている。
名前の由来は薬草の王様と云う意味で「草の王」とか、他にも諸説ある。
ちなみに我が国の生薬の歴史は古く縄文の時代に遡るとの事です。
フィールドも植栽の「ユキヤナギ」が無数の小さな花で真っ白になって、そこそこ冷たい風に揺れています。
クサノオウ


ユキヤナギ
タグ :植物