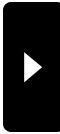稜が有る
アマドコロ

誰かに呼ばれた訳ではないが、いつもと逆の川下に向かって行ってみようと、土手の斜面をチャリのブレーキを思いっきり握りながら半分程おりた時、懐かしげな草姿が目に入った。
このフィールドでは姿を消したと思っていた『アマドコロ』が群生していた。
背丈は40cm程と大きくはないが株数は結構有る。嬉し懐かしい出会いでした。
「ナルコユリ」と似た姿をしているが、茎に稜が有る事や葉の幅がやや広い事などで識別できる。
円柱形の地下茎が横に延び毎年その先に一本の茎を立てるが、その地下茎がヤマノイモ科の「オニドコロ」に似ていて、甘味が有るので「甘野老」の名が付いたようです。
明日は雨になるらしい。


誰かに呼ばれた訳ではないが、いつもと逆の川下に向かって行ってみようと、土手の斜面をチャリのブレーキを思いっきり握りながら半分程おりた時、懐かしげな草姿が目に入った。
このフィールドでは姿を消したと思っていた『アマドコロ』が群生していた。
背丈は40cm程と大きくはないが株数は結構有る。嬉し懐かしい出会いでした。
「ナルコユリ」と似た姿をしているが、茎に稜が有る事や葉の幅がやや広い事などで識別できる。
円柱形の地下茎が横に延び毎年その先に一本の茎を立てるが、その地下茎がヤマノイモ科の「オニドコロ」に似ていて、甘味が有るので「甘野老」の名が付いたようです。
明日は雨になるらしい。
タグ :植物
2011年04月30日 Posted by 松ぽっくり at 17:31 │Comments(0) │フィールド
新枝の下の方
ムクノキ
直径5ミリ程の雄花
朝からよく晴れて若葉が目にしみます。「エノキ」は早くも5mm程の青い実を沢山付けています。その横の『ムクノキ』は今が花どき、と云っても若葉と同じ様な色の小さな花はほとんど目立ちません。そして雄花は新枝の下の方にかたまって付くので比較的見付けやすいのですが、雌花は上部の葉の脇に2~3個付くのですが、今回は見つかりませんでした。(木に登るかハシゴでも無いとムリかも)
この木の葉は両面とも短い毛が有って著しくザラつく。このザラツキを利用して漆器の木地の研磨に使われたようです。
「フジ」の花があちこちで目立つようになりました。


直径5ミリ程の雄花

朝からよく晴れて若葉が目にしみます。「エノキ」は早くも5mm程の青い実を沢山付けています。その横の『ムクノキ』は今が花どき、と云っても若葉と同じ様な色の小さな花はほとんど目立ちません。そして雄花は新枝の下の方にかたまって付くので比較的見付けやすいのですが、雌花は上部の葉の脇に2~3個付くのですが、今回は見つかりませんでした。(木に登るかハシゴでも無いとムリかも)
この木の葉は両面とも短い毛が有って著しくザラつく。このザラツキを利用して漆器の木地の研磨に使われたようです。
「フジ」の花があちこちで目立つようになりました。

タグ :植物
2011年04月29日 Posted by 松ぽっくり at 17:13 │Comments(0) │フィールド
一画を黄色く
オヘビイチゴ
5小葉からなる葉
予想以上に回復は早く、朝から快晴。ただ西風はかなり強い。
河原の茂みから「オオヨシキリ」の声が聞こえている。いよいよ夏鳥のシーズンに入ってきた。
土手横の空地の一画を黄色く彩って『オヘビイチゴ』が咲き始めた。
「ヘビイチゴ」とは属が異なるので赤いイチゴ状のものは出来ないが
花は似ている。
葉の形は5小葉から成り、3小葉のヘビイチゴとの識別点になる。(ただ茎の上部に付く葉は3小葉のものもある)
名前は「ヘビイチゴ」より大型と云う意味で「雄蛇苺」となりました。

5小葉からなる葉

予想以上に回復は早く、朝から快晴。ただ西風はかなり強い。
河原の茂みから「オオヨシキリ」の声が聞こえている。いよいよ夏鳥のシーズンに入ってきた。
土手横の空地の一画を黄色く彩って『オヘビイチゴ』が咲き始めた。
「ヘビイチゴ」とは属が異なるので赤いイチゴ状のものは出来ないが
花は似ている。
葉の形は5小葉から成り、3小葉のヘビイチゴとの識別点になる。(ただ茎の上部に付く葉は3小葉のものもある)
名前は「ヘビイチゴ」より大型と云う意味で「雄蛇苺」となりました。
タグ :植物
2011年04月28日 Posted by 松ぽっくり at 16:11 │Comments(0) │フィールド
小型版
マメグンバイナズナ

東向き斜面で『マメグンバイナズナ』が一斉に姿を現しました。花の下に幾つも果実を付けているので何日か前に咲きだしたのでしょうが、気が付きませんでした。
成長すると50cm程になるのですが、最初は10cm程でも花を付けます。
「グンバイナズナ」の小型版と云う事で「豆軍配薺」の名が付きましたが、属は異なり小さな丸い実の中には種は2個だけです。ちなみに「グンバイナズナ」のほうは沢山入っています。
北アメリカ原産で明治中期に渡来したと云われ、道端や空地などに普通に見られる草ですが整った形のものはドライフラワーにしても中々です。
雨になりました。この所天気の移り変わりが早く、明日の昼には回復するようです。


東向き斜面で『マメグンバイナズナ』が一斉に姿を現しました。花の下に幾つも果実を付けているので何日か前に咲きだしたのでしょうが、気が付きませんでした。
成長すると50cm程になるのですが、最初は10cm程でも花を付けます。
「グンバイナズナ」の小型版と云う事で「豆軍配薺」の名が付きましたが、属は異なり小さな丸い実の中には種は2個だけです。ちなみに「グンバイナズナ」のほうは沢山入っています。
北アメリカ原産で明治中期に渡来したと云われ、道端や空地などに普通に見られる草ですが整った形のものはドライフラワーにしても中々です。
雨になりました。この所天気の移り変わりが早く、明日の昼には回復するようです。
タグ :植物
2011年04月27日 Posted by 松ぽっくり at 18:30 │Comments(0) │フィールド
疎林縁で
コゴメウツギ

お地蔵さんの上の疎林縁で『コゴメウツギ』が咲き始めました。この木は図鑑の解説をして「やたらと生えている」と言わしめるほど海岸付近から山間部にかけてごく普通に見る事が出来ます。バラ科の落葉低木で叢生し、高さは1~2m。
直径5mm程の花は花弁5とガク片5が同じ白色なので一見花弁が10枚の様に感じる。
名前は「小米空木」と書き、ウツギに似た白い小さな花を小米に見立てたらしい。
南西の強い風に柳絮はたちまち彼方へ消えていきました。


お地蔵さんの上の疎林縁で『コゴメウツギ』が咲き始めました。この木は図鑑の解説をして「やたらと生えている」と言わしめるほど海岸付近から山間部にかけてごく普通に見る事が出来ます。バラ科の落葉低木で叢生し、高さは1~2m。
直径5mm程の花は花弁5とガク片5が同じ白色なので一見花弁が10枚の様に感じる。
名前は「小米空木」と書き、ウツギに似た白い小さな花を小米に見立てたらしい。
南西の強い風に柳絮はたちまち彼方へ消えていきました。
タグ :植物
2011年04月26日 Posted by 松ぽっくり at 16:59 │Comments(0) │フィールド
根元で
ムシクサ

まだ手の入っていない田んぼは今、草たちが我も我もとわが世の春を謳歌している。
畦に腰をおろし、見渡してみると「レンゲ」を筆頭に「ハハコグサ」など15種を数える事が出来た。そしてその殆どが在来種、外来種は「アメリカフウロ」だけでした。
そんな草たちの根元を覗きこんでみると、草丈15cm程の『ムシクサ』も小さな白い花を付けていました。花は直径2~3mm程、ガク片は葉状で白い花弁よりはるかに大きい。それにしても目立たない草です。
「虫草」の名前はゾウムシの仲間がこの草の子房に卵を生み付けて果実の様な「虫えい」になるのでこの名が付いたようです。
西の風は時折強くふいて、体を持っていかれそうになります。


まだ手の入っていない田んぼは今、草たちが我も我もとわが世の春を謳歌している。
畦に腰をおろし、見渡してみると「レンゲ」を筆頭に「ハハコグサ」など15種を数える事が出来た。そしてその殆どが在来種、外来種は「アメリカフウロ」だけでした。
そんな草たちの根元を覗きこんでみると、草丈15cm程の『ムシクサ』も小さな白い花を付けていました。花は直径2~3mm程、ガク片は葉状で白い花弁よりはるかに大きい。それにしても目立たない草です。
「虫草」の名前はゾウムシの仲間がこの草の子房に卵を生み付けて果実の様な「虫えい」になるのでこの名が付いたようです。
西の風は時折強くふいて、体を持っていかれそうになります。
タグ :植物
2011年04月25日 Posted by 松ぽっくり at 18:18 │Comments(0) │フィールド
林縁の
カマツカ

空は花曇り、明日に向かってゆっくりと下り坂の様です。
突き当たりの土手下、林縁の『カマツカ』は例年に比べ若干遅れて咲き始めました。直径1センチ程の小さな花ですが沢山の雄しべが有り、バラ科の特徴の一つを見せています。
何処にでも有る木ですが、よく見るとリンゴの花にも似て中々清楚で美しい花です。
昔は牛に鼻輪を付ける時、この木で穴を開けたと云われ「ウシコロシ」の別名もあります。
土手の桜もすっかり葉桜になり、野山は若葉の季節に突入です。


空は花曇り、明日に向かってゆっくりと下り坂の様です。
突き当たりの土手下、林縁の『カマツカ』は例年に比べ若干遅れて咲き始めました。直径1センチ程の小さな花ですが沢山の雄しべが有り、バラ科の特徴の一つを見せています。
何処にでも有る木ですが、よく見るとリンゴの花にも似て中々清楚で美しい花です。
昔は牛に鼻輪を付ける時、この木で穴を開けたと云われ「ウシコロシ」の別名もあります。
土手の桜もすっかり葉桜になり、野山は若葉の季節に突入です。
タグ :植物
2011年04月22日 Posted by 松ぽっくり at 17:40 │Comments(0) │フィールド
触手のような
ドクウツギ雌花
土手の下、「アケビ」や「ツルウメモドキ」に思い切り絡みつかれて気息奄々の『ドクウツギ』それでも上に伸びた枝に頑張って花を付けていた。
雄花は終盤を迎え、雌花はイソギンチャクの触手の様な花柱(雌しべの先)を広げています。この一見花柱だけの様に見える雌花ですが、じつは1ミリ程の花弁と2ミリ程のガク片が有ります。
猛毒植物として知られ「イチロベエゴロシ」なる強面の別名を持つ「毒空木」ですが、蔓植物に絡みつかれると見るも痛ましい状態に追い込まれてしまいます。

土手の下、「アケビ」や「ツルウメモドキ」に思い切り絡みつかれて気息奄々の『ドクウツギ』それでも上に伸びた枝に頑張って花を付けていた。
雄花は終盤を迎え、雌花はイソギンチャクの触手の様な花柱(雌しべの先)を広げています。この一見花柱だけの様に見える雌花ですが、じつは1ミリ程の花弁と2ミリ程のガク片が有ります。
猛毒植物として知られ「イチロベエゴロシ」なる強面の別名を持つ「毒空木」ですが、蔓植物に絡みつかれると見るも痛ましい状態に追い込まれてしまいます。
タグ :植物
2011年04月21日 Posted by 松ぽっくり at 17:46 │Comments(0) │フィールド
勝ち組の
マツバウンラン

風もそれほど有る訳でもないが、か細い茎の先に花を付けた『マツバウンラン』がこまかく揺れています。
この草も今年は勝ち組の一つ、至る所に進出していてやたら目に付きます。空地などに群生している様は鑑賞用の花卉の趣も有りますが、ゴルフ場などに発生して問題になる事も有るようです。
それに引き換え「シロツメクサ」は今頃になってようやく存在を示す様になって来ました。昨年、一昨年に比べ出足がかなり遅い!今年は負け組か?
今日は「穀雨」この時季は植物の成長に欠かせない恵みの雨が多くなる頃。


風もそれほど有る訳でもないが、か細い茎の先に花を付けた『マツバウンラン』がこまかく揺れています。
この草も今年は勝ち組の一つ、至る所に進出していてやたら目に付きます。空地などに群生している様は鑑賞用の花卉の趣も有りますが、ゴルフ場などに発生して問題になる事も有るようです。
それに引き換え「シロツメクサ」は今頃になってようやく存在を示す様になって来ました。昨年、一昨年に比べ出足がかなり遅い!今年は負け組か?
今日は「穀雨」この時季は植物の成長に欠かせない恵みの雨が多くなる頃。
タグ :植物
2011年04月20日 Posted by 松ぽっくり at 17:54 │Comments(0) │フィールド
並んで
都 草

西風がかなり強力で吹き飛ばされそうになります。
東側の斜面で『ミヤコグサ』が「ニガナ」と並んで咲き始めていました。この草の場合は遅れる事無く、ほぼ例年どおりのお出ましです。これから秋口まで長いお付き合いになるのでしょう。
この仲間「ミヤコグサ属」は地中海沿岸を中心に多くの種が分布しているようですが、我国には「ミヤコグサ」ただ一種が分布するだけです。ただ最近は外国のお仲間が、密やかに入国されているようで少なくとも3種は確認が取れています。


西風がかなり強力で吹き飛ばされそうになります。
東側の斜面で『ミヤコグサ』が「ニガナ」と並んで咲き始めていました。この草の場合は遅れる事無く、ほぼ例年どおりのお出ましです。これから秋口まで長いお付き合いになるのでしょう。
この仲間「ミヤコグサ属」は地中海沿岸を中心に多くの種が分布しているようですが、我国には「ミヤコグサ」ただ一種が分布するだけです。ただ最近は外国のお仲間が、密やかに入国されているようで少なくとも3種は確認が取れています。
タグ :植物
2011年04月19日 Posted by 松ぽっくり at 17:21 │Comments(0) │フィールド
ケシ科の
ヤマエンゴサク

「ジロボウエンゴサク」に始まり、「ムラサキケマン」「ミヤマキケマン」とケシ科の同じ様な形の花を見て、最後のしめに『ヤマエンゴサク』を見たくなって探しに行って来ました。
以前の記憶を引っ張り出しながら、林道をゆくと沢の斜面は「ニリンソウ」が一面に咲いて今が盛り。二つ目の沢も同様です。車を置いて端からじっくりと見ていきます。ニリンソウ、ナガバノスミレサイシン、イワボタン、ミツバコンロンソウ、そしてニリンソウと並んで咲いていました!少し盛りは過ぎた感じですが、小さなパラパラした葉の中から花茎を立てていました。この花の葉は変化が多く、図鑑によって葉の写真の形がちがっていて紛らわしい。
「山延胡索」の名前は山に生える延胡索の意味。延胡索はこの仲間の漢名でそれがそのまま使われている。
塊茎は漢方で鎮痛薬として古くから用いられているようです。


「ジロボウエンゴサク」に始まり、「ムラサキケマン」「ミヤマキケマン」とケシ科の同じ様な形の花を見て、最後のしめに『ヤマエンゴサク』を見たくなって探しに行って来ました。
以前の記憶を引っ張り出しながら、林道をゆくと沢の斜面は「ニリンソウ」が一面に咲いて今が盛り。二つ目の沢も同様です。車を置いて端からじっくりと見ていきます。ニリンソウ、ナガバノスミレサイシン、イワボタン、ミツバコンロンソウ、そしてニリンソウと並んで咲いていました!少し盛りは過ぎた感じですが、小さなパラパラした葉の中から花茎を立てていました。この花の葉は変化が多く、図鑑によって葉の写真の形がちがっていて紛らわしい。
「山延胡索」の名前は山に生える延胡索の意味。延胡索はこの仲間の漢名でそれがそのまま使われている。
塊茎は漢方で鎮痛薬として古くから用いられているようです。
タグ :植物
2011年04月18日 Posted by 松ぽっくり at 17:28 │Comments(0) │花を訪ねて
思いがけない
シロバナハンショウヅル
「月に叢雲花に風」と云う事で南の風が強く、土手の斜面は雪が降ったようになっています。
気温も高く上着を脱いてもまだ足りない感じ。
お地蔵さんの上の林の境、『シロバナハンショウズル』が金網に絡んで丸い蕾を沢山付けていたが、今日トップバッターが3~4個開花していた。
キンポウゲ科には多いが白い花弁の様に見えるのはガク片。垂れ下って咲くその形から「白花半鐘蔓」の名前が付きました。
山地では時々見かけますが、思いがけない出会いでした。
夜ひと雨あるらしい。朝までに上がってくれる事を祈りたい。

「月に叢雲花に風」と云う事で南の風が強く、土手の斜面は雪が降ったようになっています。
気温も高く上着を脱いてもまだ足りない感じ。
お地蔵さんの上の林の境、『シロバナハンショウズル』が金網に絡んで丸い蕾を沢山付けていたが、今日トップバッターが3~4個開花していた。
キンポウゲ科には多いが白い花弁の様に見えるのはガク片。垂れ下って咲くその形から「白花半鐘蔓」の名前が付きました。
山地では時々見かけますが、思いがけない出会いでした。
夜ひと雨あるらしい。朝までに上がってくれる事を祈りたい。
タグ :植物
2011年04月15日 Posted by 松ぽっくり at 17:03 │Comments(2) │フィールド
数にものを言わせて
スズメノエンドウ ↓ カスマグサ


土手の桜は時折の風に桜ふぶきとなって足元や斜面を斑に彩っています。その斜面では小さな花が数にものを言わせて目に付くようになって来ました。
「スズメノエンドウ」「カスマグサ」「コメツブツメクサ」「ノミノツヅリ」などです。
『スズメノエンドウ』の花は約4ミリ程、『カスマグサ』の方が若干大きくて7ミリ程です。どちらも「マメ科」で花の後、豆のサヤを付けますが、中の豆の数は「スズメ・・・」の方が2個、「カスマ・・・」の方が大体4個と決まっています。
暑くなく、寒くなく、いい陽気になって来ました。そぞろ歩きには最適です。


土手の桜は時折の風に桜ふぶきとなって足元や斜面を斑に彩っています。その斜面では小さな花が数にものを言わせて目に付くようになって来ました。
「スズメノエンドウ」「カスマグサ」「コメツブツメクサ」「ノミノツヅリ」などです。
『スズメノエンドウ』の花は約4ミリ程、『カスマグサ』の方が若干大きくて7ミリ程です。どちらも「マメ科」で花の後、豆のサヤを付けますが、中の豆の数は「スズメ・・・」の方が2個、「カスマ・・・」の方が大体4個と決まっています。
暑くなく、寒くなく、いい陽気になって来ました。そぞろ歩きには最適です。
2011年04月14日 Posted by 松ぽっくり at 16:35 │Comments(0) │フィールド
結実しない
ゴヨウアケビ
葉と雄花
南寄りの強い風で、初夏の様な暖かさ、と云うか暑さを感じる程!
先日の「アケビ」のそばで『ゴヨウアケビ』の花が強風にちぎれんばかりに振れている。
以前にも書いたが「ゴヨウアケビ」は「アケビ」と「ミツバアケビ」が自然交配したもので、葉は両方の特徴を見せて5小葉、ふちには波状のキョシがある。花は「ミツバアケビ」に似た色で、雄花と雌花は有るのですが、残念ながら結実しません。

葉と雄花

南寄りの強い風で、初夏の様な暖かさ、と云うか暑さを感じる程!
先日の「アケビ」のそばで『ゴヨウアケビ』の花が強風にちぎれんばかりに振れている。
以前にも書いたが「ゴヨウアケビ」は「アケビ」と「ミツバアケビ」が自然交配したもので、葉は両方の特徴を見せて5小葉、ふちには波状のキョシがある。花は「ミツバアケビ」に似た色で、雄花と雌花は有るのですが、残念ながら結実しません。
タグ :植物
2011年04月13日 Posted by 松ぽっくり at 16:02 │Comments(0) │フィールド
埋もれながら
姫 萩

風が強い!風向きは南東寄りだが結構冷たい風です。
今年も他の草に埋もれながら『ヒメハギ』が若干遅れ気味ではありますが咲き始めました。
独特の形状の花は羽を広げた鳥の様にも見えます。その左右に広がって花弁の様に見えるのは5片有るガクの2片。花弁は筒状で先端が房状に裂けている。いかにも何か意味の有りそうな裂け方ですがその働きはよく解っていません。
常緑の多年草で花が終わると草丈は伸びて30㎝程になりますが、その頃になると周囲の草が伸びてその中に埋没し忘れ去られる事になります。


風が強い!風向きは南東寄りだが結構冷たい風です。
今年も他の草に埋もれながら『ヒメハギ』が若干遅れ気味ではありますが咲き始めました。
独特の形状の花は羽を広げた鳥の様にも見えます。その左右に広がって花弁の様に見えるのは5片有るガクの2片。花弁は筒状で先端が房状に裂けている。いかにも何か意味の有りそうな裂け方ですがその働きはよく解っていません。
常緑の多年草で花が終わると草丈は伸びて30㎝程になりますが、その頃になると周囲の草が伸びてその中に埋没し忘れ去られる事になります。
タグ :植物
2011年04月12日 Posted by 松ぽっくり at 17:25 │Comments(0) │フィールド
控えめに
カナビキソウ

土手斜面の草たちにも栄枯盛衰が有る。昨年の春は「スズメノエンドウ」や「シロツメクサ」がハバを利かせていたが今年は何処でも「カラスノエンドウ」がかなり目立つ。
そんな中、毎年控えめに細々と出てくるのが『カナビキソウ』白い小さな花をキリッと開いているがほとんど目立たない。
もしかするとこの草は「半寄生」で自分でも養分を作りますが、他の植物からも養分をいただくと云う生活に多少引け目を感じているのかも知れない
ちなみに「ビャクダン科」には半寄生植物が多いらしい。


土手斜面の草たちにも栄枯盛衰が有る。昨年の春は「スズメノエンドウ」や「シロツメクサ」がハバを利かせていたが今年は何処でも「カラスノエンドウ」がかなり目立つ。
そんな中、毎年控えめに細々と出てくるのが『カナビキソウ』白い小さな花をキリッと開いているがほとんど目立たない。

もしかするとこの草は「半寄生」で自分でも養分を作りますが、他の植物からも養分をいただくと云う生活に多少引け目を感じているのかも知れない

ちなみに「ビャクダン科」には半寄生植物が多いらしい。
タグ :植物
2011年04月12日 Posted by 松ぽっくり at 00:04 │Comments(0) │フィールド
水路の脇の
ナツグミ
葉や花に鱗状毛が目立つ
水路の脇の『ナツグミ』も満開になりました。顔を近づけると割と良い香りがします。
5月の末から6月にかけて赤い実を沢山付けます。昨年は完熟したら味を見せてもらうつもりでしたが、しばらく忘れていて、行ってみると人か鳥か解りませんがすでに後の祭りでした。
予報に反して雲が厚く、日差しが無い分風が吹くと肌寒さを感じます(上着を薄手のものに変たせいもあるが) もう一つの予想の方は的中して桜の下はファミリーやら町内会やらで大賑わい。

葉や花に鱗状毛が目立つ

水路の脇の『ナツグミ』も満開になりました。顔を近づけると割と良い香りがします。
5月の末から6月にかけて赤い実を沢山付けます。昨年は完熟したら味を見せてもらうつもりでしたが、しばらく忘れていて、行ってみると人か鳥か解りませんがすでに後の祭りでした。

予報に反して雲が厚く、日差しが無い分風が吹くと肌寒さを感じます(上着を薄手のものに変たせいもあるが) もう一つの予想の方は的中して桜の下はファミリーやら町内会やらで大賑わい。
タグ :植物
2011年04月10日 Posted by 松ぽっくり at 17:31 │Comments(0) │フィールド
風に揺れて
アケビ
左雄花、右雌花
雨上がり、「タンポポ」はまだ一様に花をすぼめている。柳の下、「アカメガシワ」に絡みついた『アケビ』の花が風に揺れている。こちらの花は雨でもすぼむ事は無い。
いくつかの花の具合から咲き始めて何日か経っているようだが、それでも昨年や一昨年に比べると3週間近く遅い事になる。
天気の回復は急で早くも日が出て来ました。土手の桜の開花もかなり進み、明日は花見の人々で賑わう事でしょう。

左雄花、右雌花

雨上がり、「タンポポ」はまだ一様に花をすぼめている。柳の下、「アカメガシワ」に絡みついた『アケビ』の花が風に揺れている。こちらの花は雨でもすぼむ事は無い。
いくつかの花の具合から咲き始めて何日か経っているようだが、それでも昨年や一昨年に比べると3週間近く遅い事になる。
天気の回復は急で早くも日が出て来ました。土手の桜の開花もかなり進み、明日は花見の人々で賑わう事でしょう。
タグ :植物
2011年04月09日 Posted by 松ぽっくり at 16:01 │Comments(0) │フィールド
若葉と共に
サルトリイバラ
これは雄しべの無い雌花の集まり
風がつよい!川下から川上に南西の風が強力にふいている。ペダルが軽く、時々こがなくても進む。帰りは別の道にしよう。
お地蔵さんの上の林縁に『サルトリイバラ』が若葉と共に目立たない花をぶら下げていた。花は目立たないが、秋に付ける赤い実はよく目立ち、丸い大きな葉は団子を包むのに使われるなど昔から人々に親しまれてきた。
以前はユリ科シオデ属に分類されていましたが、最近の新分類法ではシオデ属が独立して「シオデ科」となったようです。
どうやら雨は夜までもってくれそう、と思っていたら落ちてきた。

これは雄しべの無い雌花の集まり

風がつよい!川下から川上に南西の風が強力にふいている。ペダルが軽く、時々こがなくても進む。帰りは別の道にしよう。

お地蔵さんの上の林縁に『サルトリイバラ』が若葉と共に目立たない花をぶら下げていた。花は目立たないが、秋に付ける赤い実はよく目立ち、丸い大きな葉は団子を包むのに使われるなど昔から人々に親しまれてきた。
以前はユリ科シオデ属に分類されていましたが、最近の新分類法ではシオデ属が独立して「シオデ科」となったようです。

どうやら雨は夜までもってくれそう、と思っていたら落ちてきた。
タグ :植物
2011年04月08日 Posted by 松ぽっくり at 16:34 │Comments(0) │フィールド
黄色く染めて
ミツバツチグリ

この所暖かい日が続いて土手の桜や草たちに勢いが付いてきた。
西向き斜面の下の方で『ミツバツチグリ』が一画を黄色く染めている。花は咲き始めて少し日が過ぎた感が有るので気付かずに通り過ぎていたらしい。
昨年は取り上げていないが一昨年とほぼ同時期に開花したものと思われる。
「陽を受けて三葉土栗つる延ばし」(一水)と云う句が有るが花の終わりごろ、ほふく枝を出して殖えていくのでしばしば群生する。
明日は久しぶりに一雨有りそうな予報が出ている。恵みの雨で春の草たちの勢いは一段と加速する事でしょう。


この所暖かい日が続いて土手の桜や草たちに勢いが付いてきた。
西向き斜面の下の方で『ミツバツチグリ』が一画を黄色く染めている。花は咲き始めて少し日が過ぎた感が有るので気付かずに通り過ぎていたらしい。
昨年は取り上げていないが一昨年とほぼ同時期に開花したものと思われる。
「陽を受けて三葉土栗つる延ばし」(一水)と云う句が有るが花の終わりごろ、ほふく枝を出して殖えていくのでしばしば群生する。
明日は久しぶりに一雨有りそうな予報が出ている。恵みの雨で春の草たちの勢いは一段と加速する事でしょう。
タグ :植物