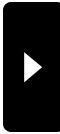可憐な
ハルリンドウ


今日は朝から先日抜歯した所の義歯の型どりです。粘土状のものをガバッと口いっぱいに入れられたが、少々柔らかかったと見えて喉の奥に流れ込みそうになって危なかった
その他所用が多く、フィールドはお休みしたので昨日の『ハルリンドウ』をアップします 。
。
日当たりの良い少し湿った所が好きなこの花は「フデリンドウ」の花とよく似ていますが、根元の葉(根生葉)が大きめではっきり見えます。
年々生育場所が狭められ、この可憐な花を見るのに苦労するようになった。
「タテヤマリンドウ」はこの花の高山型と云われています。
風が思いの他強いが、ついこの間までの様に苦にならない。


今日は朝から先日抜歯した所の義歯の型どりです。粘土状のものをガバッと口いっぱいに入れられたが、少々柔らかかったと見えて喉の奥に流れ込みそうになって危なかった

その他所用が多く、フィールドはお休みしたので昨日の『ハルリンドウ』をアップします
 。
。日当たりの良い少し湿った所が好きなこの花は「フデリンドウ」の花とよく似ていますが、根元の葉(根生葉)が大きめではっきり見えます。
年々生育場所が狭められ、この可憐な花を見るのに苦労するようになった。

「タテヤマリンドウ」はこの花の高山型と云われています。
風が思いの他強いが、ついこの間までの様に苦にならない。

タグ :植物
2010年04月30日 Posted by 松ぽっくり at 17:02 │Comments(2) │花見
半開した
キンラン

順調に雨雲は去り、昼には日差しが戻りました。予定通り島田に向けて出発です。
先日友人から「そろそろ開花している頃だよ」と聞かされて即、その気になりました。
山道で若干のロスは有りましたが、バイパスを使って1時間弱で着きました。
林の横の斜面に半開した黄色の花がそこここに見えます『キンラン』です。最近はあまり会っていなかったのでその個体数の多さに驚きました。
そしてスギナの陰から『ハルリンドウ』の鮮やかな青紫色が何本も何本も顔を出しています。こちらもかなりの個体数です。自然と顔がほころびます。
『金蘭」の名前は単純に花の色から付いたようです。
いつまでも絶えることなく咲き続けてくれる事を祈りながら帰路につきました。
花は全開しない


順調に雨雲は去り、昼には日差しが戻りました。予定通り島田に向けて出発です。
先日友人から「そろそろ開花している頃だよ」と聞かされて即、その気になりました。
山道で若干のロスは有りましたが、バイパスを使って1時間弱で着きました。
林の横の斜面に半開した黄色の花がそこここに見えます『キンラン』です。最近はあまり会っていなかったのでその個体数の多さに驚きました。

そしてスギナの陰から『ハルリンドウ』の鮮やかな青紫色が何本も何本も顔を出しています。こちらもかなりの個体数です。自然と顔がほころびます。

『金蘭」の名前は単純に花の色から付いたようです。
いつまでも絶えることなく咲き続けてくれる事を祈りながら帰路につきました。
花は全開しない

タグ :植物
2010年04月29日 Posted by 松ぽっくり at 17:32 │Comments(0) │花見
ブラシのような
風がガラリと変わりました。すれちがう人の挨拶も「暑くなったねー」
そう、後一週間もすれば「立夏」もう初夏なので有ります。
「セッカ」の声が青空から降ってきます「ヒッヒッヒッ・・・・」縄張り宣言に余念がない。
土手の下の梅の畑?の縁で『ウワミズザクラ』のブラシの様な花が咲いていました。恐らく地主の方が植えたものでしょうが珍しいので撮ってみました。
日本では北海道から九州まで分布して日当たりのよい谷間や沢の斜面などに自生していますが案外少ない。
小さな花の雄しべが付き出てビンを洗うブラシの様です
そう、後一週間もすれば「立夏」もう初夏なので有ります。
「セッカ」の声が青空から降ってきます「ヒッヒッヒッ・・・・」縄張り宣言に余念がない。
土手の下の梅の畑?の縁で『ウワミズザクラ』のブラシの様な花が咲いていました。恐らく地主の方が植えたものでしょうが珍しいので撮ってみました。
日本では北海道から九州まで分布して日当たりのよい谷間や沢の斜面などに自生していますが案外少ない。

小さな花の雄しべが付き出てビンを洗うブラシの様です
タグ :植物
2010年04月28日 Posted by 松ぽっくり at 17:36 │Comments(0) │フィールド
メリハリが
ミヤコグサ

予報通り朝から雨、いい加減安定してほしいものです。
そんな訳で昨日出会った『ミヤコグサ』をアップします。この草も花期の長い草で夏過ぎまで延々と咲きます。
京都に多かったとの事で「都草」になったようですが、花の形が烏帽子に似ているので「エボシグサ」とも言われます。
この仲間の花は雄しべも雌しべも隠れているので花にメリハリが無くて、撮った写真が間の抜けたものになる事が多い。

花粉は2枚の合わさった花弁の中に溜まっていて、虫がその上にとまると隙間から溢れ出て虫に付着します。その後で雌しべが延びて花弁の外に突き出し、体に花粉を付けた虫が来るのを待ちます。

予報通り朝から雨、いい加減安定してほしいものです。

そんな訳で昨日出会った『ミヤコグサ』をアップします。この草も花期の長い草で夏過ぎまで延々と咲きます。
京都に多かったとの事で「都草」になったようですが、花の形が烏帽子に似ているので「エボシグサ」とも言われます。
この仲間の花は雄しべも雌しべも隠れているので花にメリハリが無くて、撮った写真が間の抜けたものになる事が多い。


花粉は2枚の合わさった花弁の中に溜まっていて、虫がその上にとまると隙間から溢れ出て虫に付着します。その後で雌しべが延びて花弁の外に突き出し、体に花粉を付けた虫が来るのを待ちます。
タグ :植物
2010年04月27日 Posted by 松ぽっくり at 16:40 │Comments(0) │フィールド
ほぼ平開
マルバウツギ

花はほぼ平らに開くのでオレンジ色の花盤が良く見える

最近にしては珍しく2日続きで好天に恵まれ暖かい。
草木はたっぷりの陽をあびて勢いが付いて来ました。土手の斜面も「ニガナ」や「ミヤコグサ」など黄色が目立っています。
お地蔵さんの下の藪陰で『マルバウツギ』が木漏れ日のスポットライトを浴びて輝いていました。「ウツギ」の花は平開しませんが、こちらの花はほぼ平開します。
名前の「丸葉空木」は「ウツギ」に比べ葉が丸いからと言う単純明快な命名のようです。
ごく普通に見られる花ですが、整ったいい花です。
いつまでも冬と春がせめぎ合いをしていますが、気が付けばもう鯉のぼりの季節です。

花はほぼ平らに開くのでオレンジ色の花盤が良く見える

最近にしては珍しく2日続きで好天に恵まれ暖かい。
草木はたっぷりの陽をあびて勢いが付いて来ました。土手の斜面も「ニガナ」や「ミヤコグサ」など黄色が目立っています。
お地蔵さんの下の藪陰で『マルバウツギ』が木漏れ日のスポットライトを浴びて輝いていました。「ウツギ」の花は平開しませんが、こちらの花はほぼ平開します。
名前の「丸葉空木」は「ウツギ」に比べ葉が丸いからと言う単純明快な命名のようです。
ごく普通に見られる花ですが、整ったいい花です。
いつまでも冬と春がせめぎ合いをしていますが、気が付けばもう鯉のぼりの季節です。

タグ :植物
2010年04月26日 Posted by 松ぽっくり at 17:31 │Comments(0) │フィールド
似せる
アカハネムシの仲間

今日は朝から空港見物に行って来ました。
日曜日の事もあってかなりの見物客が来ています。
3機ほど離発着を見物し、土産品をながめた後、川根温泉をまわって帰ってきました。
団体行動ですので、余り草との出会いは有りませんでしたが、ブラッとした川べりでスイバの葉に止まった『アカハネムシ』の仲間に出会いました。
小さな虫達はそれぞれに身を守る術を持っているようですが、この仲間は毒のある「ベニホタル」に体を似せることにより、捕食者から逃れているようです。
この所の天候は日替わり状態ですが、久しぶりに気持ちよく晴れて汗ばむほどでした。
11時頃着陸したANA機


今日は朝から空港見物に行って来ました。
日曜日の事もあってかなりの見物客が来ています。
3機ほど離発着を見物し、土産品をながめた後、川根温泉をまわって帰ってきました。
団体行動ですので、余り草との出会いは有りませんでしたが、ブラッとした川べりでスイバの葉に止まった『アカハネムシ』の仲間に出会いました。
小さな虫達はそれぞれに身を守る術を持っているようですが、この仲間は毒のある「ベニホタル」に体を似せることにより、捕食者から逃れているようです。
この所の天候は日替わり状態ですが、久しぶりに気持ちよく晴れて汗ばむほどでした。
11時頃着陸したANA機

タグ :暮らし
2010年04月26日 Posted by 松ぽっくり at 00:02 │Comments(0) │日々の暮らし
水路の

ペラペラヨメナ

何だかはっきりしない空模様で昼過ぎには雷も鳴って又しても雨模様

3時過ぎ、空を見上げながらフィールドへ出かけてみました。
途中の水路のへりで『ペラペラヨメナ』が沢山花を付け始めました。
この軽い名前の花はどう言う訳か石垣の隙間とか川沿いの崖の様な所が好きなようです。
中央アメリカ原産と云う事で英名では「メキシカンデイジー」などと呼ばれています。
これから11月過ぎまで延々と花を付ける事でしょう。
雨上がりの山は何だか湯気が立っているように見えました。


タグ :植物
2010年04月24日 Posted by 松ぽっくり at 23:07 │Comments(0) │フィールド
花弁状の
イチリンソウ

昨日「アケボノスミレ」を見に行った途中で見かけた『イチリンソウ』を
取り上げて見ました。
茶畑の横の斜面に白い大きな花が点々と咲いていました。 白い花弁状のガク片は通常5~6枚ですが、時折多かったり少なかったりします(裏側はやや赤みを帯びるものも多い)
年々自生地は少なくなっているようです。
ガク片が8枚のもの

予報に違わず一日中しっかり降りました。目まぐるしく変わる空模様に結構振り回されています。

昨日「アケボノスミレ」を見に行った途中で見かけた『イチリンソウ』を
取り上げて見ました。
茶畑の横の斜面に白い大きな花が点々と咲いていました。 白い花弁状のガク片は通常5~6枚ですが、時折多かったり少なかったりします(裏側はやや赤みを帯びるものも多い)
年々自生地は少なくなっているようです。
ガク片が8枚のもの

予報に違わず一日中しっかり降りました。目まぐるしく変わる空模様に結構振り回されています。
タグ :植物
2010年04月22日 Posted by 松ぽっくり at 18:02 │Comments(0) │花見
華やかな
アケボノスミレ 上品な色合いに人気があります
上品な色合いに人気があります

友人から情報をいただき、水見色方面へ『アケボノスミレ』に会いに行って来ました。
山は濃淡取り混ぜた若葉で満ち、その中に「キヨスミミツバツツジ」のピンクがアクセントを付けています。
お目当ての「アケボノスミレ」は林道沿いにあるハイキングコース入口付近に点々と咲いていました。 その淡い紅紫色は数ある日本のスミレの中でも華やかな部類に入る事でしょう。
その淡い紅紫色は数ある日本のスミレの中でも華やかな部類に入る事でしょう。
後は光と私の運次第・・・と云う事でなんとか近い色は出ましたが実物の華やかさには・・・?
名前の「曙菫」はその色合いから曙の空を連想して付けられたようです。
昨日の雨から一転、ポカポカと快適な陽気でした。
 上品な色合いに人気があります
上品な色合いに人気があります
友人から情報をいただき、水見色方面へ『アケボノスミレ』に会いに行って来ました。
山は濃淡取り混ぜた若葉で満ち、その中に「キヨスミミツバツツジ」のピンクがアクセントを付けています。
お目当ての「アケボノスミレ」は林道沿いにあるハイキングコース入口付近に点々と咲いていました。
 その淡い紅紫色は数ある日本のスミレの中でも華やかな部類に入る事でしょう。
その淡い紅紫色は数ある日本のスミレの中でも華やかな部類に入る事でしょう。後は光と私の運次第・・・と云う事でなんとか近い色は出ましたが実物の華やかさには・・・?
名前の「曙菫」はその色合いから曙の空を連想して付けられたようです。
昨日の雨から一転、ポカポカと快適な陽気でした。
タグ :植物
2010年04月21日 Posted by 松ぽっくり at 20:58 │Comments(0) │花見
十字花
オランダガラシ(クレソン)

陽気は長続きしません、想定通り朝から雨でした。 まさしく「穀雨」となりうるか
古い差し歯が折れてしまい雨の中、歯科治療に行って来ました。
そんな訳で今日は小学校の裏の小川で真冬でも青々していた『オランダガラシ』が昨日沢山の花を付けていたのでアップします。
ヨーロッパ原産で明治の文明開化と共に入って来たようだが、今では尾瀬にまで入り込んでいる。しかし水の汚染がひどくなると消えてしまうようだ。
近づいてみると先に咲いたものはすでに棒状の果実になっている。花はアブラナ科の例にもれず4枚の十字花、(ワサビの花に似ています)


陽気は長続きしません、想定通り朝から雨でした。 まさしく「穀雨」となりうるか
古い差し歯が折れてしまい雨の中、歯科治療に行って来ました。

そんな訳で今日は小学校の裏の小川で真冬でも青々していた『オランダガラシ』が昨日沢山の花を付けていたのでアップします。
ヨーロッパ原産で明治の文明開化と共に入って来たようだが、今では尾瀬にまで入り込んでいる。しかし水の汚染がひどくなると消えてしまうようだ。

近づいてみると先に咲いたものはすでに棒状の果実になっている。花はアブラナ科の例にもれず4枚の十字花、(ワサビの花に似ています)

タグ :植物
2010年04月20日 Posted by 松ぽっくり at 17:30 │Comments(2) │近所
比べて
アカカタバミ、花の中心にも赤いリングが入ります。

カタバミ

大分暖かい、さすがの私も一枚脱ぎました。
土手下の茶畑は新芽が萌え、目にも優しい若葉色が広がっています。
「タンポポ」はもとより「シロツメクサ」や「カタバミ」も花の量産態勢にに入って来ました。
その「カタバミ」は変異が多くて、全体が赤紫色で葉が比較的小さいものは『アカカタバミ』と呼び、花弁とガクが10個有るものは「ホシザキカタバミ」、海岸に多く、毛深いものを「ケカタバミ」として区別されます。
今日は2つ並んでいたので比べて見ました。
ツバメが低く飛んでいます、下り坂なのでしょうか・・

カタバミ

大分暖かい、さすがの私も一枚脱ぎました。
土手下の茶畑は新芽が萌え、目にも優しい若葉色が広がっています。
「タンポポ」はもとより「シロツメクサ」や「カタバミ」も花の量産態勢にに入って来ました。
その「カタバミ」は変異が多くて、全体が赤紫色で葉が比較的小さいものは『アカカタバミ』と呼び、花弁とガクが10個有るものは「ホシザキカタバミ」、海岸に多く、毛深いものを「ケカタバミ」として区別されます。
今日は2つ並んでいたので比べて見ました。
ツバメが低く飛んでいます、下り坂なのでしょうか・・
タグ :植物
2010年04月19日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(2) │フィールド
パイオニア
文字どうり芽出しが赤い「アカメガシワ」

ようやく平年並みの陽気に近づいた日曜日、フィールドは思い思いに時を過ごす人々の数も多い。
花も実も地味な『アカメガシワ』はこの時季が一番人目を引く。
この木は伐採跡地や崩壊地などの明るい所にいち早く姿を見せるパイオニア植物の一つで河原にも多く、成長も早い。
漢字にすると「赤芽柏」となる。


ようやく平年並みの陽気に近づいた日曜日、フィールドは思い思いに時を過ごす人々の数も多い。
花も実も地味な『アカメガシワ』はこの時季が一番人目を引く。
この木は伐採跡地や崩壊地などの明るい所にいち早く姿を見せるパイオニア植物の一つで河原にも多く、成長も早い。
漢字にすると「赤芽柏」となる。

タグ :植物
2010年04月18日 Posted by 松ぽっくり at 16:00 │Comments(0) │フィールド
雑然とした
林道わきの雑然とした所に咲き始めたヤマルリソウ

今日は皆さんと浜石岳の中腹に行って来ました。
朝、雨が上がっていてくれることを念じていましたが、念力は通じず空を見上げてしまいました。
しかし予報どうり天気は急速に回復して時折日も差す程になり、一安心。
ただ707mの山頂は霧に覆われていて、中腹も肌寒くスミレた達は大多数が花をつぼめています。
それでも予定していたものは全て確認でき、その他の花は「ヤマルリソウ」と「センボンヤリ」が咲き始めました。一度霜にやられた「クロモジ」も新たな花を付けています。
午後3時、コジュケイの呼ぶ声を背に山を降りました。

今日は皆さんと浜石岳の中腹に行って来ました。
朝、雨が上がっていてくれることを念じていましたが、念力は通じず空を見上げてしまいました。

しかし予報どうり天気は急速に回復して時折日も差す程になり、一安心。

ただ707mの山頂は霧に覆われていて、中腹も肌寒くスミレた達は大多数が花をつぼめています。

それでも予定していたものは全て確認でき、その他の花は「ヤマルリソウ」と「センボンヤリ」が咲き始めました。一度霜にやられた「クロモジ」も新たな花を付けています。
午後3時、コジュケイの呼ぶ声を背に山を降りました。
タグ :植物
2010年04月17日 Posted by 松ぽっくり at 18:50 │Comments(0) │観察会
浜石、スミレ③
ヒゴスミレ

まー風の冷たい事!寒さに怖気づいてフィールドは止めました。
と云う事で、浜石のスミレその③にさせて頂きます。
とかく識別の難しいスミレの中にあって、『ヒゴスミレ』は比較的楽に見分ける事が出来ると思います。画像で分かる様に葉が非常に細かく切れ込んでいるので、葉さえ有れば「ヒゴスミレ」と分かります。
他に葉の切れ込むスミレは「エイザンスミレ」が有りますが、ここまで細かく有りません。
それと花の色が、エイザンは紅みを帯びますが、ヒゴスミレはどちらかと云うと花の中心が黄色みを帯びます。
昔から浜石はスミレで名が通っていますが、芝広場から野外センターまでの林道沿いに見ただけですが10種を確認出来ました

まー風の冷たい事!寒さに怖気づいてフィールドは止めました。

と云う事で、浜石のスミレその③にさせて頂きます。
とかく識別の難しいスミレの中にあって、『ヒゴスミレ』は比較的楽に見分ける事が出来ると思います。画像で分かる様に葉が非常に細かく切れ込んでいるので、葉さえ有れば「ヒゴスミレ」と分かります。

他に葉の切れ込むスミレは「エイザンスミレ」が有りますが、ここまで細かく有りません。
それと花の色が、エイザンは紅みを帯びますが、ヒゴスミレはどちらかと云うと花の中心が黄色みを帯びます。

昔から浜石はスミレで名が通っていますが、芝広場から野外センターまでの林道沿いに見ただけですが10種を確認出来ました

タグ :植物
2010年04月16日 Posted by 松ぽっくり at 16:46 │Comments(0) │下見
ハイセンスな
フモトスミレ、斑入りタイプ

4月も半ばと云うのにまたまた寒さがぶり返して、厚手の上着が中々しまえません。
本日はフィールドに行けませんでしたので、先日浜石で出会った『フモトスミレ』を取り上げます。小型ですが端正な顔立ちの私の好きなスミレです。
名前は「フモト」ですが、海岸近くの山地から2000㍍付近の高原まで広く見る事が出来ます。
スミレのプロに「地味ながらもハイセンスな逸品 」と言わしめたスミレです。
」と言わしめたスミレです。
ただ、生えている場所によっても個体差が有りますので容姿のすぐれた個体にいつも会えるとは限りません。
明日は更に寒くなるらしい

4月も半ばと云うのにまたまた寒さがぶり返して、厚手の上着が中々しまえません。

本日はフィールドに行けませんでしたので、先日浜石で出会った『フモトスミレ』を取り上げます。小型ですが端正な顔立ちの私の好きなスミレです。

名前は「フモト」ですが、海岸近くの山地から2000㍍付近の高原まで広く見る事が出来ます。
スミレのプロに「地味ながらもハイセンスな逸品
 」と言わしめたスミレです。
」と言わしめたスミレです。ただ、生えている場所によっても個体差が有りますので容姿のすぐれた個体にいつも会えるとは限りません。

明日は更に寒くなるらしい

タグ :植物
2010年04月15日 Posted by 松ぽっくり at 16:40 │Comments(0) │下見
趣が・・
マツバウンラン

マツバウンランの仮面状の花

「ヒドリガモ」も北に帰って、水門の池は大分静かになった。置いてきぼりの「カルガモ」が所在無さそうに佇んでいる。
河原にも斜面にも『マツバウンラン』が勢力を広げてきました。
細い茎を高く伸ばし、頼りなげに風に揺れる様は外来種とは思えぬ趣が有ります。
原産地は北アメリカ、名前は葉が細いので「松葉海蘭」となったようです。

所在無げなカルガモ

マツバウンランの仮面状の花

「ヒドリガモ」も北に帰って、水門の池は大分静かになった。置いてきぼりの「カルガモ」が所在無さそうに佇んでいる。
河原にも斜面にも『マツバウンラン』が勢力を広げてきました。
細い茎を高く伸ばし、頼りなげに風に揺れる様は外来種とは思えぬ趣が有ります。
原産地は北アメリカ、名前は葉が細いので「松葉海蘭」となったようです。

所在無げなカルガモ
タグ :自然
2010年04月14日 Posted by 松ぽっくり at 16:29 │Comments(0) │フィールド
全体に
思いの外、風も無く暖かで丁度いい。でもまた寒さが戻るらしいが・・
ミカン畑の下で『ウシハコベ』咲いていました。
普通のハコベに比べ全体に大きいので牛にたとえて「牛繁縷」となったようです。
ハコベとウシハコベの識別ポイントは雌しべの先(花柱)が3つ有るか5つ有るかで決まります。

葉も花も全体に大きいウシハコベ


左ウシハコベ、花柱は5個。 右ハコベ、花柱3個でガク片は花弁より長い。

ミカン畑の下で『ウシハコベ』咲いていました。
普通のハコベに比べ全体に大きいので牛にたとえて「牛繁縷」となったようです。

ハコベとウシハコベの識別ポイントは雌しべの先(花柱)が3つ有るか5つ有るかで決まります。


葉も花も全体に大きいウシハコベ


左ウシハコベ、花柱は5個。 右ハコベ、花柱3個でガク片は花弁より長い。
タグ :植物
2010年04月13日 Posted by 松ぽっくり at 17:22 │Comments(0) │フィールド
雁の足に
雨の一日でした。
そんな訳で一昨日の支流沿いにて出会った『イヌガンソク』を取り上げて見ました。
若葉はまだ丸まっていますが、前年の胞子葉が存在感を見せていました。
この胞子葉は生け花の花材やドライフラワーなどに使われますのでご存知の方も多いと思います。
名前の「犬雁足」はガンソク(クサソテツの別名)に似ていて食用にならないので付けられたようです。「クサソテツ」の若芽はコゴミと呼ばれ、山菜として珍重されます。
ただ、雁の足に似ているのはクサソテツよりこの胞子葉の方が似ていると思うのですが・・・
このシダは北海道から九州まで広く分布しているようです。
イヌガンソク

そんな訳で一昨日の支流沿いにて出会った『イヌガンソク』を取り上げて見ました。
若葉はまだ丸まっていますが、前年の胞子葉が存在感を見せていました。

この胞子葉は生け花の花材やドライフラワーなどに使われますのでご存知の方も多いと思います。

名前の「犬雁足」はガンソク(クサソテツの別名)に似ていて食用にならないので付けられたようです。「クサソテツ」の若芽はコゴミと呼ばれ、山菜として珍重されます。
ただ、雁の足に似ているのはクサソテツよりこの胞子葉の方が似ていると思うのですが・・・

このシダは北海道から九州まで広く分布しているようです。
イヌガンソク

タグ :植物
2010年04月12日 Posted by 松ぽっくり at 17:01 │Comments(0) │花見
生き残って
気温は20℃を超えて汗ばむほど、アゲハの仲間の姿が目に付くようになった。
フィールドでは外来種の「オランダミミナグサ」に席巻されたと思っていた在来種の『ミミナグサ』が生き残っていました。少し嬉しい!
両種ともよく似ていますが比べて見ると「ミミナグサ」の方が花の付く柄が長いのが分かります。花の姿も好感が持てます。
頑張って生き延びてくれる事を祈ろう。
名前の由来は小さな葉がネズミの耳に似ているので「耳菜草」となったようです。
桜は風に促されてハラハラと際限なく散っています。その下では何組ものヤングファミリーの平和な時間が流れているようだ。
ミミナグサ

ミミナグサ

オランダミミナグサ


フィールドでは外来種の「オランダミミナグサ」に席巻されたと思っていた在来種の『ミミナグサ』が生き残っていました。少し嬉しい!

両種ともよく似ていますが比べて見ると「ミミナグサ」の方が花の付く柄が長いのが分かります。花の姿も好感が持てます。

頑張って生き延びてくれる事を祈ろう。

名前の由来は小さな葉がネズミの耳に似ているので「耳菜草」となったようです。

桜は風に促されてハラハラと際限なく散っています。その下では何組ものヤングファミリーの平和な時間が流れているようだ。
ミミナグサ

ミミナグサ

オランダミミナグサ

タグ :植物
2010年04月11日 Posted by 松ぽっくり at 16:01 │Comments(0) │フィールド
「山笑う」の頃
ポカポカ陽気に誘われて午後、山手の小さな支流を歩いて来ました。
山は新芽時、まさに「山笑う」の様相を見せています。
林道沿いには「ミヤマキケマン」や「タチツボスミレ」が色を添え、カエデ科の「チドリノキ」も若葉と共に地味で小さな花をぶら下げています。
突き当たりの林の下、薄暗い所に『ツルシロカネソウ』がポツリポツリと咲いていました。
この花もキンポウゲ科の例にもれず、白い花弁に見えるのはガク片で花弁は黄色の小さな杯状になっています。
名前は花が白く、根茎が長くつる状に延びるので「蔓白銀草」となったようです。
それにしてもこの気温、歩いていると暑いくらいでした。
 ツルシロカネソウ
ツルシロカネソウ

山は新芽時、まさに「山笑う」の様相を見せています。
林道沿いには「ミヤマキケマン」や「タチツボスミレ」が色を添え、カエデ科の「チドリノキ」も若葉と共に地味で小さな花をぶら下げています。
突き当たりの林の下、薄暗い所に『ツルシロカネソウ』がポツリポツリと咲いていました。

この花もキンポウゲ科の例にもれず、白い花弁に見えるのはガク片で花弁は黄色の小さな杯状になっています。
名前は花が白く、根茎が長くつる状に延びるので「蔓白銀草」となったようです。
それにしてもこの気温、歩いていると暑いくらいでした。

 ツルシロカネソウ
ツルシロカネソウ タグ :植物