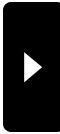珠芽を付ける
オニユリ

近所の土手で『オニユリ』が咲きだした。ススキやチガヤの中から抜きんでて、つぼみも色づき明日にでも咲きそうなものも10数本ある。ただ開花にいたる事は恐らく無いだろう。今は休みのようだが、除草作業がそこまで来ている。
日本の「オニユリ」は鱗茎(ユリ根)を食用にするため古い時代に渡来したと云われ、人里近くにしばしば野生化している。
ほとんどが結実せず、葉腋に出来る「珠芽」によって殖える。 日本で「珠芽」を付けるユリは「オニユリ」だけ。この個体は珠芽の成長が遅れているようです。
夏の雲が記憶の中から殊更暑い夏を抽出する。



近所の土手で『オニユリ』が咲きだした。ススキやチガヤの中から抜きんでて、つぼみも色づき明日にでも咲きそうなものも10数本ある。ただ開花にいたる事は恐らく無いだろう。今は休みのようだが、除草作業がそこまで来ている。
日本の「オニユリ」は鱗茎(ユリ根)を食用にするため古い時代に渡来したと云われ、人里近くにしばしば野生化している。
ほとんどが結実せず、葉腋に出来る「珠芽」によって殖える。 日本で「珠芽」を付けるユリは「オニユリ」だけ。この個体は珠芽の成長が遅れているようです。
夏の雲が記憶の中から殊更暑い夏を抽出する。

タグ :植物
2011年07月11日 Posted by 松ぽっくり at 17:18 │Comments(0) │近所
一級品
カワラナデシコ

『カワラナデシコ』が咲き始めました。と云ってもいつもの河原ではなく、近くの土手の斜面です。
フィールドの「カワラナデシコ」は今年はまだ確認出来ません。少々遅れているようです。
かの清少納言は「草の花はなでしこ」と一級品に格付けしています。昔から幾多の歌に詠まれ、愛されてきた「撫子」はこの「カワラナデシコ」の事で「愛しいわが子をなでいつくしむ」と云った意味から付けられた名前の様です。
「撫子やちひさき花のけだかさよ」 白之
中国原産の「石竹」の事を唐撫子と云うのに対し「大和撫子」とも言います。


『カワラナデシコ』が咲き始めました。と云ってもいつもの河原ではなく、近くの土手の斜面です。
フィールドの「カワラナデシコ」は今年はまだ確認出来ません。少々遅れているようです。
かの清少納言は「草の花はなでしこ」と一級品に格付けしています。昔から幾多の歌に詠まれ、愛されてきた「撫子」はこの「カワラナデシコ」の事で「愛しいわが子をなでいつくしむ」と云った意味から付けられた名前の様です。
「撫子やちひさき花のけだかさよ」 白之
中国原産の「石竹」の事を唐撫子と云うのに対し「大和撫子」とも言います。
タグ :植物
2011年07月09日 Posted by 松ぽっくり at 17:01 │Comments(3) │近所
へばり付いて
ペラペラヨメナ
水路の縁、コンクリの壁にへばり付いて『ペラペラヨメナ』が今年も見事に咲きました。
確かに水だけは充分に有るが、土のかけらも無いような所でよくもまあー、と感心する。
同時に「ペラペラヨメナ」などと付けた名前が気の毒に思えたりもします(写真は上から撮っています)
しかし、これはこの草の一面で有って、環境によっては茎がだらしなく伸びてかなりの「ペラペラ感」も見せます。
中央アメリカ原産で鑑賞用に導入されたようですが、しっかり逃げ出して関東以西の河川や道路の石垣の間などでしたたかに存在感を見せています。

水路の縁、コンクリの壁にへばり付いて『ペラペラヨメナ』が今年も見事に咲きました。
確かに水だけは充分に有るが、土のかけらも無いような所でよくもまあー、と感心する。
同時に「ペラペラヨメナ」などと付けた名前が気の毒に思えたりもします(写真は上から撮っています)
しかし、これはこの草の一面で有って、環境によっては茎がだらしなく伸びてかなりの「ペラペラ感」も見せます。
中央アメリカ原産で鑑賞用に導入されたようですが、しっかり逃げ出して関東以西の河川や道路の石垣の間などでしたたかに存在感を見せています。
タグ :植物
2011年05月05日 Posted by 松ぽっくり at 19:05 │Comments(0) │近所
栄枯盛衰
マサキ果実

今日は風が弱いせいか、いくらか凌ぎ易い。予想気温もこのところ静岡だけ10℃を超えている。
敷地の境界に植えられている『マサキ』がいい色に輝いていた。「マサキの実」は12月にも取り上げましたが、今日の方が格段きれいだったので再載する事にしました。
初夏に咲いた花が半年を経てようやく熟す訳ですが、裂開した果実から顔を出す種子は
朱赤色の仮種皮に包まれ、落ちずに留まるので見栄えがします。
成長が早く、増やし易いので以前は生垣などによく使われましたが最近は「カナメモチ」の
園芸種などに押されあまり使われなくなったようです。何の世界にも「栄枯盛衰」はあるようだ。


今日は風が弱いせいか、いくらか凌ぎ易い。予想気温もこのところ静岡だけ10℃を超えている。
敷地の境界に植えられている『マサキ』がいい色に輝いていた。「マサキの実」は12月にも取り上げましたが、今日の方が格段きれいだったので再載する事にしました。
初夏に咲いた花が半年を経てようやく熟す訳ですが、裂開した果実から顔を出す種子は
朱赤色の仮種皮に包まれ、落ちずに留まるので見栄えがします。
成長が早く、増やし易いので以前は生垣などによく使われましたが最近は「カナメモチ」の
園芸種などに押されあまり使われなくなったようです。何の世界にも「栄枯盛衰」はあるようだ。
タグ :植物
2011年01月19日 Posted by 松ぽっくり at 17:00 │Comments(2) │近所
イガイガ
フウ集合果
校庭の『フウ』の大木は燃えるような紅葉を脱ぎ捨てた後、枝いっぱいにイガイガの実を星の様にちりばめていました。
この実は小さな蒴果の集合体、かなり丈夫で少しくらい叩いても割れません。
原産地は台湾から中国にかけて、江戸の時代に渡来したと云われています。
「フウ」は漢字にすると「楓」となるがこの字は「カエデ」とも読むので紛らわしい。ただ
「カエデ科」の中には単に「カエデ」と云う種は無く、「○○カエデ」の様にたいがい頭に何か付く。 ちなみに「フウ」は「マンサク科」

校庭の『フウ』の大木は燃えるような紅葉を脱ぎ捨てた後、枝いっぱいにイガイガの実を星の様にちりばめていました。
この実は小さな蒴果の集合体、かなり丈夫で少しくらい叩いても割れません。
原産地は台湾から中国にかけて、江戸の時代に渡来したと云われています。
「フウ」は漢字にすると「楓」となるがこの字は「カエデ」とも読むので紛らわしい。ただ
「カエデ科」の中には単に「カエデ」と云う種は無く、「○○カエデ」の様にたいがい頭に何か付く。 ちなみに「フウ」は「マンサク科」
タグ :植物
2011年01月08日 Posted by 松ぽっくり at 16:48 │Comments(0) │近所
引き立てて
サネカズラ集合果
スッキリと雨も上がって暖かい朝でした。
ほとんど葉を落としたサクラの梢で「ツグミ」が2羽こちらを見ています。今シーズンの初顔合わせ、宜しくね!
今日は「勤労感謝の日」朝から河原は結構な人出です。
午後になると雲が広がり大分様相が変わって来ました。
川のそばの竹に絡んだ『サネカズラ』が葉の隙間からこちらを覗いています。緑の葉が赤い実を引きたてています。
昨年は10月の末に取り上げているので大分遅い気になりますが、果期に幅があるのでこれで普通なのかも知れない。
8月頃直径1,5㌢程で黄白色の上品な花を咲かせますが、意外と目立ちません。

スッキリと雨も上がって暖かい朝でした。
ほとんど葉を落としたサクラの梢で「ツグミ」が2羽こちらを見ています。今シーズンの初顔合わせ、宜しくね!
今日は「勤労感謝の日」朝から河原は結構な人出です。
午後になると雲が広がり大分様相が変わって来ました。
川のそばの竹に絡んだ『サネカズラ』が葉の隙間からこちらを覗いています。緑の葉が赤い実を引きたてています。
昨年は10月の末に取り上げているので大分遅い気になりますが、果期に幅があるのでこれで普通なのかも知れない。
8月頃直径1,5㌢程で黄白色の上品な花を咲かせますが、意外と目立ちません。
タグ :植物
2010年11月23日 Posted by 松ぽっくり at 16:57 │Comments(0) │近所
貴重な糧
トチノキ

校庭の隅、5月の初旬に沢山の花が集まって塔の様に咲いた『トチノキ』の実がかなり大きくなった。ただ、大きな木の梢なので気付く人は少ないかもしれない。
つやつやした大きな実はその昔「縄文人」の食生活を支え、その後も凶作、飢饉に備える保存食料として長く貢献してきた。強いアクを抜くために水にさらし、手間暇かけて
貴重な糧としたのでしょう。
相変わらず暑いのだが体が慣れたのだろうか、前ほど苦にならなくなった。

校庭の隅、5月の初旬に沢山の花が集まって塔の様に咲いた『トチノキ』の実がかなり大きくなった。ただ、大きな木の梢なので気付く人は少ないかもしれない。
つやつやした大きな実はその昔「縄文人」の食生活を支え、その後も凶作、飢饉に備える保存食料として長く貢献してきた。強いアクを抜くために水にさらし、手間暇かけて
貴重な糧としたのでしょう。
相変わらず暑いのだが体が慣れたのだろうか、前ほど苦にならなくなった。
タグ :植物
2010年08月05日 Posted by 松ぽっくり at 22:36 │Comments(1) │近所
張り付くように
クルマバザクロソウ
アリと比べると花の大きさがおおよそ見当が付きます。
道端の乾いた所に張り付くように『クルマバザクロソウ』が小さな花をいくつも付けています。白い花弁の様に見えるのはガク片で花弁は有りません。
熱帯アメリカの原産で明治の頃に新潟で見つかり、今では全国の道ばたなどで普通に見られるようです。
名前はザクロに似た葉が輪生する事から「車葉柘榴草」となったようですが・・・
明日からの予報は
 マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。
マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。

アリと比べると花の大きさがおおよそ見当が付きます。

道端の乾いた所に張り付くように『クルマバザクロソウ』が小さな花をいくつも付けています。白い花弁の様に見えるのはガク片で花弁は有りません。
熱帯アメリカの原産で明治の頃に新潟で見つかり、今では全国の道ばたなどで普通に見られるようです。
名前はザクロに似た葉が輪生する事から「車葉柘榴草」となったようですが・・・

明日からの予報は

 マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。
マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。
タグ :植物
2010年07月16日 Posted by 松ぽっくり at 22:25 │Comments(0) │近所
俗説
ノウゼンカズラ

ついこの間まで「ヒルガオ」が絡んでいた道端の藪、今日は一変して『ノウゼンカズラ』が占有し、沢山の蕾を付けて花も咲き始めていました。
花の色が派手すぎる為、昔の日本人にはあまり好まれなかったようで「花のにおいを嗅ぐと脳がおかしくなる」とか「花の露が目に入れば失明する」などの俗説も生まれました。
現代ではその花の色、大きさ、花の数などから夏の代表的な木の花とされています。

ついこの間まで「ヒルガオ」が絡んでいた道端の藪、今日は一変して『ノウゼンカズラ』が占有し、沢山の蕾を付けて花も咲き始めていました。
花の色が派手すぎる為、昔の日本人にはあまり好まれなかったようで「花のにおいを嗅ぐと脳がおかしくなる」とか「花の露が目に入れば失明する」などの俗説も生まれました。
現代ではその花の色、大きさ、花の数などから夏の代表的な木の花とされています。
タグ :植物
2010年06月27日 Posted by 松ぽっくり at 17:42 │Comments(0) │近所
吸水
アオスジアゲハ

近所の濡れたコンクリの上で『アオスジアゲハ』が吸水していました。 ちなみにこの吸水行動は本種に限らず何故か新鮮な♂ばかりだと云われています??
クスノキ科のクスノキやヤブニッケイ、タブノキなどが食樹で、市街地でもクスノキの周りを飛んでいるのを時々見かけます。飛翔は直線的でかなり敏速です。
アゲハチョウの中では少し小ぶりですが、色、姿、スピード、とも切れのいい蝶です。
目を凝らさないと確認出来ない程の雨が降ったりやんだり、それらしい空模様です。

近所の濡れたコンクリの上で『アオスジアゲハ』が吸水していました。 ちなみにこの吸水行動は本種に限らず何故か新鮮な♂ばかりだと云われています??
クスノキ科のクスノキやヤブニッケイ、タブノキなどが食樹で、市街地でもクスノキの周りを飛んでいるのを時々見かけます。飛翔は直線的でかなり敏速です。
アゲハチョウの中では少し小ぶりですが、色、姿、スピード、とも切れのいい蝶です。
目を凝らさないと確認出来ない程の雨が降ったりやんだり、それらしい空模様です。
タグ :自然
2010年06月26日 Posted by 松ぽっくり at 18:03 │Comments(0) │近所
道ばたの
ヒルガオ

道端の小藪に『ヒルガオ』がきれいに3つ並んで咲いていて足を止めさせられました。
「コヒルガオ」とよく似ていて、中間型もあるので紛らわしいのですが、包葉の先がとがらない、花柄の上部に縮れたヒレが無い点で『ヒルガオ』とさせてもらいました。
「ヒルガオ」は主に地下茎で増え、めったに結実しません。サツマイモもヒルガオ科で似た花が咲きます。
予想に反して雨は日中一杯もってくれました。

道端の小藪に『ヒルガオ』がきれいに3つ並んで咲いていて足を止めさせられました。
「コヒルガオ」とよく似ていて、中間型もあるので紛らわしいのですが、包葉の先がとがらない、花柄の上部に縮れたヒレが無い点で『ヒルガオ』とさせてもらいました。
「ヒルガオ」は主に地下茎で増え、めったに結実しません。サツマイモもヒルガオ科で似た花が咲きます。
予想に反して雨は日中一杯もってくれました。
タグ :植物
2010年06月13日 Posted by 松ぽっくり at 22:30 │Comments(0) │近所
方言名
ホタルブクロ
近所の土手『ホタルブクロ』と出会いました。イネ科の背の高い草の中、競うように背をのばし白い花をぶら下げていました。
昔からよく親しまれた草で全国に様々な方言名が有ります。「チョウチンバナ」「ツリガネソウ」「トックリバナ」「アメフリバナ」「ポンポンバナ」他
県内にも「キツネノチョーチン」「キツネノションベンオケ」などが有るようです。
梅雨入り前の貴重な晴れ間と ラジオでは有効活用をすすめている。
ラジオでは有効活用をすすめている。
フィールドは結構気温が上がり、長袖のシャツがジャマに感じます。

近所の土手『ホタルブクロ』と出会いました。イネ科の背の高い草の中、競うように背をのばし白い花をぶら下げていました。
昔からよく親しまれた草で全国に様々な方言名が有ります。「チョウチンバナ」「ツリガネソウ」「トックリバナ」「アメフリバナ」「ポンポンバナ」他
県内にも「キツネノチョーチン」「キツネノションベンオケ」などが有るようです。

梅雨入り前の貴重な晴れ間と
 ラジオでは有効活用をすすめている。
ラジオでは有効活用をすすめている。フィールドは結構気温が上がり、長袖のシャツがジャマに感じます。

タグ :植物
2010年06月10日 Posted by 松ぽっくり at 17:59 │Comments(2) │近所
葉の形状が
カワラマツバ

この葉の形状から名前が付きました
午前中はフィールドより少し下の河原で皆さんと運動をさせて頂きました。2時間程でしたが、たちまち日に焼けてしまいました。
帰り道、ススキやスイバの斜面に『カワラマツバ』が小さな花を付けていました。
葉が松葉の様に細く、河原や土手などに多いので「河原松葉」の名が付きました。
今日もまた雷が遠く聞こえて、雨もぱらつきました。

この葉の形状から名前が付きました

午前中はフィールドより少し下の河原で皆さんと運動をさせて頂きました。2時間程でしたが、たちまち日に焼けてしまいました。

帰り道、ススキやスイバの斜面に『カワラマツバ』が小さな花を付けていました。
葉が松葉の様に細く、河原や土手などに多いので「河原松葉」の名が付きました。
今日もまた雷が遠く聞こえて、雨もぱらつきました。
タグ :植物
2010年06月05日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(0) │近所
犬ツゲ
イヌツゲ雌木
雌花、雄しべは退化して小さい
畑の横で、先日の「クロガネモチ」に続いて同じ「モチノキ科」の『イヌツゲ』も咲き始めました。
名前に「ツゲ」と付いていますが、櫛の材料になる「ツゲ」とは全く違う仲間です。
大抵のモチノキ科は赤い実を付けますが、イヌツゲの仲間だけは黒い実を付けます。
この木の樹皮からも鳥もちが取れます。

雌花、雄しべは退化して小さい

畑の横で、先日の「クロガネモチ」に続いて同じ「モチノキ科」の『イヌツゲ』も咲き始めました。
名前に「ツゲ」と付いていますが、櫛の材料になる「ツゲ」とは全く違う仲間です。
大抵のモチノキ科は赤い実を付けますが、イヌツゲの仲間だけは黒い実を付けます。
この木の樹皮からも鳥もちが取れます。
タグ :植物
2010年05月31日 Posted by 松ぽっくり at 17:40 │Comments(0) │近所
方言名に
イボタノキ
今日も随分と暑い一日でした!そんな中、少しだけ運動をして、しっかり汗を出してきました。
帰り道、近所の道際で『イボタノキ』が白い小さな花を沢山付けて咲き誇っていました。
モクセイ科のこの木は山野の林縁などに普通に生える落葉の低木ですが暖かい静岡などでは冬でも葉が残っている事もあります。
この木の方言名に「トスベリ」あるいは「ロウノキ」などが有ります。これはこの木に付く「イボタロウムシ」が分泌するイボタロウを、家具の艶出しや戸の滑りを良くするために使われた事に寄るものと言われています。


今日も随分と暑い一日でした!そんな中、少しだけ運動をして、しっかり汗を出してきました。

帰り道、近所の道際で『イボタノキ』が白い小さな花を沢山付けて咲き誇っていました。

モクセイ科のこの木は山野の林縁などに普通に生える落葉の低木ですが暖かい静岡などでは冬でも葉が残っている事もあります。
この木の方言名に「トスベリ」あるいは「ロウノキ」などが有ります。これはこの木に付く「イボタロウムシ」が分泌するイボタロウを、家具の艶出しや戸の滑りを良くするために使われた事に寄るものと言われています。


タグ :植物
2010年05月22日 Posted by 松ぽっくり at 22:34 │Comments(0) │近所
蜜源植物の
山際のハリエンジュ

近所の山際に白くなっている所が有った、あれは・・・近づいてみるとやはり『ハリエンジュ』が沢山花の穂をぶら下げていました。
残念ながら少し高い所で近づけない。近づけないとなると近寄りたい。
と云う事で近づける所に行く事にした、確か千代に有ったはずです。・・・有りました。こちらもうまい具合に花盛りでした。
マメ科のこの木は別名を「ニセアカシア」と云う。 考えて見ると両方ともひとさまの名前を借りている事になる。
「エンジュ」に「針」を付けて『ハリエンジュ』、「アカシア」に「偽」を付けて『ニセアカシア』少々独自性に欠ける命名が気にかかる。
北アメリカ原産で砂防用としてよく使われるが、重要な蜜源植物のひとつでもあります。

千代のハリエンジュ

近所の山際に白くなっている所が有った、あれは・・・近づいてみるとやはり『ハリエンジュ』が沢山花の穂をぶら下げていました。

残念ながら少し高い所で近づけない。近づけないとなると近寄りたい。

と云う事で近づける所に行く事にした、確か千代に有ったはずです。・・・有りました。こちらもうまい具合に花盛りでした。

マメ科のこの木は別名を「ニセアカシア」と云う。 考えて見ると両方ともひとさまの名前を借りている事になる。
「エンジュ」に「針」を付けて『ハリエンジュ』、「アカシア」に「偽」を付けて『ニセアカシア』少々独自性に欠ける命名が気にかかる。

北アメリカ原産で砂防用としてよく使われるが、重要な蜜源植物のひとつでもあります。

千代のハリエンジュ

タグ :植物
2010年05月11日 Posted by 松ぽっくり at 16:54 │Comments(2) │近所
もうこんなに
ナツグミの若い実

 水路のそばの『ナツグミ』の実がもうこんなに大きくなってきました。3月の末に咲き始めてつい最近まで花が有ったと思いましたが・・・・・6月に入れば赤く熟す事でしょう。
水路のそばの『ナツグミ』の実がもうこんなに大きくなってきました。3月の末に咲き始めてつい最近まで花が有ったと思いましたが・・・・・6月に入れば赤く熟す事でしょう。
同じ頃花を付けた「アキグミ」とは大違いです。
その「ナツグミ」にテントウムシの幼虫が沢山いました。餌になるアブラムシが付いたのかと思い、あちこち探して見ましたが見つかりません。はたしてこの肉食の幼虫達は何を餌にするのでしょう?
雨がぱらついて来ました。これから明日までしばらくグズつくようです。
テントウムシの幼虫


 水路のそばの『ナツグミ』の実がもうこんなに大きくなってきました。3月の末に咲き始めてつい最近まで花が有ったと思いましたが・・・・・6月に入れば赤く熟す事でしょう。
水路のそばの『ナツグミ』の実がもうこんなに大きくなってきました。3月の末に咲き始めてつい最近まで花が有ったと思いましたが・・・・・6月に入れば赤く熟す事でしょう。
同じ頃花を付けた「アキグミ」とは大違いです。
その「ナツグミ」にテントウムシの幼虫が沢山いました。餌になるアブラムシが付いたのかと思い、あちこち探して見ましたが見つかりません。はたしてこの肉食の幼虫達は何を餌にするのでしょう?
雨がぱらついて来ました。これから明日までしばらくグズつくようです。

テントウムシの幼虫

タグ :自然
2010年05月10日 Posted by 松ぽっくり at 16:10 │Comments(0) │近所
校庭の
トチノキ

柿の若葉が目にしみます。
この所平年並みの気温が続いて随分と過ごし易く、草木は一段と厚みを増して来ました。
小学校の校庭の大きな『トチノキ』が今年も沢山の花を付けました。
去年の秋は栗の親分の様な大きな実がいくつも道に落ちていて、何をする訳でもないのに拾って来たのを思い出します。
よく似ている「マロニエ」は実に刺が有り、ヨーロッパでよく街路樹として使われます。花の咲く頃は「マロニエの日曜日」と呼んで親しんでいるようです。

柿の若葉が目にしみます。

この所平年並みの気温が続いて随分と過ごし易く、草木は一段と厚みを増して来ました。
小学校の校庭の大きな『トチノキ』が今年も沢山の花を付けました。
去年の秋は栗の親分の様な大きな実がいくつも道に落ちていて、何をする訳でもないのに拾って来たのを思い出します。

よく似ている「マロニエ」は実に刺が有り、ヨーロッパでよく街路樹として使われます。花の咲く頃は「マロニエの日曜日」と呼んで親しんでいるようです。

タグ :植物
2010年05月09日 Posted by 松ぽっくり at 17:15 │Comments(0) │近所
十字花
オランダガラシ(クレソン)

陽気は長続きしません、想定通り朝から雨でした。 まさしく「穀雨」となりうるか
古い差し歯が折れてしまい雨の中、歯科治療に行って来ました。
そんな訳で今日は小学校の裏の小川で真冬でも青々していた『オランダガラシ』が昨日沢山の花を付けていたのでアップします。
ヨーロッパ原産で明治の文明開化と共に入って来たようだが、今では尾瀬にまで入り込んでいる。しかし水の汚染がひどくなると消えてしまうようだ。
近づいてみると先に咲いたものはすでに棒状の果実になっている。花はアブラナ科の例にもれず4枚の十字花、(ワサビの花に似ています)


陽気は長続きしません、想定通り朝から雨でした。 まさしく「穀雨」となりうるか
古い差し歯が折れてしまい雨の中、歯科治療に行って来ました。

そんな訳で今日は小学校の裏の小川で真冬でも青々していた『オランダガラシ』が昨日沢山の花を付けていたのでアップします。
ヨーロッパ原産で明治の文明開化と共に入って来たようだが、今では尾瀬にまで入り込んでいる。しかし水の汚染がひどくなると消えてしまうようだ。

近づいてみると先に咲いたものはすでに棒状の果実になっている。花はアブラナ科の例にもれず4枚の十字花、(ワサビの花に似ています)

タグ :植物
2010年04月20日 Posted by 松ぽっくり at 17:30 │Comments(2) │近所
銀色を帯びて
新年度も朝から雨、したがってフィールドはお休みです。
そこで3/30に水路の脇で出会った『ナツグミ』の花を取り上げます。
この木は昨年、実が付いたときにアップしたものです。
グミの仲間の特徴ですが、全体に「鱗状毛」や「星状毛」と呼ばれる変わった毛?が有ります。そのため葉が銀色を帯びて見えます(ナツグミの場合は葉裏が)
夏に実がなるから「ナツグミ」と云う事になっていますが、5月の末にはもう色付き始めます。細かい事を言わせてもらえば「初夏グミ」と云う所でしょうか。
河原の「アキグミ」はまだ蕾です。こちらは若葉と蕾で木全体が白っぽく見えています。
どうやら明日も一日雨のようです
ナツグミ


そこで3/30に水路の脇で出会った『ナツグミ』の花を取り上げます。
この木は昨年、実が付いたときにアップしたものです。
グミの仲間の特徴ですが、全体に「鱗状毛」や「星状毛」と呼ばれる変わった毛?が有ります。そのため葉が銀色を帯びて見えます(ナツグミの場合は葉裏が)
夏に実がなるから「ナツグミ」と云う事になっていますが、5月の末にはもう色付き始めます。細かい事を言わせてもらえば「初夏グミ」と云う所でしょうか。

河原の「アキグミ」はまだ蕾です。こちらは若葉と蕾で木全体が白っぽく見えています。
どうやら明日も一日雨のようです

ナツグミ


タグ :植物