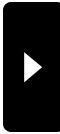フィールド暮色
サンセット

いよいよ2010年もカウントダウンに入った。
この一年間も植物の花や果実、野鳥、昆虫、などと様々な出会いを重ねてきましたがその都度引きつけられ、呼び寄せられ、新たな興味を抱かせてくれる自然の営みに感謝!
季節がめぐって繰り返される色あせる事のない再会、驚きと興奮の初見、新たな年の新たな出会いを期待せずにはいられない。

いよいよ2010年もカウントダウンに入った。
この一年間も植物の花や果実、野鳥、昆虫、などと様々な出会いを重ねてきましたがその都度引きつけられ、呼び寄せられ、新たな興味を抱かせてくれる自然の営みに感謝!
季節がめぐって繰り返される色あせる事のない再会、驚きと興奮の初見、新たな年の新たな出会いを期待せずにはいられない。
タグ :暮らし
2010年12月31日 Posted by 松ぽっくり at 22:51 │Comments(1) │フィールド
深い溝が
ガガイモ袋果

西日本や北日本では雪らしいが、押し詰まったフィールドは空気こそ冷たいが意外に穏やか、午後には一時日が差す時も。
10月の後半に取り上げた「ガガイモの袋果」が此処に来てようやく割れて種に付いた毛が確認出来るようになった。
しかし、この袋果と私の間には深い溝が・・・・・。

何とか近づきたいと悪あがきをしたが私が手にしたものはご覧の様な画像と無数にくっついたコセンダンの種で有りました。 とほほ・・・
とほほ・・・
コンデジのせいにする訳ではないが、もっとよい武器がほしくなった。
種に付いた毛も「タンポポ」などの場合は「冠毛」と呼びますが、「ガガイモ」などは
「種髪」と云うようです。


西日本や北日本では雪らしいが、押し詰まったフィールドは空気こそ冷たいが意外に穏やか、午後には一時日が差す時も。
10月の後半に取り上げた「ガガイモの袋果」が此処に来てようやく割れて種に付いた毛が確認出来るようになった。
しかし、この袋果と私の間には深い溝が・・・・・。


何とか近づきたいと悪あがきをしたが私が手にしたものはご覧の様な画像と無数にくっついたコセンダンの種で有りました。
 とほほ・・・
とほほ・・・コンデジのせいにする訳ではないが、もっとよい武器がほしくなった。
種に付いた毛も「タンポポ」などの場合は「冠毛」と呼びますが、「ガガイモ」などは
「種髪」と云うようです。
タグ :植物
2010年12月30日 Posted by 松ぽっくり at 16:48 │Comments(0) │フィールド
ほんのひと時
チョウゲンボウ
フィールドは思いのほか風も無く、着膨れした背中がポカポカです。
超スローにペダルを踏んでいると10㍍程先の斜面から鳥が飛び立った、ムクドリだろうと思ったら大きさが・・・・「チョウゲンボウ」のようだ。
うまい具合に茶畑用防霜ファンのテッペンに止まってくれた。あまり目を合わさないようにコンデジを用意した時サッと舞い降りて何かをつかんで今度は大分先の電柱に止まった。
恐らくカマキリかバッタでも捕まえたのでしょう。視線を合わさないように再度接近を試みる。
半分程距離を詰めた所で安全パイ用に2回シャッターを切り、更に接近を続行中、何と
カラスがちょっかいを出しに来て、全ては水の泡。 執拗なカラスの攻撃に川向うの上空へ消えてしまった。
それでも安全パイ用の一枚で眼の下の黒い特徴が何とか確認出来る。
『チョウゲンボウ』とのほんのひと時の出会いでありました。

フィールドは思いのほか風も無く、着膨れした背中がポカポカです。
超スローにペダルを踏んでいると10㍍程先の斜面から鳥が飛び立った、ムクドリだろうと思ったら大きさが・・・・「チョウゲンボウ」のようだ。
うまい具合に茶畑用防霜ファンのテッペンに止まってくれた。あまり目を合わさないようにコンデジを用意した時サッと舞い降りて何かをつかんで今度は大分先の電柱に止まった。
恐らくカマキリかバッタでも捕まえたのでしょう。視線を合わさないように再度接近を試みる。
半分程距離を詰めた所で安全パイ用に2回シャッターを切り、更に接近を続行中、何と
カラスがちょっかいを出しに来て、全ては水の泡。 執拗なカラスの攻撃に川向うの上空へ消えてしまった。
それでも安全パイ用の一枚で眼の下の黒い特徴が何とか確認出来る。
『チョウゲンボウ』とのほんのひと時の出会いでありました。
タグ :野鳥
2010年12月28日 Posted by 松ぽっくり at 17:04 │Comments(2) │フィールド
怠りない
キブシ蕾

寒風吹きすさぶ河原、ヤナギの横の『キブシ』は蕾をぶら下げ来春の準備に怠りない。
どういう流れでこの地に根を張ったか定かではないが、山に根を下ろした仲間に比べればひときわ厳しい環境で有る事は間違いない。
葉は言うに及ばず、その蕾さえ「あずき色」に染めて厳しい季節をやり過ごそうとしている。
名前は花が垂れ下がるので「黄藤」がなまって「キブシ」になったと云う説もある。
それにしても寒い日が続く!


寒風吹きすさぶ河原、ヤナギの横の『キブシ』は蕾をぶら下げ来春の準備に怠りない。
どういう流れでこの地に根を張ったか定かではないが、山に根を下ろした仲間に比べればひときわ厳しい環境で有る事は間違いない。
葉は言うに及ばず、その蕾さえ「あずき色」に染めて厳しい季節をやり過ごそうとしている。
名前は花が垂れ下がるので「黄藤」がなまって「キブシ」になったと云う説もある。
それにしても寒い日が続く!
タグ :植物
2010年12月26日 Posted by 松ぽっくり at 14:53 │Comments(0) │フィールド
逞しさ
ナズナ
寒さに臆病になって、ひと時ためらって窓の外を見ていたが意を決して出発!
なるべく風当たりの少ないコースを取ったつもりでも強風の中ではどこも大差はない
吹きさらしの空地で『ナズナ』が沢山集まって寒さなど素知らぬ顔で空を仰いでいる。その逞しさにあやかろうとカメラを出して風の収まるのを待っている内にあやかりきれずにUターンとなった。
そんな訳で本日の1枚は「ペンペングサ」。この草は「ナズナ」と云うよりやはり「ペンペングサ」の方がぴったりで、三味線のバチの様なハート型の実が温かみの有る味を見せています。
江戸の時代には天秤棒を担いで「ナズナ売り」が町内を売り歩いたとも言われています。
食材として、民間薬として、子供の遊び道具として、昔から人々と色々なかかわりを持ってきた野草では有ります。

寒さに臆病になって、ひと時ためらって窓の外を見ていたが意を決して出発!
なるべく風当たりの少ないコースを取ったつもりでも強風の中ではどこも大差はない

吹きさらしの空地で『ナズナ』が沢山集まって寒さなど素知らぬ顔で空を仰いでいる。その逞しさにあやかろうとカメラを出して風の収まるのを待っている内にあやかりきれずにUターンとなった。

そんな訳で本日の1枚は「ペンペングサ」。この草は「ナズナ」と云うよりやはり「ペンペングサ」の方がぴったりで、三味線のバチの様なハート型の実が温かみの有る味を見せています。
江戸の時代には天秤棒を担いで「ナズナ売り」が町内を売り歩いたとも言われています。
食材として、民間薬として、子供の遊び道具として、昔から人々と色々なかかわりを持ってきた野草では有ります。
タグ :植物
2010年12月25日 Posted by 松ぽっくり at 15:54 │Comments(0) │フィールド
西日の中
ホソバヒメミソハギ果期
西日の中、殺風景な田んぼの端で『ホソバヒメミソハギ』があずき色に染まって存在感を見せています。そこまで主張されればレンズを向けない訳にはいかない。
あの小さな4ミリ程の花は結実し、ガクに包まれたまま丸い蒴果になっていた。中には1ミリにも満たない小さな種が多数入っている。
はるばる北アメリカから渡来して異郷の地にしっかり順応しているタフなやつだ!
師走の土手下は、つるべ落としの陽が山の端に近づくと、たちまち冷気がよみがえる。

西日の中、殺風景な田んぼの端で『ホソバヒメミソハギ』があずき色に染まって存在感を見せています。そこまで主張されればレンズを向けない訳にはいかない。
あの小さな4ミリ程の花は結実し、ガクに包まれたまま丸い蒴果になっていた。中には1ミリにも満たない小さな種が多数入っている。
はるばる北アメリカから渡来して異郷の地にしっかり順応しているタフなやつだ!

師走の土手下は、つるべ落としの陽が山の端に近づくと、たちまち冷気がよみがえる。
タグ :植物
2010年12月23日 Posted by 松ぽっくり at 17:35 │Comments(0) │田んぼ
コートなし
アカメガシワ冬芽

雨は朝にはスッキリと上がっていた。
残り少なくなった「アカメガシワ」の黄葉の間から冬芽が目に付くようになった。
「アカメガシワ」の冬芽は裸芽、コートを着ていないので小さいながらも既に葉の形が確認出来る。ただ、裸芽と云っても全くの裸と云う訳ではない、さすがの「アカメガシワ」も丸裸では厳しい冬を乗り切る事は出来ないので「星状毛」と云う少し生え方変わった毛を隙間なく密生して冬に対処している。
「ロウバイ」の香がかすかに流れ、暖かな冬至です。


雨は朝にはスッキリと上がっていた。
残り少なくなった「アカメガシワ」の黄葉の間から冬芽が目に付くようになった。
「アカメガシワ」の冬芽は裸芽、コートを着ていないので小さいながらも既に葉の形が確認出来る。ただ、裸芽と云っても全くの裸と云う訳ではない、さすがの「アカメガシワ」も丸裸では厳しい冬を乗り切る事は出来ないので「星状毛」と云う少し生え方変わった毛を隙間なく密生して冬に対処している。
「ロウバイ」の香がかすかに流れ、暖かな冬至です。
タグ :植物
2010年12月22日 Posted by 松ぽっくり at 17:03 │Comments(2) │フィールド
吹きさらしの
ホトケノザ

吹きさらしの空き地で『ホトケノザ』が葉を赤くして頑張っていました。
暖かい静岡では冬でも結構春の花が咲きます。その中でも「ホトケノザ」は空地や畑の周辺では青々と群落を作り、一大勢力を誇っています。ただ今回の様に葉を赤くして咲いている所はあまり見かけた記憶がありません。
「ホトケノザ」の葉は段々に階を重ねるように付くので「三階草」の別名があります。
天気予報の通り、午前中の日和から雲は急速に厚みを増して雨になりました。


吹きさらしの空き地で『ホトケノザ』が葉を赤くして頑張っていました。
暖かい静岡では冬でも結構春の花が咲きます。その中でも「ホトケノザ」は空地や畑の周辺では青々と群落を作り、一大勢力を誇っています。ただ今回の様に葉を赤くして咲いている所はあまり見かけた記憶がありません。
「ホトケノザ」の葉は段々に階を重ねるように付くので「三階草」の別名があります。
天気予報の通り、午前中の日和から雲は急速に厚みを増して雨になりました。
タグ :植物
2010年12月21日 Posted by 松ぽっくり at 17:34 │Comments(0) │フィールド
果皮が割れて
ツルウメモドキ

風の質が異なって暖かい一日だった。
季節がら赤い実や種が続く事になるが、防災用のブロックの上を這っている『ツルウメモドキ』の果皮が割れて赤いきれいな種が顔を見せていた。
今年はいつもの年より果皮が割れるのが遅い様だ。赤い種が顔を出すこの季節はよく目立つが、葉が茂る花の頃は他の植物にまぎれて目立たない。
ツルは数メートルに達します。
赤い種が「ウメモドキ」の赤い実に似て、ツル性なので「蔓梅擬」の名が付いたようです。


風の質が異なって暖かい一日だった。
季節がら赤い実や種が続く事になるが、防災用のブロックの上を這っている『ツルウメモドキ』の果皮が割れて赤いきれいな種が顔を見せていた。
今年はいつもの年より果皮が割れるのが遅い様だ。赤い種が顔を出すこの季節はよく目立つが、葉が茂る花の頃は他の植物にまぎれて目立たない。
ツルは数メートルに達します。
赤い種が「ウメモドキ」の赤い実に似て、ツル性なので「蔓梅擬」の名が付いたようです。
タグ :植物
2010年12月20日 Posted by 松ぽっくり at 18:10 │Comments(0) │フィールド
冬至10日前
ノイバラ偽果
土手横の藪では今年も『ノイバラ』がいい色になって人目を引きます、前年に比べると少し数が少ないようだが。
完熟したものは霜にあたると軟らかくなって甘味を増すと云う。
霜のおりた草の姿は趣があって冬の被写体としてはずせないが、それ以外の楽しみがまた一つ増えた事になる。
いよいよ押し詰まって来た、後3日もすれば「冬至」、「冬至10日前」と云う事で今頃が一番日が短く感じる頃だ。
穏やかな日曜日、上空を飛行船がゆっくり横切っていきました(AM9:40頃)


土手横の藪では今年も『ノイバラ』がいい色になって人目を引きます、前年に比べると少し数が少ないようだが。
完熟したものは霜にあたると軟らかくなって甘味を増すと云う。

霜のおりた草の姿は趣があって冬の被写体としてはずせないが、それ以外の楽しみがまた一つ増えた事になる。
いよいよ押し詰まって来た、後3日もすれば「冬至」、「冬至10日前」と云う事で今頃が一番日が短く感じる頃だ。
穏やかな日曜日、上空を飛行船がゆっくり横切っていきました(AM9:40頃)

タグ :植物
2010年12月19日 Posted by 松ぽっくり at 15:58 │Comments(0) │フィールド
豊作
ヤブコウジ
今日は皆さんと「遊木の森」を歩いて来ました。
珍しく小さなお子さんを連れてきた方が有り、賑やかさを得た会になりました。
この季節、花は望むべきも有りませんが、季節の置き土産などそれなりに楽しみは尽きません。
今年は『ヤブコウジ』が大豊作で小さな赤い実が林床を一面に彩っています。
この赤い実が可愛いのでお正月の寄せ植えなどに使われ、千両や万両に対し十両の名で呼ばれたりします。
漢字にすると「藪柑子」となり赤い実はかすかに甘い。と云う事で口に入れてみました。
その感想は「甘いと云われれば甘いかな~」と云った所でした。
あまり風も無くて歩くには良い日和でした。

今日は皆さんと「遊木の森」を歩いて来ました。
珍しく小さなお子さんを連れてきた方が有り、賑やかさを得た会になりました。
この季節、花は望むべきも有りませんが、季節の置き土産などそれなりに楽しみは尽きません。
今年は『ヤブコウジ』が大豊作で小さな赤い実が林床を一面に彩っています。
この赤い実が可愛いのでお正月の寄せ植えなどに使われ、千両や万両に対し十両の名で呼ばれたりします。
漢字にすると「藪柑子」となり赤い実はかすかに甘い。と云う事で口に入れてみました。
その感想は「甘いと云われれば甘いかな~」と云った所でした。

あまり風も無くて歩くには良い日和でした。
タグ :植物
2010年12月18日 Posted by 松ぽっくり at 19:48 │Comments(0) │観察会
棒の様な
テイカカズラ袋果

二股に分かれた棒の様な『テイカカズラ』の袋果が裂け始めて、冠毛の付いた種が見えてきました。
このツルも花からは想像もつかない様な実を結び、おまけに種には冠毛まで付いていて風に乗って飛んでいきます。
常緑のつる性木本ですが古くなった葉は赤くなります。また、樹木に絡みついて高い所にある葉と、地表を這っている時の葉ではかなりの違いがあり別種の様にみえます。
晴れてよい天気だが寒さはきつく身にしみます。


二股に分かれた棒の様な『テイカカズラ』の袋果が裂け始めて、冠毛の付いた種が見えてきました。
このツルも花からは想像もつかない様な実を結び、おまけに種には冠毛まで付いていて風に乗って飛んでいきます。
常緑のつる性木本ですが古くなった葉は赤くなります。また、樹木に絡みついて高い所にある葉と、地表を這っている時の葉ではかなりの違いがあり別種の様にみえます。
晴れてよい天気だが寒さはきつく身にしみます。
タグ :植物
2010年12月17日 Posted by 松ぽっくり at 17:06 │Comments(0) │フィールド
逃げ出して
ツルムラサキ

風がそれ程有る訳ではないが日差しが無くかなり寒い。こうなると楽しいはずの散歩?も知らず知らず家路を急ぐようになる。
水辺では「カルガモ」が首をすくめていた(彼らは私達が思うほど寒さは感じていないと云うが)
畑の横の空地に『ツルムラサキ』がいい色をして這っていた。どかで植えられていたものが逃げ出したのでしょう。ピンク色のものはガク片で花弁は有りません。
熱帯アジア原産で江戸時代と明治時代の2度に分かれて入って来たと云われています。
江戸時代に入ったものは茎が緑色、明治時代に入ったものは紫色をした品種です。
名前は果汁を紫色の染料に使い、ツル植物で有る事から付いたようです。
茎や葉はかなり栄養価が高いと云われています。
カルガモ



風がそれ程有る訳ではないが日差しが無くかなり寒い。こうなると楽しいはずの散歩?も知らず知らず家路を急ぐようになる。
水辺では「カルガモ」が首をすくめていた(彼らは私達が思うほど寒さは感じていないと云うが)
畑の横の空地に『ツルムラサキ』がいい色をして這っていた。どかで植えられていたものが逃げ出したのでしょう。ピンク色のものはガク片で花弁は有りません。
熱帯アジア原産で江戸時代と明治時代の2度に分かれて入って来たと云われています。
江戸時代に入ったものは茎が緑色、明治時代に入ったものは紫色をした品種です。
名前は果汁を紫色の染料に使い、ツル植物で有る事から付いたようです。
茎や葉はかなり栄養価が高いと云われています。
カルガモ

タグ :植物
2010年12月16日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(0) │フィールド
白く粉をふいた
トウネズミモチ果実
強風!河原は強い西風が吹き荒れています。昨日とは打って変って寒い。
河原の『トウネズミモチ』は今年も溢れんばかりに実を付けていました。
その白く粉をふいた様な黒い実は在来の「ネズミモチ」より少し太く丸く感じる。
ただ全体よく似ているのですが、確実な識別法としては葉を日にかざして見た時、脈が透けて見える方が「トウネズミモチ」です。
この実も冬の後半になれば全て野鳥たちのおなかに収まる事になるでしょう。

強風!河原は強い西風が吹き荒れています。昨日とは打って変って寒い。
河原の『トウネズミモチ』は今年も溢れんばかりに実を付けていました。
その白く粉をふいた様な黒い実は在来の「ネズミモチ」より少し太く丸く感じる。
ただ全体よく似ているのですが、確実な識別法としては葉を日にかざして見た時、脈が透けて見える方が「トウネズミモチ」です。
この実も冬の後半になれば全て野鳥たちのおなかに収まる事になるでしょう。
タグ :植物
2010年12月15日 Posted by 松ぽっくり at 17:03 │Comments(0) │フィールド
暖色の中
ツルボ種子

思いの外回復は遅く、昼過ぎ頃やっと日差しが出て、随分と暖かい。
西向きの斜面はでは傾き始めた日を受けて「チガヤ」の葉が暖かい色に染まっています。
そんな暖色の中『ツルボ』が一面に林立しています。色は抜けて白くなっていますが、黒い小さな種をそれぞれが抱えています。この一面だけでも膨大な数の種がこの次の風で散布される事でしょう。
ちなみに新分類法では「ツルボ属」は新しく出来た「キジカクシ科」に入るらしい(これがまた悩みの種です)


思いの外回復は遅く、昼過ぎ頃やっと日差しが出て、随分と暖かい。
西向きの斜面はでは傾き始めた日を受けて「チガヤ」の葉が暖かい色に染まっています。
そんな暖色の中『ツルボ』が一面に林立しています。色は抜けて白くなっていますが、黒い小さな種をそれぞれが抱えています。この一面だけでも膨大な数の種がこの次の風で散布される事でしょう。
ちなみに新分類法では「ツルボ属」は新しく出来た「キジカクシ科」に入るらしい(これがまた悩みの種です)

タグ :植物
2010年12月14日 Posted by 松ぽっくり at 17:56 │Comments(0) │フィールド
気まま
ガマズミ
先日「カワラナデシコ」の帰り花を取り上げましたが、お地蔵さんの奥の林で今度は木本の『ガマズミ』が花を付けていました。
普通ならその赤い実も鳥に食べられて無くなっているか、有ったとしても水気を失って干からびている季節なのだが・・・・・? こうして見ると草も木も結構気ままに生きているのかも知れない?
白い小さな花の雄しべは長く花の外へ突き出しているのがわかります。「ガマズミ」は北海道の西南部から九州まで分布する日本の固有種。

先日「カワラナデシコ」の帰り花を取り上げましたが、お地蔵さんの奥の林で今度は木本の『ガマズミ』が花を付けていました。
普通ならその赤い実も鳥に食べられて無くなっているか、有ったとしても水気を失って干からびている季節なのだが・・・・・? こうして見ると草も木も結構気ままに生きているのかも知れない?

白い小さな花の雄しべは長く花の外へ突き出しているのがわかります。「ガマズミ」は北海道の西南部から九州まで分布する日本の固有種。
タグ :植物
2010年12月12日 Posted by 松ぽっくり at 22:37 │Comments(0) │フィールド
ドングリ
アラカシ果実
日が高くなるにつれ、気温も上がって来て、あたたかかった。
お地蔵さんの並びの『アラカシ』がドングリを沢山付けています。今年は山のドングリが少なくて熊たちが里に出没する事が多いと聞きましたがこの木は例外の様です。
アラカシはこの辺りでは一番よく見られる樫の仲間、漢字にすると「粗樫」と書き、葉がやや大きくて鋸歯が粗いのでこの名が付いたようです。
ドングリは年内に熟し、すでに落ち始めていました。

日が高くなるにつれ、気温も上がって来て、あたたかかった。
お地蔵さんの並びの『アラカシ』がドングリを沢山付けています。今年は山のドングリが少なくて熊たちが里に出没する事が多いと聞きましたがこの木は例外の様です。
アラカシはこの辺りでは一番よく見られる樫の仲間、漢字にすると「粗樫」と書き、葉がやや大きくて鋸歯が粗いのでこの名が付いたようです。
ドングリは年内に熟し、すでに落ち始めていました。
タグ :植物
2010年12月11日 Posted by 松ぽっくり at 17:19 │Comments(0) │フィールド
コントラスト
トキリマメ豆果
冷たい風の強い日でした。その為と云う訳でも有りませんが、フィールドに出れませんでした。
昨日、仲間と歩いた裏山で赤く染まった『トキリマメ』の豆果に出会いました。
「トキリマメ」の名前の由来はよく解りませんが、別名を「オオバタンキリマメ」と云い「タンキリマメ」とよく似ています。ちなみにタンキリマメの名前はその種を食べるとタンが止まる。と云う俗説によるらしい。
この2種は豆果だけ見るとはっきりしませんが、葉の質と形は明らかに異なります。豆果は熟すと二つに割れ、豆の一部がサヤにくっ付いていて赤と黒の鮮やかなコントラストを見せてくれます。

冷たい風の強い日でした。その為と云う訳でも有りませんが、フィールドに出れませんでした。
昨日、仲間と歩いた裏山で赤く染まった『トキリマメ』の豆果に出会いました。
「トキリマメ」の名前の由来はよく解りませんが、別名を「オオバタンキリマメ」と云い「タンキリマメ」とよく似ています。ちなみにタンキリマメの名前はその種を食べるとタンが止まる。と云う俗説によるらしい。
この2種は豆果だけ見るとはっきりしませんが、葉の質と形は明らかに異なります。豆果は熟すと二つに割れ、豆の一部がサヤにくっ付いていて赤と黒の鮮やかなコントラストを見せてくれます。
タグ :植物
2010年12月09日 Posted by 松ぽっくり at 17:06 │Comments(0) │下見
くっ付くための
キンミズヒキ

土手のエノキもサクラもあらかた葉を落として今日は大雪「雪もいよいよ本格的になる頃」とされていますが静岡に住んでいると大雪も小雪もあまりピンとこない。市街地に居れば雪を見る事さえが希なのです。
突き当たりの藪で『キンミズヒキ』が葉も果実も赤く染まっていました。その果実をよく見ると刺の先が鉤状に曲がっています。これで動物などにくっ付いて分布を広げていくのでしょう。
自分で移動する事の出来ない野の草たちの中にはこうして他のものにくっ付く為の構造を持ったものが多々見受けられます。


土手のエノキもサクラもあらかた葉を落として今日は大雪「雪もいよいよ本格的になる頃」とされていますが静岡に住んでいると大雪も小雪もあまりピンとこない。市街地に居れば雪を見る事さえが希なのです。
突き当たりの藪で『キンミズヒキ』が葉も果実も赤く染まっていました。その果実をよく見ると刺の先が鉤状に曲がっています。これで動物などにくっ付いて分布を広げていくのでしょう。
自分で移動する事の出来ない野の草たちの中にはこうして他のものにくっ付く為の構造を持ったものが多々見受けられます。
タグ :植物
2010年12月07日 Posted by 松ぽっくり at 17:31 │Comments(0) │フィールド
フカフカ
ヤブムラサキ果実
ガクに密生する毛が確認できます。
近くの林道を少し歩いてみました。
「イヌビワ」と「アカメガシワ」が黄葉して一帯を明るくして
いました。
「ウツギ」は真中にローソクの芯の様な花柱を残した固い実を沢山付けています。
その横に『ヤブムラサキ』がいい色になっていました。「ムラサキシキブ」とよく似ていますが、枝、葉裏、ガク、に毛が密生している事で識別します。
葉にさわるとフカフカ感があります。
しばらく続いた小春日も今日までとか、今夜あたりから崩れて寒くなるらしい。

ガクに密生する毛が確認できます。

近くの林道を少し歩いてみました。
「イヌビワ」と「アカメガシワ」が黄葉して一帯を明るくして
いました。
「ウツギ」は真中にローソクの芯の様な花柱を残した固い実を沢山付けています。
その横に『ヤブムラサキ』がいい色になっていました。「ムラサキシキブ」とよく似ていますが、枝、葉裏、ガク、に毛が密生している事で識別します。
葉にさわるとフカフカ感があります。
しばらく続いた小春日も今日までとか、今夜あたりから崩れて寒くなるらしい。
タグ :植物