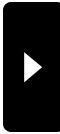連想
ラセンソウ果実

9月17日に、花と出会った『ラセンソウ』ですが、見るからにくっつきそうな果実を沢山実らせました。
その時「ラセンソウ」の名の由来を毛のある果実から毛織物を連想する、と書きましたがよくよく見ると先の曲がった鉤の様なトゲからは毛織物と云うよりはマジックテープの一面が連想されます。
今日は台風一過の晴天を期待したのですが、朝から小ぬか雨模様のはっきりしない天気です。
そんな空模様にもめげず、河原の広場はおびただしい数のシニアプレーヤーが集まっています、GGの大会のようでした。


9月17日に、花と出会った『ラセンソウ』ですが、見るからにくっつきそうな果実を沢山実らせました。
その時「ラセンソウ」の名の由来を毛のある果実から毛織物を連想する、と書きましたがよくよく見ると先の曲がった鉤の様なトゲからは毛織物と云うよりはマジックテープの一面が連想されます。
今日は台風一過の晴天を期待したのですが、朝から小ぬか雨模様のはっきりしない天気です。
そんな空模様にもめげず、河原の広場はおびただしい数のシニアプレーヤーが集まっています、GGの大会のようでした。
タグ :植物
2010年10月31日 Posted by 松ぽっくり at 22:52 │Comments(0) │畑地
他説
イヌタデ
別名はアカマンマ
明日は嵐が来ると云う、曇天の中『イヌタデ』が茶畑の法面を何処までも赤く染めていました。 どこでもみられるイヌタデですがこれだけ見事に咲いていると壮観です。
草の手入れはされていますから、農家の方もここだけあえて残したように見えます。
「犬蓼」の名前は、辛みがあって食用に利用される「ヤナギダデ」に対し、辛くないのでこの名前が付きました。
植物の世界では「似て非なるもの」「食べれない」ものなどによく「犬」を付けますがこれは蔑称では無く、否定の「イナ」が変化したもの、と云う説もあります。

別名はアカマンマ

明日は嵐が来ると云う、曇天の中『イヌタデ』が茶畑の法面を何処までも赤く染めていました。 どこでもみられるイヌタデですがこれだけ見事に咲いていると壮観です。
草の手入れはされていますから、農家の方もここだけあえて残したように見えます。
「犬蓼」の名前は、辛みがあって食用に利用される「ヤナギダデ」に対し、辛くないのでこの名前が付きました。
植物の世界では「似て非なるもの」「食べれない」ものなどによく「犬」を付けますがこれは蔑称では無く、否定の「イナ」が変化したもの、と云う説もあります。
タグ :植物
2010年10月29日 Posted by 松ぽっくり at 17:28 │Comments(0) │畑地
口をあけて
アケビ
イワシャジン
天気予報の晴れマークは今日までだったので少し安倍奥を走って来ました。しかし山に近づくにつれ雲が厚くなり新田あたりでは時折パラつく有り様・・・
暫くぶりに訪ねた大谷崩れの付近ですが、以前とは大分様変わりしていて草花の種類も少なく感じました。あれから10年以上経っているので当然と云えば当然ですが・・
それでも目的のひとつであった「イワシャジン」は寂しげに岩肌から垂れ下がっている所を見る事が出来て何となくほっとしました。
帰り道、林の出口で『アケビ』の実がひとつ大きく口を開けてぶら下がっていました。種ごと口に含んでわずかな甘さを楽しみ、その種をプッと吐き出した昔が思い出されます。

イワシャジン

天気予報の晴れマークは今日までだったので少し安倍奥を走って来ました。しかし山に近づくにつれ雲が厚くなり新田あたりでは時折パラつく有り様・・・

暫くぶりに訪ねた大谷崩れの付近ですが、以前とは大分様変わりしていて草花の種類も少なく感じました。あれから10年以上経っているので当然と云えば当然ですが・・

それでも目的のひとつであった「イワシャジン」は寂しげに岩肌から垂れ下がっている所を見る事が出来て何となくほっとしました。
帰り道、林の出口で『アケビ』の実がひとつ大きく口を開けてぶら下がっていました。種ごと口に含んでわずかな甘さを楽しみ、その種をプッと吐き出した昔が思い出されます。
タグ :植物
2010年10月27日 Posted by 松ぽっくり at 23:42 │Comments(1) │花を訪ねて
変種
シロノセンダングサ

みかん畑のミカンも大分色付い来ました、寒くなる前の穏やかな日和です。
コセンダングサは今年も至る所で盛大に存在感を示しています。そのコセンダングサの変種で白い舌状花のある『シロノセンダングサ』が昨年と同じ土手で姿を見せていました。
白い舌状花以外はコセンダングサとそっくりなので花が咲くまではそれと気づきません。
在来種で黄色の舌状花の「センダングサ」は「コセンダングサ」に圧倒され最近ほとんど見られなくなってしまいました。


みかん畑のミカンも大分色付い来ました、寒くなる前の穏やかな日和です。
コセンダングサは今年も至る所で盛大に存在感を示しています。そのコセンダングサの変種で白い舌状花のある『シロノセンダングサ』が昨年と同じ土手で姿を見せていました。
白い舌状花以外はコセンダングサとそっくりなので花が咲くまではそれと気づきません。
在来種で黄色の舌状花の「センダングサ」は「コセンダングサ」に圧倒され最近ほとんど見られなくなってしまいました。

タグ :植物
2010年10月26日 Posted by 松ぽっくり at 17:50 │Comments(0) │フィールド
流れ落ちて
ダイモンジソウ
10月も半ばを過ぎたので、いつもの所へ『ダイモンジソウ』を見に行って来ました。
昨夜の雨で崖の水量は多く「滴る」と云うより幾すじも「流れ落ちて」いました。
花に少しでも近づきたいが、濡れたくもない、と云う相反する気持ちを整理するのに少々手間取りましたが、結論はカメラさえ濡れなければ良いと云う事に落ち着きました。
花は今年も順調で崖の上半部は一面白く見える程びっしりと咲いています。少し盛りは過ぎた感はありますが、まだまだ壮観でした。
この花は日本全土の低地から高山帯までと分布が広い為、形は変化に富み、多くの変種があるようです。

10月も半ばを過ぎたので、いつもの所へ『ダイモンジソウ』を見に行って来ました。
昨夜の雨で崖の水量は多く「滴る」と云うより幾すじも「流れ落ちて」いました。
花に少しでも近づきたいが、濡れたくもない、と云う相反する気持ちを整理するのに少々手間取りましたが、結論はカメラさえ濡れなければ良いと云う事に落ち着きました。
花は今年も順調で崖の上半部は一面白く見える程びっしりと咲いています。少し盛りは過ぎた感はありますが、まだまだ壮観でした。
この花は日本全土の低地から高山帯までと分布が広い為、形は変化に富み、多くの変種があるようです。
タグ :植物
2010年10月25日 Posted by 松ぽっくり at 23:21 │Comments(2) │花見
質感
カワラハハコ
カワラハハコ雌花
スポーツの秋、と云う事で日曜の河原は大賑わい、Gゴルフ、ゲートボール、野球、ジョギングと皆さんそれぞれに体を動かしています。
草地に目をやると白いかたまりが、所どころにに目立ちます。今年も『カワラハハコ』が盛りを迎えたようです。
そのナマの内から「ドライフラワー」の様な質感の花は、これから訪れる白い季節を予感させるように、私達の目にささやき掛けます。
桜の梢で白い紋付姿の「ジョウビタキ」が尻尾を細かく振っていました。
今季の初見です。


カワラハハコ雌花

スポーツの秋、と云う事で日曜の河原は大賑わい、Gゴルフ、ゲートボール、野球、ジョギングと皆さんそれぞれに体を動かしています。
草地に目をやると白いかたまりが、所どころにに目立ちます。今年も『カワラハハコ』が盛りを迎えたようです。
そのナマの内から「ドライフラワー」の様な質感の花は、これから訪れる白い季節を予感させるように、私達の目にささやき掛けます。
桜の梢で白い紋付姿の「ジョウビタキ」が尻尾を細かく振っていました。
今季の初見です。

タグ :植物
2010年10月24日 Posted by 松ぽっくり at 14:53 │Comments(0) │フィールド
日溜まりに
イヌコウジュ

土手横、石積みの裾、比較的湿り気のある日溜まりに『イヌコウジュ』が小さな花をまばらに付けていました。
花の大きさは3~4ミリ、咲き方も一斉には咲かないのであまり目立ちません。
よく似ている「ヒメジソ」とは細毛が多い事、ガクの先端が鋭くとがる事などで識別出来ます。
漢字にすると「犬香需」となるようですが、いわれはよく解りません。
今朝は「霜降」の暦通り、それなりに寒い朝でした。


土手横、石積みの裾、比較的湿り気のある日溜まりに『イヌコウジュ』が小さな花をまばらに付けていました。
花の大きさは3~4ミリ、咲き方も一斉には咲かないのであまり目立ちません。
よく似ている「ヒメジソ」とは細毛が多い事、ガクの先端が鋭くとがる事などで識別出来ます。
漢字にすると「犬香需」となるようですが、いわれはよく解りません。
今朝は「霜降」の暦通り、それなりに寒い朝でした。
タグ :植物
2010年10月23日 Posted by 松ぽっくり at 16:55 │Comments(0) │フィールド
覗いています
ガガイモの袋果
やっと出会いました!細い水路に設けられた金網に金網が見えなくなるほど絡みついた「ガガイモ」の葉の間から「袋果」がひとつこちらを覗いています。
土手の斜面には沢山ある「ガガイモ」ですが、花が咲いてしばらくすると刈り取られてしまうので実を結ぶ所を見る事が出来ず残念に思っていました。今回は刈られる心配のない所なので期待が出来そうです。
まだ未熟ですがこれから秋が深まり完熟して割れ、中から長い毛(種髪)のある種が晩秋の風に飛び散るところを確認したいものです。

やっと出会いました!細い水路に設けられた金網に金網が見えなくなるほど絡みついた「ガガイモ」の葉の間から「袋果」がひとつこちらを覗いています。
土手の斜面には沢山ある「ガガイモ」ですが、花が咲いてしばらくすると刈り取られてしまうので実を結ぶ所を見る事が出来ず残念に思っていました。今回は刈られる心配のない所なので期待が出来そうです。
まだ未熟ですがこれから秋が深まり完熟して割れ、中から長い毛(種髪)のある種が晩秋の風に飛び散るところを確認したいものです。
タグ :植物
2010年10月22日 Posted by 松ぽっくり at 21:56 │Comments(0) │フィールド
雨模様
ミゾソバ

雨模様の土手下の細い水路、先日の「ヤナギタデ」に続いて『ミゾソバ』が先端を紅く染めて金平糖のように咲き始めました。タデの仲間にあっては遅咲きで、これから晩秋にかけて湿地や溝をうめる様に彩ります。
同じタデ科の「サクラタデ」が個体の美しさなら「ミゾソバ』は集合の美しさと云えるかも知れない。
葉の形が牛の顔の形に似ている事から「ウシノヒタイ」の別名があります。
はっきりしない雨模様が2日続いて若干肌寒く感じますが、気温は平年並みらしい。


雨模様の土手下の細い水路、先日の「ヤナギタデ」に続いて『ミゾソバ』が先端を紅く染めて金平糖のように咲き始めました。タデの仲間にあっては遅咲きで、これから晩秋にかけて湿地や溝をうめる様に彩ります。

同じタデ科の「サクラタデ」が個体の美しさなら「ミゾソバ』は集合の美しさと云えるかも知れない。
葉の形が牛の顔の形に似ている事から「ウシノヒタイ」の別名があります。
はっきりしない雨模様が2日続いて若干肌寒く感じますが、気温は平年並みらしい。
タグ :植物
2010年10月21日 Posted by 松ぽっくり at 17:01 │Comments(0) │フィールド
仲良く再生
チカラシバとアオチカラシバ




草を刈った後の斜面に『チカラシバ』と『アオチカラシバ』が仲良く再生していました。
踏まれ強く、しっかり根を張っているので引っ張っても容易に抜けない事から「力芝」の名前が付いたようです。
昔の悪童たちはこの草の穂と穂を結んで「足罠」を作ったり、穂を引き抜いて友達の後ろから首筋をそっとなでて驚かしたりして遊んでいました。
晩秋に草むらを歩くとこの草の実が沢山くっついて閉口する事があります。




草を刈った後の斜面に『チカラシバ』と『アオチカラシバ』が仲良く再生していました。
踏まれ強く、しっかり根を張っているので引っ張っても容易に抜けない事から「力芝」の名前が付いたようです。
昔の悪童たちはこの草の穂と穂を結んで「足罠」を作ったり、穂を引き抜いて友達の後ろから首筋をそっとなでて驚かしたりして遊んでいました。
晩秋に草むらを歩くとこの草の実が沢山くっついて閉口する事があります。
タグ :植物
2010年10月19日 Posted by 松ぽっくり at 17:06 │Comments(0) │フィールド
しびれる程辛い
ヤナギタデ
秋はタデの季節でも有る、イヌタデ、ハナタデ、サクラタデ、次々と小さな花を付ける。
土手下の水路に『ヤナギタデ』が花穂を垂らしていた。葉を噛むと舌がしびれる程
辛い、その辛さは少し遅れてやってくる。「蓼食う虫も好き好き」のタデはこのタデを指す。
「マタデ」「ホンタデ」などと呼ばれ、その辛さが刺身のツマとして好まれる。
いくつかの栽培品があって、種をまいてそこから出た若芽を利用するようだ。
今季初の寒い朝だった。秋もいよいよ本格化?

秋はタデの季節でも有る、イヌタデ、ハナタデ、サクラタデ、次々と小さな花を付ける。
土手下の水路に『ヤナギタデ』が花穂を垂らしていた。葉を噛むと舌がしびれる程
辛い、その辛さは少し遅れてやってくる。「蓼食う虫も好き好き」のタデはこのタデを指す。
「マタデ」「ホンタデ」などと呼ばれ、その辛さが刺身のツマとして好まれる。
いくつかの栽培品があって、種をまいてそこから出た若芽を利用するようだ。
今季初の寒い朝だった。秋もいよいよ本格化?
タグ :植物
2010年10月18日 Posted by 松ぽっくり at 17:20 │Comments(0) │フィールド
巻きひげに
オオバクサフジ


今日は法事で沼津に行って来ました。少々早く着き過ぎたので裏山の農道を覗いてみる事に、いい具合と云うかどうか?手が入っておらず草が生い茂っています。
ヤブマメは至る所でススキや低木に絡みつき小さな花を沢山付けています。トキリマメは花が終わり若い豆果がぶら下がっていました。そんな道沿いで『オオバクサフジ』が一区画を彩っていました。葉の先が巻きひげになって周りの草木に絡みついています。クサフジの仲間では葉が大きいので「大葉草藤」と名前が付いたようです。
心の中の故郷の景色に必ず現れる人々が少しずつかけていく。


今日は法事で沼津に行って来ました。少々早く着き過ぎたので裏山の農道を覗いてみる事に、いい具合と云うかどうか?手が入っておらず草が生い茂っています。
ヤブマメは至る所でススキや低木に絡みつき小さな花を沢山付けています。トキリマメは花が終わり若い豆果がぶら下がっていました。そんな道沿いで『オオバクサフジ』が一区画を彩っていました。葉の先が巻きひげになって周りの草木に絡みついています。クサフジの仲間では葉が大きいので「大葉草藤」と名前が付いたようです。
心の中の故郷の景色に必ず現れる人々が少しずつかけていく。
タグ :植物
2010年10月17日 Posted by 松ぽっくり at 23:23 │Comments(0) │出先で
見応えのある
サクラタデ
サクラタデ雌花、3本の花柱は雄しべより長く花の外へ突き出る

先日「ヤマハッカ」の咲いていた草地の並びで少し離れた道端に『サクラタデ』が咲き始めました。
サクラタデは水辺や湿地に生えるものと決め込んでいたので、これもまた意外でした。
今は茶畑や畑になっているが、川からそんなに離れていない事を考えると昔は湿地だったのかも知れない。
それはともかくとして、地味なものが多いタデの仲間の中にあって1個1個の花の大きさと云い淡いピンクの花の色と云い、充分に見応えがあり、好きな花のひとつです。
この所思いがけない出会いが続きます。

サクラタデ雌花、3本の花柱は雄しべより長く花の外へ突き出る

先日「ヤマハッカ」の咲いていた草地の並びで少し離れた道端に『サクラタデ』が咲き始めました。
サクラタデは水辺や湿地に生えるものと決め込んでいたので、これもまた意外でした。
今は茶畑や畑になっているが、川からそんなに離れていない事を考えると昔は湿地だったのかも知れない。
それはともかくとして、地味なものが多いタデの仲間の中にあって1個1個の花の大きさと云い淡いピンクの花の色と云い、充分に見応えがあり、好きな花のひとつです。
この所思いがけない出会いが続きます。

タグ :植物
2010年10月15日 Posted by 松ぽっくり at 23:26 │Comments(0) │畑地
油を塗ったような
アブラススキ

一番先に草刈りされた斜面に『アブラススキ』が7~8本頼りなげに風に揺れています。
花序は垂れて元気なさそうに見えますが、これがアブラススキのスタイル。
茎や花序の軸から粘液を出し、油を塗ったような光沢と臭気があるので「油薄」の名前が付いたらしい。その粘液に時々小さな虫がくっ付いているのを見かけます。
今日も日中は夏日、平年並みの気温になるのは週末とか


一番先に草刈りされた斜面に『アブラススキ』が7~8本頼りなげに風に揺れています。
花序は垂れて元気なさそうに見えますが、これがアブラススキのスタイル。
茎や花序の軸から粘液を出し、油を塗ったような光沢と臭気があるので「油薄」の名前が付いたらしい。その粘液に時々小さな虫がくっ付いているのを見かけます。
今日も日中は夏日、平年並みの気温になるのは週末とか
タグ :植物
2010年10月14日 Posted by 松ぽっくり at 22:06 │Comments(0) │フィールド
ちょっと意外
ヤマハッカ


土手下、茶畑の外側に草達が密生している「お気に入り」の空地があります「カナムグラ」「イシミカワ」などに絡みつかれながら「メマツヨイグサ」「ヌカキビ」「ハナタデ」 他が生えています。
その中に今日新たに『ヤマハッカ』が咲いているのを見つけました。ちょっと意外でした。今まで何度も「ヤマハッカ」は見ていますが、いずれも山地と云うか農道や林道の脇などが多かったので、まさか民家近くの舗装された道路に面した所で出会うとは思っていませんでした。
「ハッカ」の名が付いていますが、ハッカ臭はありません。


土手下、茶畑の外側に草達が密生している「お気に入り」の空地があります「カナムグラ」「イシミカワ」などに絡みつかれながら「メマツヨイグサ」「ヌカキビ」「ハナタデ」 他が生えています。
その中に今日新たに『ヤマハッカ』が咲いているのを見つけました。ちょっと意外でした。今まで何度も「ヤマハッカ」は見ていますが、いずれも山地と云うか農道や林道の脇などが多かったので、まさか民家近くの舗装された道路に面した所で出会うとは思っていませんでした。
「ハッカ」の名が付いていますが、ハッカ臭はありません。
タグ :植物
2010年10月13日 Posted by 松ぽっくり at 23:51 │Comments(0) │フィールド
コリコリして美味?
キクイモ

ススキの開花が例年に比べ一ヶ月以上遅れて今日発表されました。
河原では『キクイモ』も大分遅れ「ススキ」や「セイタカアワダチソウ」などをかき分けてやっと花を見せています。
地下にイモが出来るのでこの名前が付いた事は前回書きましたが、この芋が漬けものにするとコリコリして美味しいと云う事を本で見ました、にわかには信じがたいが・・・
空では秋の雲と夏の雲がせめぎ合い、日中は結構汗ばむ陽気でした。

ススキの開花が例年に比べ一ヶ月以上遅れて今日発表されました。
河原では『キクイモ』も大分遅れ「ススキ」や「セイタカアワダチソウ」などをかき分けてやっと花を見せています。
地下にイモが出来るのでこの名前が付いた事は前回書きましたが、この芋が漬けものにするとコリコリして美味しいと云う事を本で見ました、にわかには信じがたいが・・・
空では秋の雲と夏の雲がせめぎ合い、日中は結構汗ばむ陽気でした。
タグ :植物
2010年10月12日 Posted by 松ぽっくり at 22:07 │Comments(3) │フィールド
怪魚のように
ツリフネソウ


朝からの快晴に誘われて山道を走って来ました。道沿いには「ノコンギク」が咲き乱れ秋を演出し、木陰には『ツリフネソウ』も群落を作っていました。
ツリフネソウはガク片3、花弁3、からなりガク片も花弁と同じ色で下の1個は大きく袋状になりその先端がクルリと巻き、そこに蜜をためています。
名前は花の形を「帆をかけた舟」に見立てて「釣舟草」となったようです。ただ正面から見ると大きく口を開けた怪魚の様にも見えます。
別名を「ヤマホウセンカ」と云うように「ホウセンカ」の仲間で、果実は熟すとちょっとした刺激で種をはじき飛ばします。
山道も標高が上がるとカラマツに絡みついた「ツタウルシ」などはすでに色付き始めていました。


朝からの快晴に誘われて山道を走って来ました。道沿いには「ノコンギク」が咲き乱れ秋を演出し、木陰には『ツリフネソウ』も群落を作っていました。
ツリフネソウはガク片3、花弁3、からなりガク片も花弁と同じ色で下の1個は大きく袋状になりその先端がクルリと巻き、そこに蜜をためています。
名前は花の形を「帆をかけた舟」に見立てて「釣舟草」となったようです。ただ正面から見ると大きく口を開けた怪魚の様にも見えます。
別名を「ヤマホウセンカ」と云うように「ホウセンカ」の仲間で、果実は熟すとちょっとした刺激で種をはじき飛ばします。
山道も標高が上がるとカラマツに絡みついた「ツタウルシ」などはすでに色付き始めていました。
タグ :植物
2010年10月12日 Posted by 松ぽっくり at 00:01 │Comments(1) │花を訪ねて
カラフルだが
ノブドウ

土手下の笹に絡んだ『ノブドウ』の実がいい色になっていました。
野原や林縁などごく普通に生えているブドウ科の多年草です。ブドウ科は木本が多いですがノブドウは草本に区分されています。
以前に取り上げた通り花は極端に地味ですが、果実は緑から白、青、紫、紺へと変化して結構カラフルです。ただ味の方はまずくてとても食えた代物ではありません。それと「ブドウタマバエ」などの幼虫が寄生して、虫こぶが出来ているものが多いようです。

土手下の笹に絡んだ『ノブドウ』の実がいい色になっていました。
野原や林縁などごく普通に生えているブドウ科の多年草です。ブドウ科は木本が多いですがノブドウは草本に区分されています。
以前に取り上げた通り花は極端に地味ですが、果実は緑から白、青、紫、紺へと変化して結構カラフルです。ただ味の方はまずくてとても食えた代物ではありません。それと「ブドウタマバエ」などの幼虫が寄生して、虫こぶが出来ているものが多いようです。
タグ :植物
2010年10月10日 Posted by 松ぽっくり at 17:54 │Comments(0) │フィールド
好みの色
ヤブマメ


朝から雨で一日閉じ込められてしまいました。
2日に農道を覗いた時出会った『ヤブマメ』の花が私好みの色をしていたので紹介する事にします。
ヤブマメは草地や野山などに普通に見られる「マメ科」のツル植物で決して珍しくはありませんが、花の色は生えている場所によって微妙に異なり、ついついシャッターを押してしまいます。
豆果は普通3個の豆が入っていて、強いて言えばウズラの卵に似た模様をしています。
秋が深まると葉は黄色に色付きます。


朝から雨で一日閉じ込められてしまいました。
2日に農道を覗いた時出会った『ヤブマメ』の花が私好みの色をしていたので紹介する事にします。
ヤブマメは草地や野山などに普通に見られる「マメ科」のツル植物で決して珍しくはありませんが、花の色は生えている場所によって微妙に異なり、ついついシャッターを押してしまいます。
豆果は普通3個の豆が入っていて、強いて言えばウズラの卵に似た模様をしています。
秋が深まると葉は黄色に色付きます。
タグ :植物
2010年10月09日 Posted by 松ぽっくり at 17:37 │Comments(2) │下見
勝手気まま
オガルカヤ


刈り残された斜面の草むらから「カンタン」のか細い声が聞こえるようになって今日は「寒露」秋も深まる頃、のはずだがそこはそれ、中々暦どうりにはいかない。
土手の下では『オガルカヤ』が小穂の集団を左右に広げています。離れてみるとそれが幾つも重なって勝手気ままに穂を出しているように見えます。
「オガルカヤ」は「メガルカヤ」に対しての名前。「カルカヤ」とは屋根を葺くために刈り取る草の総称だった様です。


刈り残された斜面の草むらから「カンタン」のか細い声が聞こえるようになって今日は「寒露」秋も深まる頃、のはずだがそこはそれ、中々暦どうりにはいかない。
土手の下では『オガルカヤ』が小穂の集団を左右に広げています。離れてみるとそれが幾つも重なって勝手気ままに穂を出しているように見えます。
「オガルカヤ」は「メガルカヤ」に対しての名前。「カルカヤ」とは屋根を葺くために刈り取る草の総称だった様です。
タグ :植物