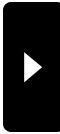隙間に
トウネズミモチ

防災用のブロックの隙間に生えている『トウネズミモチ』が枝先によく目立つ大きな花序を付けた。
鳥の糞が運よく20cm程の隙間に落ちて育ったものでしょう。
小さな花の集まりにはハナムグリの仲間や様々な虫達が訪れ、そのおかげで秋にはたわわに実を付けます。
中国原産で明治の頃に入ったと云われていますが、成長が早く丈夫なので公園や工場の緑化樹として、今でもよく植栽されています。
名前の方は外国産で「ネズミモチ」に似ているので「唐鼠黐」となりました。
漢方では果実を乾燥させたものを「女貞」と呼び、強壮薬として使われるとの事です。


防災用のブロックの隙間に生えている『トウネズミモチ』が枝先によく目立つ大きな花序を付けた。
鳥の糞が運よく20cm程の隙間に落ちて育ったものでしょう。
小さな花の集まりにはハナムグリの仲間や様々な虫達が訪れ、そのおかげで秋にはたわわに実を付けます。
中国原産で明治の頃に入ったと云われていますが、成長が早く丈夫なので公園や工場の緑化樹として、今でもよく植栽されています。
名前の方は外国産で「ネズミモチ」に似ているので「唐鼠黐」となりました。
漢方では果実を乾燥させたものを「女貞」と呼び、強壮薬として使われるとの事です。
タグ :植物
2011年06月30日 Posted by 松ぽっくり at 17:04 │Comments(0) │フィールド
麻糸を巻いた
ヤマオダマキ
暑さから逃れようと高みへ出かけてみました。
山肌のあちこちで「マタタビ」の葉が白くなり花のありかを教えていて、この時季になると思いの外沢山ある事が判明する。
峠の手前の道端に『ヤマオダマキ』が咲き始めていました。この花も以前に比べ見る機会が減った様に思います。そばに掘り起こした様な形跡も有り、もしかするとここも・・・
花の色は一般的にはもう少し色が濃いようですが、この個体はかなりうすかった。
そばには花全体が薄黄色の「キバナノヤマオダマキ」と呼ばれるタイプのものも有りました。
ちなみに「オダマキ」とは昔、麻糸を巻いた管の事で、花がその形に似ているからと「山苧環」になったようです。
峠に着いてもそれ程気温が変わる訳でもないが、降り注ぐ「エゾハルゼミ」の声や突然頭上で茶筒を叩く様な「ツツドリ」の声に幾分暑さを忘れる事が出来た。

暑さから逃れようと高みへ出かけてみました。
山肌のあちこちで「マタタビ」の葉が白くなり花のありかを教えていて、この時季になると思いの外沢山ある事が判明する。
峠の手前の道端に『ヤマオダマキ』が咲き始めていました。この花も以前に比べ見る機会が減った様に思います。そばに掘り起こした様な形跡も有り、もしかするとここも・・・

花の色は一般的にはもう少し色が濃いようですが、この個体はかなりうすかった。
そばには花全体が薄黄色の「キバナノヤマオダマキ」と呼ばれるタイプのものも有りました。
ちなみに「オダマキ」とは昔、麻糸を巻いた管の事で、花がその形に似ているからと「山苧環」になったようです。
峠に着いてもそれ程気温が変わる訳でもないが、降り注ぐ「エゾハルゼミ」の声や突然頭上で茶筒を叩く様な「ツツドリ」の声に幾分暑さを忘れる事が出来た。
タグ :植物
2011年06月29日 Posted by 松ぽっくり at 23:00 │Comments(0) │何かあるかな
味のランク
ナワシロイチゴ
午前中に35℃を越してアスファルトの照り返しがはんぱでない。ラジオでは九州南部の
梅雨明けを伝えている。どうも気象の常識が覆りつつあるようだ。
出先の石垣に『ナワシロイチゴ』が沢山の赤い実を付けていた。一番良さそうなやつを口に入れてみたが味は今いち、以前に完熟したものをいただいた時はかなり甘味があったのだが・・・。それと「クサイチゴ」などに比べると種がしっかりしているので後味ももう一つ。
この辺の野山で見られる野イチゴの味にランクを付けるとすれば1位が「モミジイチゴ」2位が「クサイチゴ」その後に「ナワシロイチゴ」「ニガイチゴ」「クマイチゴ」などがほぼ同率で並ぶ。あくまで私見だが!

午前中に35℃を越してアスファルトの照り返しがはんぱでない。ラジオでは九州南部の
梅雨明けを伝えている。どうも気象の常識が覆りつつあるようだ。
出先の石垣に『ナワシロイチゴ』が沢山の赤い実を付けていた。一番良さそうなやつを口に入れてみたが味は今いち、以前に完熟したものをいただいた時はかなり甘味があったのだが・・・。それと「クサイチゴ」などに比べると種がしっかりしているので後味ももう一つ。
この辺の野山で見られる野イチゴの味にランクを付けるとすれば1位が「モミジイチゴ」2位が「クサイチゴ」その後に「ナワシロイチゴ」「ニガイチゴ」「クマイチゴ」などがほぼ同率で並ぶ。あくまで私見だが!
タグ :植物
2011年06月28日 Posted by 松ぽっくり at 18:07 │Comments(0) │出先で
恐らく
ドクウツギ
朝から降ったり照ったりの荒れた天気、気温は昨日より多少低いがそれでも結構暑い。
河原の『ドクウツギ』の実が黒くなってきた。ものの本には「果実は甘い」と書いてあるが、シタワレ、ネジコロシ、オニコロシ、ウマオドロカシ、ヒトコロビ、イチロベゴロシ、
など
物騒な別名の数々を知っていたり、植物を少しでもかじった事のある者ならまず口にしないでしょう。
昔から「食うと死ぬ」と評判の高い植物ですから!
黒く熟した実はやがて地面に落ちるが、その辺りにアリが群がっているのが見られるので、
恐らく甘いのでしょう。評判の猛毒もどうやらアリには通用しないとみえる。

朝から降ったり照ったりの荒れた天気、気温は昨日より多少低いがそれでも結構暑い。
河原の『ドクウツギ』の実が黒くなってきた。ものの本には「果実は甘い」と書いてあるが、シタワレ、ネジコロシ、オニコロシ、ウマオドロカシ、ヒトコロビ、イチロベゴロシ、
など
物騒な別名の数々を知っていたり、植物を少しでもかじった事のある者ならまず口にしないでしょう。
昔から「食うと死ぬ」と評判の高い植物ですから!
黒く熟した実はやがて地面に落ちるが、その辺りにアリが群がっているのが見られるので、
恐らく甘いのでしょう。評判の猛毒もどうやらアリには通用しないとみえる。
タグ :植物
2011年06月27日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(0) │フィールド
母の草
メハジキ

中々暑さが収まらない、まさかこのまま夏に突入と云う訳ではあるまいが・・・。
今日はいつもの農道に『メハジキ』を確認に行って来ました。
相変わらず舗装道と壁面の隙間に一列に並んで咲いていますが、半分以上がすでに花が終わっていました。昨年に比べると随分早いようです。
それにしてもどうしてこんな隙間に生えるのか理解不能、そばに空地はいくらでもあるのに?
漢方でこの草を乾燥させて、婦人薬として使う事は以前にも書きましたが、欧米でもこの
仲間を「motherwoet」(母の草)と呼んで利用されるようです。


中々暑さが収まらない、まさかこのまま夏に突入と云う訳ではあるまいが・・・。
今日はいつもの農道に『メハジキ』を確認に行って来ました。
相変わらず舗装道と壁面の隙間に一列に並んで咲いていますが、半分以上がすでに花が終わっていました。昨年に比べると随分早いようです。
それにしてもどうしてこんな隙間に生えるのか理解不能、そばに空地はいくらでもあるのに?
漢方でこの草を乾燥させて、婦人薬として使う事は以前にも書きましたが、欧米でもこの
仲間を「motherwoet」(母の草)と呼んで利用されるようです。
タグ :植物
2011年06月26日 Posted by 松ぽっくり at 18:07 │Comments(0) │花を訪ねて
特異な
ウマノスズクサ

いつものフィールドから大分河口側へ下がった土手で以前に見た
『ウマノスズクサ』を探しに行ってみた。
所がそこには「除草作業中!」の看板が立っている。「遅かったかー」と思いつつも近寄って見ると、始まったばかりで目的の場所はまだ刈られていない。
急いで先回りして斜面を探すと他の草と絡まり合って特異な形の花が幾つも咲いている。それではとコンデジを取り出して撮ろうとすると今度は風が遊びにやって来て焦らせる。
うーん・・・
何とか10枚程撮った所で自走式の草刈り車の音が近づいて来た。あぶなかった!
この独特の花はガクが筒状になったもので、ラッパ状の先端部には内側に向いた毛が密生して虫が入り易く、出にくくなっている。下の丸くなった所に花柱と雄しべが入っている。
花は何度か見ているがまだ果実を見た事がない。結実の確率が低いらしい。
そして「ウマノスズクサ」の名前は、その果実のようすを馬の首に付ける鈴に見立てて付けられた、と云われている。そんな訳で一度果実を見てみたいと思っているのだが・・・・。


いつものフィールドから大分河口側へ下がった土手で以前に見た
『ウマノスズクサ』を探しに行ってみた。
所がそこには「除草作業中!」の看板が立っている。「遅かったかー」と思いつつも近寄って見ると、始まったばかりで目的の場所はまだ刈られていない。
急いで先回りして斜面を探すと他の草と絡まり合って特異な形の花が幾つも咲いている。それではとコンデジを取り出して撮ろうとすると今度は風が遊びにやって来て焦らせる。
うーん・・・
何とか10枚程撮った所で自走式の草刈り車の音が近づいて来た。あぶなかった!
この独特の花はガクが筒状になったもので、ラッパ状の先端部には内側に向いた毛が密生して虫が入り易く、出にくくなっている。下の丸くなった所に花柱と雄しべが入っている。
花は何度か見ているがまだ果実を見た事がない。結実の確率が低いらしい。
そして「ウマノスズクサ」の名前は、その果実のようすを馬の首に付ける鈴に見立てて付けられた、と云われている。そんな訳で一度果実を見てみたいと思っているのだが・・・・。
タグ :植物
2011年06月24日 Posted by 松ぽっくり at 17:43 │Comments(0) │花を訪ねて
盛んに繁茂する
ヤブガラシ
花弁と雄しべは午前中に落ちてしまう
連日の真夏日。空調のリモコンについ手が伸びてしまう。
この季節はつる植物がよく目に付く。金網に絡みついた『ヤブガラシ』が沢山の花を付け、その小さな花にミツバチが入れ替わり立ち替わり訪れていた。
この花はガクが退化し、緑色の花弁、雄しべ4、雌しべ1からなるが、開花すると間もなく花弁と雄しべは散り落ちていまい、後に雌しべとその子房をとりまく花盤が残る。
花盤ははじめオレンジ色でのちにうすいピンクに変わるがこの小さな花盤から蜜が分泌され、花弁が落ちた後も昆虫達が次々にやって来る。
名前は地下茎を長く延ばし、藪を枯らす程さかんに繁茂する事から「藪枯らし」と付けられたようです。別名は「貧乏蔓」

花弁と雄しべは午前中に落ちてしまう

連日の真夏日。空調のリモコンについ手が伸びてしまう。
この季節はつる植物がよく目に付く。金網に絡みついた『ヤブガラシ』が沢山の花を付け、その小さな花にミツバチが入れ替わり立ち替わり訪れていた。
この花はガクが退化し、緑色の花弁、雄しべ4、雌しべ1からなるが、開花すると間もなく花弁と雄しべは散り落ちていまい、後に雌しべとその子房をとりまく花盤が残る。
花盤ははじめオレンジ色でのちにうすいピンクに変わるがこの小さな花盤から蜜が分泌され、花弁が落ちた後も昆虫達が次々にやって来る。
名前は地下茎を長く延ばし、藪を枯らす程さかんに繁茂する事から「藪枯らし」と付けられたようです。別名は「貧乏蔓」

タグ :植物
2011年06月23日 Posted by 松ぽっくり at 17:29 │Comments(0) │フィールド
黄ばみ始めた
アワブキ

今日は「夏至」 葵区の日の入りはわずかだが7時を回る。冬至の頃と比べると2時間余りのびた事になる。
それにしても随分と暑いので少し藁科の奥を走ってみましたが余り変わりはなかった。
道沿いの林縁で『アワブキ』が盛り上がる様に花を付けている。
少し盛りが過ぎて白い小さな花が黄ばみ始めています。それでも手の届きそうな距離で確認するのは初めて、近づくとほんのり良い香りがします。
「アワブキ」の花の作りは変っているのでしっかり見てやろうと思ったが・・・1個の花は5ミリにも満たないほど小さいのと、風に負けた画像の為、確認は次回に譲るしかない。
「アワブキ」の名前はこの木を燃やすと切り口から盛んに泡を出すので「泡吹」となったようです。


今日は「夏至」 葵区の日の入りはわずかだが7時を回る。冬至の頃と比べると2時間余りのびた事になる。
それにしても随分と暑いので少し藁科の奥を走ってみましたが余り変わりはなかった。
道沿いの林縁で『アワブキ』が盛り上がる様に花を付けている。
少し盛りが過ぎて白い小さな花が黄ばみ始めています。それでも手の届きそうな距離で確認するのは初めて、近づくとほんのり良い香りがします。
「アワブキ」の花の作りは変っているのでしっかり見てやろうと思ったが・・・1個の花は5ミリにも満たないほど小さいのと、風に負けた画像の為、確認は次回に譲るしかない。
「アワブキ」の名前はこの木を燃やすと切り口から盛んに泡を出すので「泡吹」となったようです。
タグ :植物
2011年06月22日 Posted by 松ぽっくり at 17:38 │Comments(0) │何かあるかな
成長が早く
アカメガシワ雌花

雄花
天気は急速に回復し昼前には日が差して南西の風が強い。
今年も『アカメガシワ』が花を付けて、1年の半分が終わろうとしている・・・。
日当たりの良い所が好きなこの木は成長が早く、数年で5㍍程の高さになるものもある。
土手下に何本も並んでいる「アカメガシワ」はまだ3㍍程だがそろって花を付けてた。
雌雄別株で、花には花弁が無い。雄花は多数の雄しべが丸くなって小さなポンポンの様に見える。雌花も沢山並んで付き、3つに開いた雌しべの先だけが目立つ。
ごくありふれた木だが、樹皮を煎じたりエキスを胃酸過多や胃潰瘍の薬としても使われたようだ。

雄花

天気は急速に回復し昼前には日が差して南西の風が強い。
今年も『アカメガシワ』が花を付けて、1年の半分が終わろうとしている・・・。
日当たりの良い所が好きなこの木は成長が早く、数年で5㍍程の高さになるものもある。
土手下に何本も並んでいる「アカメガシワ」はまだ3㍍程だがそろって花を付けてた。
雌雄別株で、花には花弁が無い。雄花は多数の雄しべが丸くなって小さなポンポンの様に見える。雌花も沢山並んで付き、3つに開いた雌しべの先だけが目立つ。
ごくありふれた木だが、樹皮を煎じたりエキスを胃酸過多や胃潰瘍の薬としても使われたようだ。
タグ :植物
2011年06月21日 Posted by 松ぽっくり at 16:41 │Comments(0) │フィールド
意外に大きい
ナヨクサフジ
意外に大きい豆果
朝からはっきりしない空模様だったが何とか一日もってくれた。
所用で出かけた帰り、遊水池のそばで『ナヨクサフジ』がアシに絡みついていた。
盛りは過ぎていて、すでに豆果も出来ている。花は時々みかけるが豆果は始めてみます。
意外に大きくてびっくり!
ヨーロッパ原産で飼料や緑肥として導入されたものが現在ではほぼ全国的に野生化しているようです。
在来の「クサフジ」とよく似ていますが、花柄がガクの後端に付く「クサフジ」に対し、「ナヨクサフジ」の花柄は少し前にずれてガクの下側に付きます。
週刊予報を見ると雲と傘のマークがずらっと並んでいる。この時季仕方ない事だが・・・・・

意外に大きい豆果

朝からはっきりしない空模様だったが何とか一日もってくれた。
所用で出かけた帰り、遊水池のそばで『ナヨクサフジ』がアシに絡みついていた。
盛りは過ぎていて、すでに豆果も出来ている。花は時々みかけるが豆果は始めてみます。
意外に大きくてびっくり!
ヨーロッパ原産で飼料や緑肥として導入されたものが現在ではほぼ全国的に野生化しているようです。
在来の「クサフジ」とよく似ていますが、花柄がガクの後端に付く「クサフジ」に対し、「ナヨクサフジ」の花柄は少し前にずれてガクの下側に付きます。
週刊予報を見ると雲と傘のマークがずらっと並んでいる。この時季仕方ない事だが・・・・・

タグ :植物
2011年06月19日 Posted by 松ぽっくり at 20:59 │Comments(0) │寄り道
板バネの
アメリカフウロ(角果)
雨は期待通り昼前に上がってくれた。このまま明日の夕方までもってくれる事を再度祈ろう。
土手の下で『アメリカフウロ』の角果が思いっきり反り返っていた。
板バネの様に反り返っている部分は始めまっすぐ下にくっ付いているが熟すと1個ずつ上に反り返る、その反動を利用して種を遠くに弾き飛ばす。分布を広げる為の知恵だろう!
これは「フウロソウ属」の特徴で、在来種の「ゲンノショウコ」も全く同じ仕組みで種を弾き飛ばす。日本産の「フウロソウ属」の種は表面が滑らかだが、「アメリカフウロ」の種は網目状の隆起した模様がある。
土手の斜面に上がってきた「キジ♂」とばったり出くわした。


雨は期待通り昼前に上がってくれた。このまま明日の夕方までもってくれる事を再度祈ろう。
土手の下で『アメリカフウロ』の角果が思いっきり反り返っていた。
板バネの様に反り返っている部分は始めまっすぐ下にくっ付いているが熟すと1個ずつ上に反り返る、その反動を利用して種を遠くに弾き飛ばす。分布を広げる為の知恵だろう!
これは「フウロソウ属」の特徴で、在来種の「ゲンノショウコ」も全く同じ仕組みで種を弾き飛ばす。日本産の「フウロソウ属」の種は表面が滑らかだが、「アメリカフウロ」の種は網目状の隆起した模様がある。
土手の斜面に上がってきた「キジ♂」とばったり出くわした。

タグ :自然
2011年06月17日 Posted by 松ぽっくり at 16:56 │Comments(0) │フィールド
タンポポモドキ
ブタナ
背の高いタンポポを思わせる『ブタナ』、一番最初に草刈りの済んだ土手の上で早くも小群落を作り花を咲かせている。
一度やそこら刈られてもたちまち復活する逞しさは、熱帯の高地を含めてほぼ世界中に帰化していると云う事がうなずける。
1930年代に札幌で見つかった時は「タンポポモドキ」と命名されたとか、その名は現在別名として使われている。
雨は思いの外早く、昼前にはパラパラし始めた。願わくば明日の昼頃までに上がってくれる事を祈りたい。

背の高いタンポポを思わせる『ブタナ』、一番最初に草刈りの済んだ土手の上で早くも小群落を作り花を咲かせている。
一度やそこら刈られてもたちまち復活する逞しさは、熱帯の高地を含めてほぼ世界中に帰化していると云う事がうなずける。
1930年代に札幌で見つかった時は「タンポポモドキ」と命名されたとか、その名は現在別名として使われている。
雨は思いの外早く、昼前にはパラパラし始めた。願わくば明日の昼頃までに上がってくれる事を祈りたい。
タグ :植物
2011年06月16日 Posted by 松ぽっくり at 17:48 │Comments(0) │フィールド
南に多く
クマノミズキ
小さな花の集まり
二日程ご無沙汰している間に、土手の草刈りはほぼ完了していた。昨年は部分的に残した所もあったが、今年は一部の隙も無く刈られている。
そんな中、河原の「オニグルミ」の実は大分大きくなり、その「オニグルミ」と「エノキ」に挟まれている『クマノミズキ』が小さな花のかたまりを枝いっぱいに広げて満開です。
名前の「熊野水木」は三重県熊野に産すると云う事で付けられたが、ほぼ全国的に見られる。ただ量的には南に多く雪国には少ない。
花は蜜を多く含み、黒っぽい「蜂蜜」が採れると云う。
お地蔵さん下の藪、ここは草刈り除外地らしく毎年刈られる事は無い。そこの「ヤブジラミ」の小さな花に「ツバメシジミ」夏型♀が訪れていた。

小さな花の集まり

二日程ご無沙汰している間に、土手の草刈りはほぼ完了していた。昨年は部分的に残した所もあったが、今年は一部の隙も無く刈られている。
そんな中、河原の「オニグルミ」の実は大分大きくなり、その「オニグルミ」と「エノキ」に挟まれている『クマノミズキ』が小さな花のかたまりを枝いっぱいに広げて満開です。
名前の「熊野水木」は三重県熊野に産すると云う事で付けられたが、ほぼ全国的に見られる。ただ量的には南に多く雪国には少ない。
花は蜜を多く含み、黒っぽい「蜂蜜」が採れると云う。
お地蔵さん下の藪、ここは草刈り除外地らしく毎年刈られる事は無い。そこの「ヤブジラミ」の小さな花に「ツバメシジミ」夏型♀が訪れていた。

タグ :自然
2011年06月15日 Posted by 松ぽっくり at 16:43 │Comments(0) │フィールド
引けを取らない
テリハノイバラ

イバラの苑へ踏み込むのをためらっていたが『テリハノイバラ』がそろそろ盛りを過ぎそうなので意を決して進入。
開花直後の花を探している内に案の定、指先とムコウズネに刺の報復を受けた。
海岸や河原など簡単に見られる花だが「ノイバラ」に比べ一回り大きな白い花に多数の黄色い雄しべ、小さくツヤの有る端正な葉。園芸種に引けを取らない清楚な美しさを持っている。
今年の梅雨はシトシトと降り続かないので助かる。


イバラの苑へ踏み込むのをためらっていたが『テリハノイバラ』がそろそろ盛りを過ぎそうなので意を決して進入。
開花直後の花を探している内に案の定、指先とムコウズネに刺の報復を受けた。
海岸や河原など簡単に見られる花だが「ノイバラ」に比べ一回り大きな白い花に多数の黄色い雄しべ、小さくツヤの有る端正な葉。園芸種に引けを取らない清楚な美しさを持っている。
今年の梅雨はシトシトと降り続かないので助かる。
タグ :植物
2011年06月12日 Posted by 松ぽっくり at 18:16 │Comments(0) │フィールド
オレンジ色の
ハゼノキ
オレンジ色の葯が目立つ雄花
湿度が高いとみえてジットリと暑い。土手の草刈りも佳境に入ってきて、咲き始めたばかりの「ウツボグサ」も開花後4日であっさりゴミと化した。
お地蔵さんの上の疎林縁、さすがにここまでは手が回っていない。『ハゼノキ』が黄緑色の小さな花を泡のように盛り上げていた。
ハゼノキは雌雄別株でこの木は雄木、近づくとオレンジ色の葯が目立つ。この比較的地味な花に対し秋の紅葉は美しい。県内、土肥町の日陰山はハゼの紅葉で知られている。
中国、ヒマラヤが原産とされ、別名が「リュウキュウハゼ」や「サツマウルシ」、これは伝播経路を示すものと云われている。

オレンジ色の葯が目立つ雄花

湿度が高いとみえてジットリと暑い。土手の草刈りも佳境に入ってきて、咲き始めたばかりの「ウツボグサ」も開花後4日であっさりゴミと化した。
お地蔵さんの上の疎林縁、さすがにここまでは手が回っていない。『ハゼノキ』が黄緑色の小さな花を泡のように盛り上げていた。
ハゼノキは雌雄別株でこの木は雄木、近づくとオレンジ色の葯が目立つ。この比較的地味な花に対し秋の紅葉は美しい。県内、土肥町の日陰山はハゼの紅葉で知られている。
中国、ヒマラヤが原産とされ、別名が「リュウキュウハゼ」や「サツマウルシ」、これは伝播経路を示すものと云われている。
タグ :植物
2011年06月10日 Posted by 松ぽっくり at 17:48 │Comments(0) │フィールド
無防備で
ネジバナ

広場や土手に『ネジバナ』が咲きだした。この花を見ると暑い夏が蘇る。過ぎた日のボール遊びの最中、汗まみれで倒れこんだ鼻先にネジれていた記憶。
ラン科の植物は一般的に日蔭を好むものが多い中、この花は炎天下に無防備で立っています。ちょっと変わったラン科ですが、「ひねくれもの」とは口が裂けても言いません!
野の花の愛らしさランキングでは上位に入れたい花です。
まだ梅雨に入ったばかりで、本格的夏はもう少し先のはずだが気温はすでにそれに近いものがある。


広場や土手に『ネジバナ』が咲きだした。この花を見ると暑い夏が蘇る。過ぎた日のボール遊びの最中、汗まみれで倒れこんだ鼻先にネジれていた記憶。
ラン科の植物は一般的に日蔭を好むものが多い中、この花は炎天下に無防備で立っています。ちょっと変わったラン科ですが、「ひねくれもの」とは口が裂けても言いません!
野の花の愛らしさランキングでは上位に入れたい花です。
まだ梅雨に入ったばかりで、本格的夏はもう少し先のはずだが気温はすでにそれに近いものがある。
タグ :植物
2011年06月09日 Posted by 松ぽっくり at 17:42 │Comments(0) │フィールド
太く短い
ウツボグサ

チガヤの穂はほうけて膨らみ、風が小さな種の付いた綿毛をあたり一帯にまき散らして道端には綿ぼこりの様に積もっています。
そんなチガヤに埋もれるように『ウツボグサ』のトップバッターが姿を見せました。
花の咲く前はその気配さえ感じさせませんが、鮮やかな青紫色の花が咲くとよく目立ちます。
太く短い穂に唇型をした花が下から上に順に咲いていきます。
夏、花が終わると穂はカサカサと乾燥して黒っぽくなるので「夏枯草(カコソウ)」とも呼ばれます。
例年なら5月の内に姿を見せるので今年は少し遅れた事になります。


チガヤの穂はほうけて膨らみ、風が小さな種の付いた綿毛をあたり一帯にまき散らして道端には綿ぼこりの様に積もっています。
そんなチガヤに埋もれるように『ウツボグサ』のトップバッターが姿を見せました。
花の咲く前はその気配さえ感じさせませんが、鮮やかな青紫色の花が咲くとよく目立ちます。
太く短い穂に唇型をした花が下から上に順に咲いていきます。
夏、花が終わると穂はカサカサと乾燥して黒っぽくなるので「夏枯草(カコソウ)」とも呼ばれます。
例年なら5月の内に姿を見せるので今年は少し遅れた事になります。
タグ :植物
2011年06月07日 Posted by 松ぽっくり at 16:35 │Comments(0) │フィールド
内陸の県からは
シロバナマンテマ

雨の心配は無く、気温も上がって夏日。
柳の下の草むらで『シロバナマンテマ』が咲き始めていた。シロバナと云う名前が付いているが真っ白いものはあまり見かけない。色の濃い薄いは有るが大抵薄紅色の花が多い。
ヨーロッパの原産で北海道から九州まで帰化している様ですが内陸の県からは報告が無いとの事です。
県内では海岸や河原、疎林、道路の中央分離帯、公園、と至る所で見かけ、最近テレトリーを広げているように感じる。萼筒の長い毛がよく目立つ。
前回取り上げたときは「マンテマ」として載せましたが「シロバナマンテマ」が正解のようです。


雨の心配は無く、気温も上がって夏日。
柳の下の草むらで『シロバナマンテマ』が咲き始めていた。シロバナと云う名前が付いているが真っ白いものはあまり見かけない。色の濃い薄いは有るが大抵薄紅色の花が多い。
ヨーロッパの原産で北海道から九州まで帰化している様ですが内陸の県からは報告が無いとの事です。
県内では海岸や河原、疎林、道路の中央分離帯、公園、と至る所で見かけ、最近テレトリーを広げているように感じる。萼筒の長い毛がよく目立つ。
前回取り上げたときは「マンテマ」として載せましたが「シロバナマンテマ」が正解のようです。
タグ :植物
2011年06月06日 Posted by 松ぽっくり at 17:40 │Comments(0) │フィールド
丸まって
ウリノキ
思いの他雲は厚く、らしい空模様でしたが少し山道を走って来ました。
緑は一段とボリュームを増して、「ウツギ」や「テイカカズラ」の花に混じって「マタタビ」の白く染まった葉も見られる様になって来ました。
林の中では『ウリノキ』の花が咲き始めています。白い棒状の蕾は開くと花びらはゼンマイの様にクルクルと丸まってしまい、黄色い雄しべが丸見えになります。
葉の形が瓜の葉に似ていると云う事でこの名が付きました。この仲間は1科1属20種程の小さな科です。
明日は「芒種」稲などのノギの有る穀物の種まきをし、カマキリや蛍が現れ始め、梅の実が黄ばみ始める頃。との事ですが現代の農作業は1ヶ月程早くなっている様です。

思いの他雲は厚く、らしい空模様でしたが少し山道を走って来ました。
緑は一段とボリュームを増して、「ウツギ」や「テイカカズラ」の花に混じって「マタタビ」の白く染まった葉も見られる様になって来ました。
林の中では『ウリノキ』の花が咲き始めています。白い棒状の蕾は開くと花びらはゼンマイの様にクルクルと丸まってしまい、黄色い雄しべが丸見えになります。
葉の形が瓜の葉に似ていると云う事でこの名が付きました。この仲間は1科1属20種程の小さな科です。
明日は「芒種」稲などのノギの有る穀物の種まきをし、カマキリや蛍が現れ始め、梅の実が黄ばみ始める頃。との事ですが現代の農作業は1ヶ月程早くなっている様です。
タグ :植物
2011年06月05日 Posted by 松ぽっくり at 23:25 │Comments(0) │下見
かなりの差が
ウツギ
ウツギの花は平開しない
竹林の縁で『ウツギ』が咲いています。河原に1本有る「ウツギ」も木全体を白くしています。
1ヶ月程前に林道の入り口付近で満開だったので、場所によって開花の時期にかなりの差がでるようだ。
ウツギの名は枝を切ると芯が中空になっているので「空木」の名が付きました。
河原では相当数の関係者が集まり大がかりな水防訓練?が実施されており、土手は一部通行が止められていた。そんな中、水門の池の奥ではカメが甲羅干しをしている。
近づくと気配に気づいたとみえ首を伸ばした、その顔には遠目にも赤い筋模様が見てとれる。「ミシシッピーアカミミガメ」のようだ。「ミドリガメ」の通称でペットとして人気の有るカメはこの「子ガメ」です。誰かが飼育に飽きて放したものでしょうか?在来種が圧迫されなければいいのですが・・・・。
ミシシッピーアカミミガメ

ウツギの花は平開しない

竹林の縁で『ウツギ』が咲いています。河原に1本有る「ウツギ」も木全体を白くしています。
1ヶ月程前に林道の入り口付近で満開だったので、場所によって開花の時期にかなりの差がでるようだ。
ウツギの名は枝を切ると芯が中空になっているので「空木」の名が付きました。
河原では相当数の関係者が集まり大がかりな水防訓練?が実施されており、土手は一部通行が止められていた。そんな中、水門の池の奥ではカメが甲羅干しをしている。
近づくと気配に気づいたとみえ首を伸ばした、その顔には遠目にも赤い筋模様が見てとれる。「ミシシッピーアカミミガメ」のようだ。「ミドリガメ」の通称でペットとして人気の有るカメはこの「子ガメ」です。誰かが飼育に飽きて放したものでしょうか?在来種が圧迫されなければいいのですが・・・・。
ミシシッピーアカミミガメ

タグ :自然