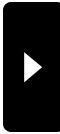オレンジ
ヤブカンゾウ

水路のふち、ヤブカラシに絡まれながら『ヤブカンゾウ』が頑張っています。
ほぼ緑一色の草地で八重咲きの鮮やかなオレンジは一目で存在を教えてくれます。
万葉では「ワスレグサ」と呼び、この花を着物の紐に付けておくと、いやな事を忘れさせてくれると云う。
遠くで小さく雷が鳴って一雨あり、ひと時の涼を残していきました。

水路のふち、ヤブカラシに絡まれながら『ヤブカンゾウ』が頑張っています。
ほぼ緑一色の草地で八重咲きの鮮やかなオレンジは一目で存在を教えてくれます。
万葉では「ワスレグサ」と呼び、この花を着物の紐に付けておくと、いやな事を忘れさせてくれると云う。
遠くで小さく雷が鳴って一雨あり、ひと時の涼を残していきました。
タグ :植物
2010年06月30日 Posted by 松ぽっくり at 23:04 │Comments(0) │フィールド
倒れるように
クマツヅラ

葉は不規則に切れ込みます


空地の道端に倒れるように『クマツヅラ』が小さな花を付けていました。
最近は同じ「クマツヅラ科」の外来種「アレチハナガサ」に押されてか、見る機会が減った様に感じます。
細くて長い花序をムチに見立てて漢名では「馬鞭草」と呼び、葉を生薬として利用します。
それにしても暑い日でした。予報の34℃まではいきませんでしたが、30℃はゆうに超えました。

葉は不規則に切れ込みます


空地の道端に倒れるように『クマツヅラ』が小さな花を付けていました。
最近は同じ「クマツヅラ科」の外来種「アレチハナガサ」に押されてか、見る機会が減った様に感じます。
細くて長い花序をムチに見立てて漢名では「馬鞭草」と呼び、葉を生薬として利用します。
それにしても暑い日でした。予報の34℃まではいきませんでしたが、30℃はゆうに超えました。
タグ :植物
2010年06月28日 Posted by 松ぽっくり at 23:32 │Comments(0) │フィールド
俗説
ノウゼンカズラ

ついこの間まで「ヒルガオ」が絡んでいた道端の藪、今日は一変して『ノウゼンカズラ』が占有し、沢山の蕾を付けて花も咲き始めていました。
花の色が派手すぎる為、昔の日本人にはあまり好まれなかったようで「花のにおいを嗅ぐと脳がおかしくなる」とか「花の露が目に入れば失明する」などの俗説も生まれました。
現代ではその花の色、大きさ、花の数などから夏の代表的な木の花とされています。

ついこの間まで「ヒルガオ」が絡んでいた道端の藪、今日は一変して『ノウゼンカズラ』が占有し、沢山の蕾を付けて花も咲き始めていました。
花の色が派手すぎる為、昔の日本人にはあまり好まれなかったようで「花のにおいを嗅ぐと脳がおかしくなる」とか「花の露が目に入れば失明する」などの俗説も生まれました。
現代ではその花の色、大きさ、花の数などから夏の代表的な木の花とされています。
タグ :植物
2010年06月27日 Posted by 松ぽっくり at 17:42 │Comments(0) │近所
吸水
アオスジアゲハ

近所の濡れたコンクリの上で『アオスジアゲハ』が吸水していました。 ちなみにこの吸水行動は本種に限らず何故か新鮮な♂ばかりだと云われています??
クスノキ科のクスノキやヤブニッケイ、タブノキなどが食樹で、市街地でもクスノキの周りを飛んでいるのを時々見かけます。飛翔は直線的でかなり敏速です。
アゲハチョウの中では少し小ぶりですが、色、姿、スピード、とも切れのいい蝶です。
目を凝らさないと確認出来ない程の雨が降ったりやんだり、それらしい空模様です。

近所の濡れたコンクリの上で『アオスジアゲハ』が吸水していました。 ちなみにこの吸水行動は本種に限らず何故か新鮮な♂ばかりだと云われています??
クスノキ科のクスノキやヤブニッケイ、タブノキなどが食樹で、市街地でもクスノキの周りを飛んでいるのを時々見かけます。飛翔は直線的でかなり敏速です。
アゲハチョウの中では少し小ぶりですが、色、姿、スピード、とも切れのいい蝶です。
目を凝らさないと確認出来ない程の雨が降ったりやんだり、それらしい空模様です。
タグ :自然
2010年06月26日 Posted by 松ぽっくり at 18:03 │Comments(0) │近所
正木
マサキ
畑の隅の『マサキ』が満開になっていた。小さな地味な花は同じニシキギ科ニシキギ属と云う事もあって「マユミ」の花によく似ている。
以前はよく生垣に使われたが最近はあまり使われなくなった。
漢字は「正木」あるいは「柾」をあてるが由来はいまひとつはっきりしないようだ。
秋から冬にかけ、熟した果実は裂開し中から橙赤色の種子がのぞいて中々きれいです。
花は多少蜜を分泌するらしく、アリが訪れていた


畑の隅の『マサキ』が満開になっていた。小さな地味な花は同じニシキギ科ニシキギ属と云う事もあって「マユミ」の花によく似ている。
以前はよく生垣に使われたが最近はあまり使われなくなった。
漢字は「正木」あるいは「柾」をあてるが由来はいまひとつはっきりしないようだ。
秋から冬にかけ、熟した果実は裂開し中から橙赤色の種子がのぞいて中々きれいです。
花は多少蜜を分泌するらしく、アリが訪れていた

タグ :植物
2010年06月25日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(0) │フィールド
傷ついて
ウツボグサ
梅雨の隙間としては湿度が低く、すこぶる気持ちの良い日です。
ママチャリでフィールドを風に吹かれていると何処までも行きたい気持ちになります。
斜面の中ほどに『ウツボグサ』が一本立っていました。
葉や茎が大分傷ついています。恐らく草刈りの時、刈られるのだけは免れたが踏みつけにあったのでしょう。
それでもいつもより多めの花を付けて、野生の根性を見せています。


梅雨の隙間としては湿度が低く、すこぶる気持ちの良い日です。
ママチャリでフィールドを風に吹かれていると何処までも行きたい気持ちになります。

斜面の中ほどに『ウツボグサ』が一本立っていました。
葉や茎が大分傷ついています。恐らく草刈りの時、刈られるのだけは免れたが踏みつけにあったのでしょう。

それでもいつもより多めの花を付けて、野生の根性を見せています。


タグ :植物
2010年06月24日 Posted by 松ぽっくり at 21:07 │Comments(0) │フィールド
光の加減で
アオカミキリ
午前中どしゃぶりの雨は昼過ぎにあっさりと上がり、4時頃には日も差して来ました。
中学校の横「タデ科」の不明種の葉に金属光沢のきれいなカミキリが一匹、じっとしていました。
帰宅後確認の結果『アオカミキリ』と判明。虫屋さんの間では割と人気のカミキリの様で、このカミキリを見てから虫屋さんになった方もあるようです。確かに光の加減で変化する装いは中々のものでした。
明日は前線が南下して梅雨の晴れ間がのぞくらしい。

午前中どしゃぶりの雨は昼過ぎにあっさりと上がり、4時頃には日も差して来ました。
中学校の横「タデ科」の不明種の葉に金属光沢のきれいなカミキリが一匹、じっとしていました。
帰宅後確認の結果『アオカミキリ』と判明。虫屋さんの間では割と人気のカミキリの様で、このカミキリを見てから虫屋さんになった方もあるようです。確かに光の加減で変化する装いは中々のものでした。

明日は前線が南下して梅雨の晴れ間がのぞくらしい。
タグ :自然
2010年06月23日 Posted by 松ぽっくり at 23:03 │Comments(0) │フィールド
多肉の
マルバマンネングサ
土手の上に「ウスバキトンボ」が漂っています、今季初見。「夏至」も過ぎて季節は着実に流れているようです。
水門の池のふち『マルバマンネングサ』が咲いていました。昨年より若干遅いような気がします。
多肉質の厚い葉をもつこの草は、他の植物が暮らせない様な岩の僅かな隙間に根を差し込んで競合を避けた生活をしています。石垣の上などでも時々見かけます。
マンネングサの仲間の中では葉が丸いので「丸葉万年草」となったようです。
よく見るとガク片まで多肉である事が分かります。


土手の上に「ウスバキトンボ」が漂っています、今季初見。「夏至」も過ぎて季節は着実に流れているようです。
水門の池のふち『マルバマンネングサ』が咲いていました。昨年より若干遅いような気がします。
多肉質の厚い葉をもつこの草は、他の植物が暮らせない様な岩の僅かな隙間に根を差し込んで競合を避けた生活をしています。石垣の上などでも時々見かけます。
マンネングサの仲間の中では葉が丸いので「丸葉万年草」となったようです。
よく見るとガク片まで多肉である事が分かります。

タグ :植物
2010年06月22日 Posted by 松ぽっくり at 17:04 │Comments(3) │フィールド
縮れたヒレ
コヒルガオ

花柄上部の縮れたヒレが確認できます
放置された茶の木に『コヒルガオ』が絡んでいました。
先日の「ヒルガオ」の時にも書きましたが、中間的のものが多く識別に悩むのですが、この個体は「ヒルガオ」より少し小さめの花、先がとがって基部左右の耳がほぼ直角に張り出した葉。花柄の上部に縮れた「ヒレ」が有る事。これらの点から「コヒルガオ」としました。
近所の道端に植わっている「ヤマモモ」の実が大分熟して来ましたが誰も採ってあげないので、みんな落ちてしまい道路を汚します。


花柄上部の縮れたヒレが確認できます

放置された茶の木に『コヒルガオ』が絡んでいました。
先日の「ヒルガオ」の時にも書きましたが、中間的のものが多く識別に悩むのですが、この個体は「ヒルガオ」より少し小さめの花、先がとがって基部左右の耳がほぼ直角に張り出した葉。花柄の上部に縮れた「ヒレ」が有る事。これらの点から「コヒルガオ」としました。

近所の道端に植わっている「ヤマモモ」の実が大分熟して来ましたが誰も採ってあげないので、みんな落ちてしまい道路を汚します。


タグ :植物
2010年06月21日 Posted by 松ぽっくり at 18:00 │Comments(0) │フィールド
示し合わせたように
アカメガシワ雌花 同雄花


この所「トウダイグサ科」の木が示し合わせたように開花している「アブラギリ」「シラキ」そして『アカメガシワ』と、雌雄別々の花を見せている。
アカメガシワは万葉集に「久木」の名でも載っているが、材も軟らかく樹齢の久しい巨木にはならない。
「所により雷雨」と云う予報の「所」に選ばれたようで午後雷鳴と共に一雨有り、フィールドは若干涼しくなった気がする。


この所「トウダイグサ科」の木が示し合わせたように開花している「アブラギリ」「シラキ」そして『アカメガシワ』と、雌雄別々の花を見せている。
アカメガシワは万葉集に「久木」の名でも載っているが、材も軟らかく樹齢の久しい巨木にはならない。
「所により雷雨」と云う予報の「所」に選ばれたようで午後雷鳴と共に一雨有り、フィールドは若干涼しくなった気がする。
タグ :植物
2010年06月20日 Posted by 松ぽっくり at 17:13 │Comments(0) │フィールド
至福の
アブラギリ

奇跡の様な一日だった。昨夜の激しい雨は早朝に上がり大雨警報も解除された!
空は次第に明るくなり、私達が集合する12時には青空も広がった、昨夜の降り方を思うと信じられない激変です。
そして溢れんばかりに咲いていた「アブラギリ」の花。路が白くなるほど落ちているその花を見て感嘆の声が上がった。会をセットした者にとって至福の時だ。
湿度が高く、ジットリした暑さも山路の風が癒してくれた。

奇跡の様な一日だった。昨夜の激しい雨は早朝に上がり大雨警報も解除された!
空は次第に明るくなり、私達が集合する12時には青空も広がった、昨夜の降り方を思うと信じられない激変です。
そして溢れんばかりに咲いていた「アブラギリ」の花。路が白くなるほど落ちているその花を見て感嘆の声が上がった。会をセットした者にとって至福の時だ。
湿度が高く、ジットリした暑さも山路の風が癒してくれた。
タグ :植物
2010年06月19日 Posted by 松ぽっくり at 23:47 │Comments(2) │観察会
俗名を
ブタナ
草刈りが済んだ後、一番先に斜面の一角を占有して黄色く彩ったのは『ブタナ』でした。
この花はヨーロッパが故郷。フランスでの俗名「ブタのサラダ」をそのまま訳して
「豚菜」となったようです。
タンポポに似ていますが背が高く、茎が途中で枝分かれしています。
花はそろそろピークを超えようとしています。
午前中に用事と徘徊を済ませて正解でした。外はまとまった雨が降っています。

草刈りが済んだ後、一番先に斜面の一角を占有して黄色く彩ったのは『ブタナ』でした。
この花はヨーロッパが故郷。フランスでの俗名「ブタのサラダ」をそのまま訳して
「豚菜」となったようです。
タンポポに似ていますが背が高く、茎が途中で枝分かれしています。
花はそろそろピークを超えようとしています。
午前中に用事と徘徊を済ませて正解でした。外はまとまった雨が降っています。

タグ :植物
2010年06月18日 Posted by 松ぽっくり at 16:43 │Comments(0) │フィールド
全部結実?
ギンヨウアカシア
3月に木全体が黄色に見える程、沢山の花を付けていた『ギンヨウアカシア』
あの時の花が全部結実したかの様にこれまた沢山の豆果をぶら下げています。
サヤがきれいに割れて中の豆がしっかり確認出来ます。
引き続き晴れて暑い一日でした。予報に寄ると明日からは雲と傘のマークがずらっと並んで、雨の季節が本格化するらしい。

3月に木全体が黄色に見える程、沢山の花を付けていた『ギンヨウアカシア』
あの時の花が全部結実したかの様にこれまた沢山の豆果をぶら下げています。
サヤがきれいに割れて中の豆がしっかり確認出来ます。
引き続き晴れて暑い一日でした。予報に寄ると明日からは雲と傘のマークがずらっと並んで、雨の季節が本格化するらしい。
タグ :植物
2010年06月17日 Posted by 松ぽっくり at 23:02 │Comments(0) │フィールド
垂直尾翼が
キマダラセセリ

雨が上がって急激に天気は回復したが湿度が高く相当暑かった。夜になっても部屋の温度計は26℃を指している。
気温が上がったせいか、蝶や蛾の姿が目に付く事が多くなった。
シロツメクサの小さな花に一つづつ口吻を差し込んで蜜を吸っている『キマダラセセリ』がいました。
前翅を半開し後翅を全開にして止まっているこのチョウの姿を見るといつも、垂直尾翼が2枚のジェット機が思い浮かびます(飛び方も敏速です)
その先の草陰ではススキにつかまって『カノコガ』が休んでいます。鹿子ふうの水玉模様の可愛らしい蛾です。


雨が上がって急激に天気は回復したが湿度が高く相当暑かった。夜になっても部屋の温度計は26℃を指している。
気温が上がったせいか、蝶や蛾の姿が目に付く事が多くなった。
シロツメクサの小さな花に一つづつ口吻を差し込んで蜜を吸っている『キマダラセセリ』がいました。
前翅を半開し後翅を全開にして止まっているこのチョウの姿を見るといつも、垂直尾翼が2枚のジェット機が思い浮かびます(飛び方も敏速です)
その先の草陰ではススキにつかまって『カノコガ』が休んでいます。鹿子ふうの水玉模様の可愛らしい蛾です。

タグ :自然
2010年06月16日 Posted by 松ぽっくり at 22:30 │Comments(0) │フィールド
怠りない
ドクウツギ ツルウメモドキ


河原の『ドクウツギ』の実が深紅に色付いて目を引きます。これから徐々に成熟していき秋口には完熟して黒紫色になります。
その「ドクウツギ」に絡みついた『ツルウメモドキ』の丸い実もその存在がわかる様になっていました。
天気が不順だ、異常だ、と云ってるうちに、植物は子孫を送り出す準備に怠りが無い。
今日は雨を覚悟していたが朝方は青空ものぞく始末、夕方までしっかりもってくれた。


河原の『ドクウツギ』の実が深紅に色付いて目を引きます。これから徐々に成熟していき秋口には完熟して黒紫色になります。
その「ドクウツギ」に絡みついた『ツルウメモドキ』の丸い実もその存在がわかる様になっていました。
天気が不順だ、異常だ、と云ってるうちに、植物は子孫を送り出す準備に怠りが無い。
今日は雨を覚悟していたが朝方は青空ものぞく始末、夕方までしっかりもってくれた。
タグ :植物
2010年06月15日 Posted by 松ぽっくり at 17:13 │Comments(0) │フィールド
濡れて
サフランモドキ

朝から降ったりやんだり、それらしい空模様になって来ました。
土手の下の道端に『サフランモドキ』がひとつ濡れています。
ヒガンバナ科のこの花は江戸の末期に渡来して鑑賞用に植えられ今でも庭などで見かけますが、暖地などには野生化もかなり進んでいるようです。
渡来当時は間違えて「サフラン」と呼んでいたものを後に「サフランモドキ」と改名されました。ちなみに「サフラン」はアヤメ科です。
ビワの実が色付いて、桃の実も大分大きくなってきました。

朝から降ったりやんだり、それらしい空模様になって来ました。
土手の下の道端に『サフランモドキ』がひとつ濡れています。
ヒガンバナ科のこの花は江戸の末期に渡来して鑑賞用に植えられ今でも庭などで見かけますが、暖地などには野生化もかなり進んでいるようです。
渡来当時は間違えて「サフラン」と呼んでいたものを後に「サフランモドキ」と改名されました。ちなみに「サフラン」はアヤメ科です。
ビワの実が色付いて、桃の実も大分大きくなってきました。

タグ :植物
2010年06月14日 Posted by 松ぽっくり at 17:56 │Comments(2) │フィールド
道ばたの
ヒルガオ

道端の小藪に『ヒルガオ』がきれいに3つ並んで咲いていて足を止めさせられました。
「コヒルガオ」とよく似ていて、中間型もあるので紛らわしいのですが、包葉の先がとがらない、花柄の上部に縮れたヒレが無い点で『ヒルガオ』とさせてもらいました。
「ヒルガオ」は主に地下茎で増え、めったに結実しません。サツマイモもヒルガオ科で似た花が咲きます。
予想に反して雨は日中一杯もってくれました。

道端の小藪に『ヒルガオ』がきれいに3つ並んで咲いていて足を止めさせられました。
「コヒルガオ」とよく似ていて、中間型もあるので紛らわしいのですが、包葉の先がとがらない、花柄の上部に縮れたヒレが無い点で『ヒルガオ』とさせてもらいました。
「ヒルガオ」は主に地下茎で増え、めったに結実しません。サツマイモもヒルガオ科で似た花が咲きます。
予想に反して雨は日中一杯もってくれました。
タグ :植物
2010年06月13日 Posted by 松ぽっくり at 22:30 │Comments(0) │近所
自生か?
アブラギリ

梅雨入りがそこまで迫って来た様なので、その前に近くの山道を少し歩いて来ました。
そろそろ「ウツギ」もピークを過ぎようとしています。
「アオスジアゲハ」や「オナガアゲハ」など、蝶たちの動きは活発でした。
路に2㌢程の白い花が沢山落ちていました、見上げると『アブラギリ』のようだ、葉の感じはちょっと「アカメガシワ」に似ているが、花は全く異なる。
果実から桐油を採るために栽培される事が多く、本来の自生か疑われている種です。
梅雨入り前の土曜日とあって山道は結構な人出、誰も思う事は一緒のようだ。

梅雨入りがそこまで迫って来た様なので、その前に近くの山道を少し歩いて来ました。
そろそろ「ウツギ」もピークを過ぎようとしています。
「アオスジアゲハ」や「オナガアゲハ」など、蝶たちの動きは活発でした。
路に2㌢程の白い花が沢山落ちていました、見上げると『アブラギリ』のようだ、葉の感じはちょっと「アカメガシワ」に似ているが、花は全く異なる。
果実から桐油を採るために栽培される事が多く、本来の自生か疑われている種です。
梅雨入り前の土曜日とあって山道は結構な人出、誰も思う事は一緒のようだ。

タグ :植物
2010年06月12日 Posted by 松ぽっくり at 23:26 │Comments(2) │下見
這いまわって
テリハノイバラ


ノイバラから大分遅れて『テリハノイバラ』が盛りを迎え、防災用のブロックを被いつくして白い大き目の花をいい具合に配置しています。
そして草刈りの手の及ばない河原にも蔓をのばしひたすら這いまわって白い花を付けているのが遠目にも分かる。
分布は日当たりの良い海岸や河原などに多いが、標高1,000mを超すブナ帯でも見る事が有る。


ノイバラから大分遅れて『テリハノイバラ』が盛りを迎え、防災用のブロックを被いつくして白い大き目の花をいい具合に配置しています。
そして草刈りの手の及ばない河原にも蔓をのばしひたすら這いまわって白い花を付けているのが遠目にも分かる。
分布は日当たりの良い海岸や河原などに多いが、標高1,000mを超すブナ帯でも見る事が有る。
タグ :植物
2010年06月11日 Posted by 松ぽっくり at 16:36 │Comments(0) │フィールド
方言名
ホタルブクロ
近所の土手『ホタルブクロ』と出会いました。イネ科の背の高い草の中、競うように背をのばし白い花をぶら下げていました。
昔からよく親しまれた草で全国に様々な方言名が有ります。「チョウチンバナ」「ツリガネソウ」「トックリバナ」「アメフリバナ」「ポンポンバナ」他
県内にも「キツネノチョーチン」「キツネノションベンオケ」などが有るようです。
梅雨入り前の貴重な晴れ間と ラジオでは有効活用をすすめている。
ラジオでは有効活用をすすめている。
フィールドは結構気温が上がり、長袖のシャツがジャマに感じます。

近所の土手『ホタルブクロ』と出会いました。イネ科の背の高い草の中、競うように背をのばし白い花をぶら下げていました。
昔からよく親しまれた草で全国に様々な方言名が有ります。「チョウチンバナ」「ツリガネソウ」「トックリバナ」「アメフリバナ」「ポンポンバナ」他
県内にも「キツネノチョーチン」「キツネノションベンオケ」などが有るようです。

梅雨入り前の貴重な晴れ間と
 ラジオでは有効活用をすすめている。
ラジオでは有効活用をすすめている。フィールドは結構気温が上がり、長袖のシャツがジャマに感じます。

タグ :植物