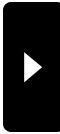独特な
ヤブツルアズキ

花の中央でカーブしている筒状の花弁の中にオシベ、メシベが入っています。
雨が降らないので、土手下の茶畑ではスプリンクラーがフル回転、水路から水をくみ上げるモーターがあちこちで唸っています。
そんな茶畑の隅で『ヤブツルアズキ』が電柱に絡みついて花を咲かせていました。暑い太陽の下で独特な形状の黄色がひと際鮮やかでした。
8月は今日で終わりだが暑さは終わりそうにない。山の上には夏の雲が垂直に湧き上がっています。

花の中央でカーブしている筒状の花弁の中にオシベ、メシベが入っています。

雨が降らないので、土手下の茶畑ではスプリンクラーがフル回転、水路から水をくみ上げるモーターがあちこちで唸っています。
そんな茶畑の隅で『ヤブツルアズキ』が電柱に絡みついて花を咲かせていました。暑い太陽の下で独特な形状の黄色がひと際鮮やかでした。
8月は今日で終わりだが暑さは終わりそうにない。山の上には夏の雲が垂直に湧き上がっています。

タグ :植物
2010年08月31日 Posted by 松ぽっくり at 19:02 │Comments(0) │フィールド
天狗のような
アレチヌスビトハギ


水門の池付近の土手斜面では、昨年に比べ更にテレトリーを広げた『アレチヌスビトハギ』が咲き始めていました。去年より若干遅い気がします。
一面を埋め尽くすほどの株数なので、一斉に花が咲けばかなり見応えがあると思うのですが、そこは雑草と呼ばれる所以でしょうか、いっぺんには咲かず、それぞれが勝手気ままにポツリポツリと咲くので今ひとつ訴えかけるものが足りません(果実になった時の疎ましさは絶大なのですが・・)
ただ、近づいてよく見ると天狗の様な面白い顔をしています。


水門の池付近の土手斜面では、昨年に比べ更にテレトリーを広げた『アレチヌスビトハギ』が咲き始めていました。去年より若干遅い気がします。
一面を埋め尽くすほどの株数なので、一斉に花が咲けばかなり見応えがあると思うのですが、そこは雑草と呼ばれる所以でしょうか、いっぺんには咲かず、それぞれが勝手気ままにポツリポツリと咲くので今ひとつ訴えかけるものが足りません(果実になった時の疎ましさは絶大なのですが・・)

ただ、近づいてよく見ると天狗の様な面白い顔をしています。

タグ :植物
2010年08月30日 Posted by 松ぽっくり at 21:22 │Comments(0) │フィールド
端正な
キキョウ

今日はKさんに案内をお願いして県西部、蛇紋岩地帯へ草花を見に行って来ました。
目的地までは東名を使って約1時間半で到着、歩き始めるとすぐに初見の「アイナエ」が小さな小さな白い花を付けて迎えてくれました。どんな時でも初対面はテンションが上がります。相変わらずの暑さをしばし忘れさせてくれました。
「コガンピ」の花などを愛でながらマイフィールドとはかなり異なる植生に一喜一憂しながら進むと『キキョウ』が端正な花を見せています。家庭のお庭ではよく見かける「キキョウ」ですが野生のものは随分と久しぶりです。一同感激!
その後も初見の「オオヒキヨモギ」にもお目に掛かれるなど充実した時を過ごす事が出来ました。 Kさんありがとう!
歩いていると目の前の木にセミが止まり、鳴き始めました、なんとも馴れ馴れしい「ツクツクボウシ」ではありました。 《ツクツクボウシ》


今日はKさんに案内をお願いして県西部、蛇紋岩地帯へ草花を見に行って来ました。
目的地までは東名を使って約1時間半で到着、歩き始めるとすぐに初見の「アイナエ」が小さな小さな白い花を付けて迎えてくれました。どんな時でも初対面はテンションが上がります。相変わらずの暑さをしばし忘れさせてくれました。
「コガンピ」の花などを愛でながらマイフィールドとはかなり異なる植生に一喜一憂しながら進むと『キキョウ』が端正な花を見せています。家庭のお庭ではよく見かける「キキョウ」ですが野生のものは随分と久しぶりです。一同感激!
その後も初見の「オオヒキヨモギ」にもお目に掛かれるなど充実した時を過ごす事が出来ました。 Kさんありがとう!
歩いていると目の前の木にセミが止まり、鳴き始めました、なんとも馴れ馴れしい「ツクツクボウシ」ではありました。 《ツクツクボウシ》

タグ :植物
2010年08月29日 Posted by 松ぽっくり at 23:15 │Comments(3) │花見
年に2回
ツルボ


「チガヤ」や「クズ」に覆われた斜面の隙間から『ツルボ』が一斉に顔を出しています。
ユリ科のこの草は春先に地中の鱗茎から普通2枚の葉を出しますが一旦枯れ、夏の終わりにもう一度葉が出て花を咲かせます。どうして年に2回も葉を出すのかよく解りませんが、「ヒガンバナ」の様に葉と花がすれ違いの生活をする者あり、「センボンヤリ」の様に春と秋に違うタイプの花を咲かせる者ありと、植物の習性も様々です。
ツルボの名前は穂が群生する事から「連れ立つ穂」ツレボが転じたと云う説などいくつかありますが定かではありません。
鱗茎はネギの様な匂いがします。


「チガヤ」や「クズ」に覆われた斜面の隙間から『ツルボ』が一斉に顔を出しています。
ユリ科のこの草は春先に地中の鱗茎から普通2枚の葉を出しますが一旦枯れ、夏の終わりにもう一度葉が出て花を咲かせます。どうして年に2回も葉を出すのかよく解りませんが、「ヒガンバナ」の様に葉と花がすれ違いの生活をする者あり、「センボンヤリ」の様に春と秋に違うタイプの花を咲かせる者ありと、植物の習性も様々です。
ツルボの名前は穂が群生する事から「連れ立つ穂」ツレボが転じたと云う説などいくつかありますが定かではありません。
鱗茎はネギの様な匂いがします。
タグ :植物
2010年08月28日 Posted by 松ぽっくり at 14:38 │Comments(0) │フィールド
大差なく
マルバルコウ

中々秋の気配が見えてこない気温ですが、草花は去年と大差なく咲いて来ます。
『マルバルコウ』が昨年とは別の斜面で咲き始めました。
花は直径1.5~2㌢とさほど大きくはありませんが、その朱赤色は人参を輪切りにしたような色でよく目立ちます。
葉はハート型に近い形をしていますが、極めて変化が多い。
熱帯アメリカ原産、ヒルガオ科のツル性一年草で北陸、北関東以南に帰化しているようです。

中々秋の気配が見えてこない気温ですが、草花は去年と大差なく咲いて来ます。
『マルバルコウ』が昨年とは別の斜面で咲き始めました。
花は直径1.5~2㌢とさほど大きくはありませんが、その朱赤色は人参を輪切りにしたような色でよく目立ちます。
葉はハート型に近い形をしていますが、極めて変化が多い。
熱帯アメリカ原産、ヒルガオ科のツル性一年草で北陸、北関東以南に帰化しているようです。
タグ :植物
2010年08月26日 Posted by 松ぽっくり at 22:25 │Comments(0) │フィールド
豆のサヤを
クサネム


朝の休耕田『クサネム』が花と一緒に豆のサヤを作り始めていました。
このサヤは熟すと節ごとに離れて落ちます。果皮がコルク質で軽いので水に浮き、流れて散布される。
「草合歓」の名前は葉が「ネムノキ」に似ている為。そして「ネムノキ」同様に暗くなると葉を閉じます。
フィールドには同じような形の葉を持つ「カワラケツメイ」もありますが花の作りが大分違う。
ちなみにカワラケツメイはもうすぐ咲き始めるはずです。


朝の休耕田『クサネム』が花と一緒に豆のサヤを作り始めていました。
このサヤは熟すと節ごとに離れて落ちます。果皮がコルク質で軽いので水に浮き、流れて散布される。
「草合歓」の名前は葉が「ネムノキ」に似ている為。そして「ネムノキ」同様に暗くなると葉を閉じます。
フィールドには同じような形の葉を持つ「カワラケツメイ」もありますが花の作りが大分違う。
ちなみにカワラケツメイはもうすぐ咲き始めるはずです。
タグ :植物
2010年08月25日 Posted by 松ぽっくり at 23:27 │Comments(0) │休耕田
突き立てて
ヤブマオ

今日は曇り気味でいくらか暑さも・・・と思ったが相変わらず・・・です。
土手下の空地では『ヤブマオ』が雌花の穂を突き立てていました。
全国の山野や道端などに普通に見られる「ヤブマオ」や「アカソ」ですが、この仲間はほとんどが雄花を付けず雌花だけ付ける個体が多い。
そしてほとんどが無性生殖で両性生殖をするものは少なく、無性生殖をすると親の形質がそのまま次の代に伝わる為、色々な形が出来やすくなり、識別には結構手をやく事になる。

今日は曇り気味でいくらか暑さも・・・と思ったが相変わらず・・・です。

土手下の空地では『ヤブマオ』が雌花の穂を突き立てていました。
全国の山野や道端などに普通に見られる「ヤブマオ」や「アカソ」ですが、この仲間はほとんどが雄花を付けず雌花だけ付ける個体が多い。
そしてほとんどが無性生殖で両性生殖をするものは少なく、無性生殖をすると親の形質がそのまま次の代に伝わる為、色々な形が出来やすくなり、識別には結構手をやく事になる。
タグ :植物
2010年08月24日 Posted by 松ぽっくり at 22:40 │Comments(0) │フィールド
絡みついて
ツルフジバカマ


今日は「処暑」暑さも和らぐ頃、と云う事になっていますが、今しばらくはムリのようだ。
「チガヤ」や「ススキ」の葉を押しやり絡みついて『ツルフジバカマ』の花が咲き始めました。
去年と同じ土手の斜面、多少テレトリーは狭まったような気がします、そして去年この花を取り上げたのが8/23と全くの同日 これはあくまで私が気付いた日なので、同じ日に咲き始めた訳ではありませんがそれにしてもほぼ同日に近い正確さです。
「クサフジ」や「ナヨクサフジ」によく似ていますが、花の色はこちらの方が少し赤みを帯びています。名前の由来は今一つはっきりしませんが漢字では「蔓藤袴」と書く。
土手の斜面でも向きによっては草達が肩を落としている所もあります、一雨ほしいところです。


今日は「処暑」暑さも和らぐ頃、と云う事になっていますが、今しばらくはムリのようだ。
「チガヤ」や「ススキ」の葉を押しやり絡みついて『ツルフジバカマ』の花が咲き始めました。
去年と同じ土手の斜面、多少テレトリーは狭まったような気がします、そして去年この花を取り上げたのが8/23と全くの同日 これはあくまで私が気付いた日なので、同じ日に咲き始めた訳ではありませんがそれにしてもほぼ同日に近い正確さです。

「クサフジ」や「ナヨクサフジ」によく似ていますが、花の色はこちらの方が少し赤みを帯びています。名前の由来は今一つはっきりしませんが漢字では「蔓藤袴」と書く。
土手の斜面でも向きによっては草達が肩を落としている所もあります、一雨ほしいところです。
タグ :植物
2010年08月23日 Posted by 松ぽっくり at 22:49 │Comments(0) │フィールド
裏の
メマツヨイグサ


朝、『メマツヨイグサ』が務めを終えようとしていました。
この花は夕方、暗くなってから咲き始め、朝、明るくなると萎んでしまいます。
恐らく夜行性の蛾などに花粉の媒介を委ねているものと思われ、裏の生活パターンを持った花です。ただ、この生活パターンも今の内だけで9月に入って花期も終盤になるとかなりダラけてきて、夕方も早い内から咲き始め、朝、日が昇って簡単には萎みません。雨の日などは更に顕著で日中でも咲いていたりします。
北アメリカ原産で明治中期に渡来したと云われ、各地の道ばたや空地、河原などによく見られます。


朝、『メマツヨイグサ』が務めを終えようとしていました。
この花は夕方、暗くなってから咲き始め、朝、明るくなると萎んでしまいます。
恐らく夜行性の蛾などに花粉の媒介を委ねているものと思われ、裏の生活パターンを持った花です。ただ、この生活パターンも今の内だけで9月に入って花期も終盤になるとかなりダラけてきて、夕方も早い内から咲き始め、朝、日が昇って簡単には萎みません。雨の日などは更に顕著で日中でも咲いていたりします。
北アメリカ原産で明治中期に渡来したと云われ、各地の道ばたや空地、河原などによく見られます。
タグ :植物
2010年08月22日 Posted by 松ぽっくり at 23:20 │Comments(0) │フィールド
色づいた実
エノキ

土手横の『エノキ』の実が色付き始めました。国蝶に指定されている
「オオムラサキ」の食樹としても知られているし、昔から云われの有る大木が
あったりしてよく見る木ですが、案外色付く果実は知られていない。
大きな木の、手の届かない所で実を結び、直径6ミリ程と小さい事もあるのでしょう。
河原では鳥が種を運ぶのでしょうか、あちこちで幼木を見かけます。
果実は完熟すると赤褐色になり、干し柿に似た味がするが水分が少ないため、
あまりお勧めできる味ではない。


土手横の『エノキ』の実が色付き始めました。国蝶に指定されている
「オオムラサキ」の食樹としても知られているし、昔から云われの有る大木が
あったりしてよく見る木ですが、案外色付く果実は知られていない。
大きな木の、手の届かない所で実を結び、直径6ミリ程と小さい事もあるのでしょう。
河原では鳥が種を運ぶのでしょうか、あちこちで幼木を見かけます。
果実は完熟すると赤褐色になり、干し柿に似た味がするが水分が少ないため、
あまりお勧めできる味ではない。

タグ :植物
2010年08月20日 Posted by 松ぽっくり at 22:29 │Comments(2) │フィールド
花だけ出して
ヨメナ

畑の横の空き地、ヨモギが生茂る中から花だけ出して『ヨメナ』が微笑んでいました。
一般に野菊と呼ばれるものは「ノコンギク」や「ユウガギク」など多数ありますが、その中でも「ヨメナ」は代表選手と云っていいでしょう。
昔から春の摘み草でも「ウハギ」と呼ばれ人気があったようで、現代でもキクの香りと苦味を好む方は多いようです。
花の形や色は生えている場所によって結構バラツキがあり、花弁が細かったり太かったり、うす紫色で有ったり白かったりします。
この頃夕方になると雷が鳴るのですが、その割には雨が降らない。

畑の横の空き地、ヨモギが生茂る中から花だけ出して『ヨメナ』が微笑んでいました。
一般に野菊と呼ばれるものは「ノコンギク」や「ユウガギク」など多数ありますが、その中でも「ヨメナ」は代表選手と云っていいでしょう。
昔から春の摘み草でも「ウハギ」と呼ばれ人気があったようで、現代でもキクの香りと苦味を好む方は多いようです。
花の形や色は生えている場所によって結構バラツキがあり、花弁が細かったり太かったり、うす紫色で有ったり白かったりします。
この頃夕方になると雷が鳴るのですが、その割には雨が降らない。

タグ :植物
2010年08月19日 Posted by 松ぽっくり at 21:57 │Comments(0) │空き地
球体の中で
イヌビワ

土手下の水路のわきで 早くも『イヌビワ』が黒熟し始めています。
クワ科イチジク属の仲間は秘密が好きなようで、この果実の様な球体の中で花を付け、受粉し、種を、秘密裏に作るのです。そしてその手助けをするのが「イチジクコバチ科」のハチ達で有り、イヌビワの場合は「イヌビワコバチ」がその役を担います。
したがってこの球体は、ある時は花で有りまたある時は果実であったりするのです。
どうしてこんな頭が混乱するような仕組みをあみ出したのか???がいくつあっても足りません。
もう暑いと云うのも飽きてきました。

土手下の水路のわきで 早くも『イヌビワ』が黒熟し始めています。
クワ科イチジク属の仲間は秘密が好きなようで、この果実の様な球体の中で花を付け、受粉し、種を、秘密裏に作るのです。そしてその手助けをするのが「イチジクコバチ科」のハチ達で有り、イヌビワの場合は「イヌビワコバチ」がその役を担います。

したがってこの球体は、ある時は花で有りまたある時は果実であったりするのです。

どうしてこんな頭が混乱するような仕組みをあみ出したのか???がいくつあっても足りません。
もう暑いと云うのも飽きてきました。

タグ :植物
2010年08月18日 Posted by 松ぽっくり at 23:10 │Comments(0) │フィールド
チョウチンバナ
ツリガネニンジン

草丈の伸びた斜面に『ツリガネニンジン』の白い釣鐘が見え隠れしています。
今年は草刈りのタイミングが悪かったと見えてこのフィールドでは初見になります。
図鑑等で花の色は薄紫色のものが多く載っていますが、ここでは色がうすくほとんど白に見えます。
名前は花が釣鐘型で根が朝鮮人参に似ていて薬用にもなる事から「釣鐘人参」となったとの事。県内には「チョウチンバナ」「チチクサ」などの方言名もあるようです。
相変わらずの残暑です。さすがに日の盛りは避けてのお出かけとなります。もう少し風でも有ってくれれば救われるのですが・・・

草丈の伸びた斜面に『ツリガネニンジン』の白い釣鐘が見え隠れしています。
今年は草刈りのタイミングが悪かったと見えてこのフィールドでは初見になります。
図鑑等で花の色は薄紫色のものが多く載っていますが、ここでは色がうすくほとんど白に見えます。
名前は花が釣鐘型で根が朝鮮人参に似ていて薬用にもなる事から「釣鐘人参」となったとの事。県内には「チョウチンバナ」「チチクサ」などの方言名もあるようです。
相変わらずの残暑です。さすがに日の盛りは避けてのお出かけとなります。もう少し風でも有ってくれれば救われるのですが・・・
タグ :植物
2010年08月17日 Posted by 松ぽっくり at 23:09 │Comments(2) │フィールド
埋め尽くすほど
フサフジウツギ


暑さに負けて部屋から脱出、車で山に向けて走ってみました。おおよそ1時間、梅が島に付きましたが、残念な事に涼しくはありません。
更に車を進めて安倍峠まで行くとさすがに下界とは異なり空気がフレッシュです。
ただ林床を笹が支配する「笹の安倍峠」に今ひとつ心が晴れぬまま帰路につく事に。
この時期花は望むべきもなく、道すがらは「ボタンズル」「タマアジサイ」程度ですが、梅が島付近の河原では『フサフジウツギ』が河原を埋め尽くすほど沢山咲いていました。
落葉低木のこの花は中国原産の栽培植物が野生化したと云う説と、本州中部の石灰岩地に自生する在来種とする説が有りますが、この河原を埋め尽くすほどの勢いは外来種のそれを思い起こさせます。


暑さに負けて部屋から脱出、車で山に向けて走ってみました。おおよそ1時間、梅が島に付きましたが、残念な事に涼しくはありません。

更に車を進めて安倍峠まで行くとさすがに下界とは異なり空気がフレッシュです。

ただ林床を笹が支配する「笹の安倍峠」に今ひとつ心が晴れぬまま帰路につく事に。

この時期花は望むべきもなく、道すがらは「ボタンズル」「タマアジサイ」程度ですが、梅が島付近の河原では『フサフジウツギ』が河原を埋め尽くすほど沢山咲いていました。
落葉低木のこの花は中国原産の栽培植物が野生化したと云う説と、本州中部の石灰岩地に自生する在来種とする説が有りますが、この河原を埋め尽くすほどの勢いは外来種のそれを思い起こさせます。

タグ :植物
2010年08月17日 Posted by 松ぽっくり at 00:22 │Comments(2) │花見
白い玉の
ヤマノイモ雄花

今日は日の盛りを避けて出かけさせていただきました。
土手の下の茶畑、手入れが不十分と見えて茶の木の上に「ヘクソカズラ」や『ヤマノイモ』が花を咲かせていました。ヤマノイモは雌雄別株で雌花は垂れ下りますが、雄花は立ちあがります。雄花の花被は6個有りますがほんの僅かしか開かないので白い玉の様に見えます。
「ジネンジョ」として人気の有るヤマノイモですが、茶畑に入り込まれると他のツル植物と同様に結構厄介かも知れません。
暑かった、今年初めて35℃を超えたそうです。エアコンの効いていない部屋ではこの時間になっても30℃を指しています(少々寒暖計の精度が気になる所では有りますが)

今日は日の盛りを避けて出かけさせていただきました。
土手の下の茶畑、手入れが不十分と見えて茶の木の上に「ヘクソカズラ」や『ヤマノイモ』が花を咲かせていました。ヤマノイモは雌雄別株で雌花は垂れ下りますが、雄花は立ちあがります。雄花の花被は6個有りますがほんの僅かしか開かないので白い玉の様に見えます。
「ジネンジョ」として人気の有るヤマノイモですが、茶畑に入り込まれると他のツル植物と同様に結構厄介かも知れません。
暑かった、今年初めて35℃を超えたそうです。エアコンの効いていない部屋ではこの時間になっても30℃を指しています(少々寒暖計の精度が気になる所では有りますが)
タグ :植物
2010年08月15日 Posted by 松ぽっくり at 23:42 │Comments(0) │フィールド
今様の
アカメガシワ(種)

土手沿いの『アカメガシワ』は早くも果実が割れて黒い種を見せている。その同じ木には雌花が咲いていると云うのに!
去年の暮れに黄葉と一緒に種も写した事を思うと同じフィールド内でも木によってかなり差が有るようだ。と云うか自由奔放、今様の木かも知れない。
土手下の工場はお盆の休みに入ったようで静まり返っている。フィールドもいつもの土曜日とはどこか違う、世間は休暇モードだ。

土手沿いの『アカメガシワ』は早くも果実が割れて黒い種を見せている。その同じ木には雌花が咲いていると云うのに!
去年の暮れに黄葉と一緒に種も写した事を思うと同じフィールド内でも木によってかなり差が有るようだ。と云うか自由奔放、今様の木かも知れない。

土手下の工場はお盆の休みに入ったようで静まり返っている。フィールドもいつもの土曜日とはどこか違う、世間は休暇モードだ。
2010年08月14日 Posted by 松ぽっくり at 23:27 │Comments(0) │フィールド
ペパーミント
コショウハッカ

先日の「マルバハッカ」に続いて『コショウハッカ』も田んぼのすみで咲いていました。
ヨーロッパ原産のこのハッカは英名が「ペパーミント」、世界各地で香辛料として栽培され、また野生化しているようです。
日本にも明治年間に香辛料として導入されましたが、本格的に生産されるには至らずハーブとして家庭用に栽培されて来ました。全国的に野生化していて、別名は「セイヨウハッカ」
ハーブに興味を持つ方が増えているので、ハッカの仲間は新たな野性化が進む可能性があります。
立秋の後、多少和らいでいた暑さがぶり返しました。

先日の「マルバハッカ」に続いて『コショウハッカ』も田んぼのすみで咲いていました。
ヨーロッパ原産のこのハッカは英名が「ペパーミント」、世界各地で香辛料として栽培され、また野生化しているようです。
日本にも明治年間に香辛料として導入されましたが、本格的に生産されるには至らずハーブとして家庭用に栽培されて来ました。全国的に野生化していて、別名は「セイヨウハッカ」
ハーブに興味を持つ方が増えているので、ハッカの仲間は新たな野性化が進む可能性があります。
立秋の後、多少和らいでいた暑さがぶり返しました。
タグ :植物
2010年08月13日 Posted by 松ぽっくり at 22:53 │Comments(0) │田んぼ
密生して
ガガイモ

白い毛が密生した花
先日までつぼみだった『ガガイモ』の花が開いていた。内側に白い毛が密生して内部の構造がよく見えないが、先日の「イケマ」同様に雄しべと雌しべが合着してズイ柱を作り、その先端が長く突き出ているのが分かります。
秋に袋状の果実を付けますが、その内面がカガミの様に光っていた事から「カガミ」の古名ができ、それが変化して「ガガイモ」になったと云われています。
午後、意外と早く回復して青空も見えてきた。雨上がりのフィールドは湿度が高く「ムッ」とするが、強めの風がそれを取り除いてくれた。

白い毛が密生した花

先日までつぼみだった『ガガイモ』の花が開いていた。内側に白い毛が密生して内部の構造がよく見えないが、先日の「イケマ」同様に雄しべと雌しべが合着してズイ柱を作り、その先端が長く突き出ているのが分かります。
秋に袋状の果実を付けますが、その内面がカガミの様に光っていた事から「カガミ」の古名ができ、それが変化して「ガガイモ」になったと云われています。

午後、意外と早く回復して青空も見えてきた。雨上がりのフィールドは湿度が高く「ムッ」とするが、強めの風がそれを取り除いてくれた。
タグ :植物
2010年08月12日 Posted by 松ぽっくり at 21:54 │Comments(0) │フィールド
獰猛な
ハンミョウ

不安定な空模様を気にかけながら仲間と近くの山道を歩いて来ました。
チョウの数も多く、樹冠を飛ぶもの、花に来るもの、道端で吸水するものと様々、
雲が切れ、突然日が差して明るくなった目の前に『ハンミョウ』が現れました。
いつもながらその金属光沢の艶やかさに目を見張ります。
しかし妖しささえ湛えたその姿には何故か悪のにおいが! 成虫はもちろん幼虫までも獰猛な肉食である事がインプットされている為でしょうか?
私達が進めば進み、止まれば止まる「ミチオシエ」なる別名も持つ「ハンミョウ」に
ひと時楽しませて頂きました。
吸水するカラスアゲハ


不安定な空模様を気にかけながら仲間と近くの山道を歩いて来ました。
チョウの数も多く、樹冠を飛ぶもの、花に来るもの、道端で吸水するものと様々、
雲が切れ、突然日が差して明るくなった目の前に『ハンミョウ』が現れました。
いつもながらその金属光沢の艶やかさに目を見張ります。
しかし妖しささえ湛えたその姿には何故か悪のにおいが! 成虫はもちろん幼虫までも獰猛な肉食である事がインプットされている為でしょうか?
私達が進めば進み、止まれば止まる「ミチオシエ」なる別名も持つ「ハンミョウ」に
ひと時楽しませて頂きました。
吸水するカラスアゲハ

タグ :自然
2010年08月11日 Posted by 松ぽっくり at 23:25 │Comments(4) │下見
ぶら下げて
ジュズダマ

ツボの先端から糸の様な柱頭がのぞいています
土手下の空地で『ジュズダマ』が花をぶら下げていました。
雌花はツボの中に入っていて先端の白い柱頭だけが外に出て、花粉を待っています。雄花はツボの外へ延びだして黄色い葯をいくつもブラブラさせて花粉を風に委ねます。なんとも変わった作りの花です。
このツボは成熟して固く光沢のある玉となるので「数珠玉」の名が付いたようです。
よく似ている「ハトムギ」はツボが固くならず、指でつぶれます。

ツボの先端から糸の様な柱頭がのぞいています

土手下の空地で『ジュズダマ』が花をぶら下げていました。
雌花はツボの中に入っていて先端の白い柱頭だけが外に出て、花粉を待っています。雄花はツボの外へ延びだして黄色い葯をいくつもブラブラさせて花粉を風に委ねます。なんとも変わった作りの花です。
このツボは成熟して固く光沢のある玉となるので「数珠玉」の名が付いたようです。
よく似ている「ハトムギ」はツボが固くならず、指でつぶれます。
タグ :植物