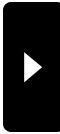レストラン
ヤナギの樹液に集まるチョウやカナブンなど
左コムラサキ、右ゴマダラチョウ
土曜の昼下がり、土手のヤナギのレストランではチョウ達がランチを楽しんでいました。
カミキリムシの仲間が付けたと思われる傷口から浸み出る樹液はそうとう魅力的と見えて、少しくらい翅に触っても知らん顔をしています。さすがに二回目に触ると飛び立ちますがその辺を一周してまた戻ってきます。ハチやカナブンも呉越同舟で食事に没頭していました。
チョウの種類は「コムラサキ」「ゴマダラチョウ」「アカタテハ」まで確認出来たがその他は??数からいくと「ヤナギ」を食樹にしていて、食樹から余り離れる事のない「コムラサキ」が多数派でした。ちなみにゴマダラチョウの食樹は「エノキ」です。
本日で7月も終わり。後一週間もすれば暦の上では秋が立つのだが、今年の暑さはそう簡単に引き下がりそうにない。

左コムラサキ、右ゴマダラチョウ

土曜の昼下がり、土手のヤナギのレストランではチョウ達がランチを楽しんでいました。
カミキリムシの仲間が付けたと思われる傷口から浸み出る樹液はそうとう魅力的と見えて、少しくらい翅に触っても知らん顔をしています。さすがに二回目に触ると飛び立ちますがその辺を一周してまた戻ってきます。ハチやカナブンも呉越同舟で食事に没頭していました。
チョウの種類は「コムラサキ」「ゴマダラチョウ」「アカタテハ」まで確認出来たがその他は??数からいくと「ヤナギ」を食樹にしていて、食樹から余り離れる事のない「コムラサキ」が多数派でした。ちなみにゴマダラチョウの食樹は「エノキ」です。
本日で7月も終わり。後一週間もすれば暦の上では秋が立つのだが、今年の暑さはそう簡単に引き下がりそうにない。
タグ :自然
2010年07月31日 Posted by 松ぽっくり at 17:09 │Comments(0) │フィールド
盛り久しい
アキカラマツ

雄しべだけが目立ちますが、雌しべは短くて雄しべの付け根にあります。
久々の雨です。それもかなり強力にアクセントを付けながら一日中降り、明日まで続くようです。 土手の草達は大いに元気づいた事でしょう。
と云う事で一日閉じ込められましたので、昨日出会った『アキカラマツ』を紹介します。
この草もフィールド内のメインメンバーのひとつで、時々登場しますが刈られても刈られても元気です。昔の本に「夏から秋へ盛り久しい」と載っているように花期は長い。
花には花弁が無くガクも早く落ちて、雄しべが目立つ姿をカラマツの葉に見立てた「カラマツソウ」の仲間で秋まで咲いているので「秋唐松」となったようです。
つかの間、暑さが大分退いて、そうとう楽です。

雄しべだけが目立ちますが、雌しべは短くて雄しべの付け根にあります。

久々の雨です。それもかなり強力にアクセントを付けながら一日中降り、明日まで続くようです。 土手の草達は大いに元気づいた事でしょう。
と云う事で一日閉じ込められましたので、昨日出会った『アキカラマツ』を紹介します。
この草もフィールド内のメインメンバーのひとつで、時々登場しますが刈られても刈られても元気です。昔の本に「夏から秋へ盛り久しい」と載っているように花期は長い。
花には花弁が無くガクも早く落ちて、雄しべが目立つ姿をカラマツの葉に見立てた「カラマツソウ」の仲間で秋まで咲いているので「秋唐松」となったようです。
つかの間、暑さが大分退いて、そうとう楽です。
タグ :植物
2010年07月29日 Posted by 松ぽっくり at 18:50 │Comments(0) │フィールド
模様が
キアゲハ

ほとんど花が終わり、残り少なくなった「ムラサキツメクサ」に『キアゲハ』が訪れていました。
「アゲハ」とよく似ていますが翅の付け根(頭に近い所)の模様が黒く塗りつぶされています。
梅雨が明けてからほとんど雨らしい雨が降らず土手の草達は乾燥に強いものとそうでないものとが明暗を分けています。
『梅雨明け10日』も過ぎそろそろ変化がほしい所です。

ほとんど花が終わり、残り少なくなった「ムラサキツメクサ」に『キアゲハ』が訪れていました。
「アゲハ」とよく似ていますが翅の付け根(頭に近い所)の模様が黒く塗りつぶされています。
梅雨が明けてからほとんど雨らしい雨が降らず土手の草達は乾燥に強いものとそうでないものとが明暗を分けています。
『梅雨明け10日』も過ぎそろそろ変化がほしい所です。
タグ :自然
2010年07月28日 Posted by 松ぽっくり at 17:31 │Comments(0) │フィールド
太陽を受けて
スベリヒユ

雄しべは触った方へ集まる
道端や畑のそばで『スベリヒユ』をよく見かけるが、午後は花に会う事はほとんどない。
黄色の小さな花は太陽を受けて開くが昼過ぎには萎んでしまう、もちろん曇った日や雨の日は開かない。
雄しべは7~12本あり触ると動く、この運動は虫の体に花粉を付ける為ではないかと云われている。
多肉質の葉を持ち丈夫な草で、茹でるとぬめりが有り昔から食用にされている。フランスでは食用に改良もされているようです。
江戸時代の本にはこの草の事が「葉は緑色、茎は赤色、花は黄色、根は白色、種は黒色なので五行草と云う」と説明している。実際に根は白い。

雄しべは触った方へ集まる

道端や畑のそばで『スベリヒユ』をよく見かけるが、午後は花に会う事はほとんどない。
黄色の小さな花は太陽を受けて開くが昼過ぎには萎んでしまう、もちろん曇った日や雨の日は開かない。
雄しべは7~12本あり触ると動く、この運動は虫の体に花粉を付ける為ではないかと云われている。
多肉質の葉を持ち丈夫な草で、茹でるとぬめりが有り昔から食用にされている。フランスでは食用に改良もされているようです。
江戸時代の本にはこの草の事が「葉は緑色、茎は赤色、花は黄色、根は白色、種は黒色なので五行草と云う」と説明している。実際に根は白い。
タグ :植物
2010年07月27日 Posted by 松ぽっくり at 22:17 │Comments(2) │フィールド
色も派手
マツグミ

変わった形のマツグミの花

『マツグミ』の花を見に行って来ました。2月の後半に青い実の付いている時に取り上げた所です。
想像以上に沢山の花に驚きました。半寄生でお世話になっている割には色もまた派手でひさしを貸した『クロマツ』は母屋を奪われそうな勢いでした。
子房下位の花は赤い筒状で先が4裂し片側に反り返る、そしてシベは花の外へ突き出しています。
地味な「クロマツ」に小さな赤い花のかたまりがおかしなコントラストを見せています。
この所、野山は大分乾き気味で草達もしんなりしています。一雨ほしい所ですが雷も音ばっかりで降るまでには至りません。

変わった形のマツグミの花

『マツグミ』の花を見に行って来ました。2月の後半に青い実の付いている時に取り上げた所です。
想像以上に沢山の花に驚きました。半寄生でお世話になっている割には色もまた派手でひさしを貸した『クロマツ』は母屋を奪われそうな勢いでした。
子房下位の花は赤い筒状で先が4裂し片側に反り返る、そしてシベは花の外へ突き出しています。
地味な「クロマツ」に小さな赤い花のかたまりがおかしなコントラストを見せています。
この所、野山は大分乾き気味で草達もしんなりしています。一雨ほしい所ですが雷も音ばっかりで降るまでには至りません。
タグ :植物
2010年07月26日 Posted by 松ぽっくり at 17:55 │Comments(2) │花を訪ねて
スッキリ!
ヤノネボンテンカ(中心に梅花模様が)

金網で囲んだ空地の隅に、午後に通るといつもしぼんでいる花が有るので今日は午前中に行って見ました。予想通りしっかり開いています、恐らく「アオイ科」ではないかと見当は付けたが始めて見る花なので??
帰宅後「アオイ科」付近をめくっているとよく似ている花が有った「ギンセンカ」とある、しかしよく見るとシベの作りが違う。「う~ん」と唸りながら「日本の帰化植物」(平凡社)に望みをかけて開くとまさしく「アオイ科」にありました。『ヤノネボンテンカ』でした。
南アメリカ原産で園芸植物として渡来したものと考えられているが、その時期については
不明となっていました。とりあえず疑問が解消されてスッキリ!
別名「タカサゴフヨウ」と呼ばれ茶花用に栽培もされるようです。

金網で囲んだ空地の隅に、午後に通るといつもしぼんでいる花が有るので今日は午前中に行って見ました。予想通りしっかり開いています、恐らく「アオイ科」ではないかと見当は付けたが始めて見る花なので??
帰宅後「アオイ科」付近をめくっているとよく似ている花が有った「ギンセンカ」とある、しかしよく見るとシベの作りが違う。「う~ん」と唸りながら「日本の帰化植物」(平凡社)に望みをかけて開くとまさしく「アオイ科」にありました。『ヤノネボンテンカ』でした。
南アメリカ原産で園芸植物として渡来したものと考えられているが、その時期については
不明となっていました。とりあえず疑問が解消されてスッキリ!

別名「タカサゴフヨウ」と呼ばれ茶花用に栽培もされるようです。
タグ :植物
2010年07月25日 Posted by 松ぽっくり at 14:19 │Comments(2) │空き地
花の長さが
ヤナギハナガサ

畑の横の道端に『ヤナギハナガサ』が一株、半分倒れそうになって花を付け、そこに「モンシロチョウ」が来ていました。昨年も一度取り上げましたが、こうしてアップにしてみると、1個1個の花の長さが「アレチハナガサ」に比べ倍ぐらい長いのが分かります。
茎や葉には剛毛が有って著しくざらつきます。
今日は「大暑」一年で一番暑さの厳しい頃と云う事になっています。暦の上と実際は異なるものだが、今回はぴったり合致してひどく暑く、この暑さにタイショしきれていない自分がいます。

畑の横の道端に『ヤナギハナガサ』が一株、半分倒れそうになって花を付け、そこに「モンシロチョウ」が来ていました。昨年も一度取り上げましたが、こうしてアップにしてみると、1個1個の花の長さが「アレチハナガサ」に比べ倍ぐらい長いのが分かります。
茎や葉には剛毛が有って著しくざらつきます。
今日は「大暑」一年で一番暑さの厳しい頃と云う事になっています。暦の上と実際は異なるものだが、今回はぴったり合致してひどく暑く、この暑さにタイショしきれていない自分がいます。

タグ :植物
2010年07月23日 Posted by 松ぽっくり at 23:02 │Comments(0) │フィールド
一本だけ
ホルトノキ

花は下から覗かないとはっきりしない
土手に一本だけ植えられている『ホルトノキ』が数え切れないほど沢山のツボミを付け、その約40%程が花を開きました。昨年に比べると少し遅い気がします。
小さくて繊細な白い花には虫達が訪れ始めています。昨年はほとんど結実しなかったが・・・さて今年はどうでしょう「オリーブ」に似た実を付ける事が出来るだろうか?
日に日に暑さは増して室内の温度計までもついに30℃を超えた。こんな時に夕立のひとつもほしいのだが遠くで雷の音はするものの降らない。

花は下から覗かないとはっきりしない

土手に一本だけ植えられている『ホルトノキ』が数え切れないほど沢山のツボミを付け、その約40%程が花を開きました。昨年に比べると少し遅い気がします。
小さくて繊細な白い花には虫達が訪れ始めています。昨年はほとんど結実しなかったが・・・さて今年はどうでしょう「オリーブ」に似た実を付ける事が出来るだろうか?
日に日に暑さは増して室内の温度計までもついに30℃を超えた。こんな時に夕立のひとつもほしいのだが遠くで雷の音はするものの降らない。

タグ :植物
2010年07月21日 Posted by 松ぽっくり at 23:09 │Comments(0) │フィールド
林立して
イヌドクサ

土手の西向きの斜面に『イヌドクサ』が胞子嚢を付けて林立していた。胞子嚢は春のツクシンボウによく似て可愛い。
研磨材や薬用(利尿、下痢止、眼病、止血等)として栽培もされる「トクサ」に対し、役に立たないので「犬砥草」と名付けられたようです。
また、「トクサ」は半日蔭を好みますが「イヌドクサ」は陽地を好み「カワラドクサ」の別名もある。
TVやラジオで盛んに「熱中症」に注意を呼びかけています。こまめに水を補給したら盛んに汗が出てきました。

土手の西向きの斜面に『イヌドクサ』が胞子嚢を付けて林立していた。胞子嚢は春のツクシンボウによく似て可愛い。
研磨材や薬用(利尿、下痢止、眼病、止血等)として栽培もされる「トクサ」に対し、役に立たないので「犬砥草」と名付けられたようです。
また、「トクサ」は半日蔭を好みますが「イヌドクサ」は陽地を好み「カワラドクサ」の別名もある。
TVやラジオで盛んに「熱中症」に注意を呼びかけています。こまめに水を補給したら盛んに汗が出てきました。

タグ :植物
2010年07月20日 Posted by 松ぽっくり at 22:51 │Comments(0) │フィールド
定かでは
オオケタデ

水路のふち「ナツグミ」の横に何処からか逃げ出して来たのか?それとも誰かが植えたのか?定かではないが『オオケタデ』が一本120㌢ほどに伸び、紅い花穂を付けていました。
インドから中国にかけての原産で、江戸時代に蛇毒の薬草として導入されたようだが、その後は主に鑑賞用に栽培され、全国各地で逸出して野生化が見られる。
タデの仲間にしては、全体に大型で毛が多いので「大毛蓼」となった。
云いたくは無いが今日も暑かった!

水路のふち「ナツグミ」の横に何処からか逃げ出して来たのか?それとも誰かが植えたのか?定かではないが『オオケタデ』が一本120㌢ほどに伸び、紅い花穂を付けていました。
インドから中国にかけての原産で、江戸時代に蛇毒の薬草として導入されたようだが、その後は主に鑑賞用に栽培され、全国各地で逸出して野生化が見られる。
タデの仲間にしては、全体に大型で毛が多いので「大毛蓼」となった。
云いたくは無いが今日も暑かった!
タグ :植物
2010年07月19日 Posted by 松ぽっくり at 22:45 │Comments(0) │フィールド
19:10分
カラスウリ雄花

折は有りませんでしたが、気になって・・・
静岡の日没時間19:00時丁度、に家を出て現地到着が19:10分。すでにドラマは終わっていました。
夕闇が忍び寄る中、そこだけポッと白くなって花は開ききっていました。 白い花弁は5つに分かれ、その先は繊細に絡み合い美しい。
白い花弁は5つに分かれ、その先は繊細に絡み合い美しい。
数ある花の中でもこれほど不思議な作りは少なく、自然の妙に驚かざるを得ません。
ただフラッシュを使わずに撮りたかったのですが、手持ちのコンデジでは夕闇の中そういう訳にもいかず多少不満の残る画になってしまいました。

折は有りませんでしたが、気になって・・・
静岡の日没時間19:00時丁度、に家を出て現地到着が19:10分。すでにドラマは終わっていました。
夕闇が忍び寄る中、そこだけポッと白くなって花は開ききっていました。
 白い花弁は5つに分かれ、その先は繊細に絡み合い美しい。
白い花弁は5つに分かれ、その先は繊細に絡み合い美しい。
数ある花の中でもこれほど不思議な作りは少なく、自然の妙に驚かざるを得ません。
ただフラッシュを使わずに撮りたかったのですが、手持ちのコンデジでは夕闇の中そういう訳にもいかず多少不満の残る画になってしまいました。
タグ :植物
2010年07月18日 Posted by 松ぽっくり at 22:31 │Comments(0) │花を訪ねて
日が暮れてから
カラスウリ

ドラマは日が暮れてから。
イヌマキの垣根に絡んだ『カラスウリ』が早くも蕾を付けた。この花は日が暮れてから繊細で白いレース編みの様な花をひっそりと開く。花は雌雄別株のため夏の宵に訪れる蛾にその橋渡しを委ね、翌朝には萎んでしまう。したがってこの花を知っている人は案外少ない。
折を見て開花を撮りに行ってみるつもりです。

ドラマは日が暮れてから。
イヌマキの垣根に絡んだ『カラスウリ』が早くも蕾を付けた。この花は日が暮れてから繊細で白いレース編みの様な花をひっそりと開く。花は雌雄別株のため夏の宵に訪れる蛾にその橋渡しを委ね、翌朝には萎んでしまう。したがってこの花を知っている人は案外少ない。
折を見て開花を撮りに行ってみるつもりです。
タグ :植物
2010年07月18日 Posted by 松ぽっくり at 17:05 │Comments(0) │畑地
抜きんでて
チダケサシ

今日は皆さんと梅雨明け直後の里山を覗いて来ました。30℃を超えるしたたかな暑さですが時折の涼風が癒してくれます。
セリの花が咲く小さな湿地のそばではトンボやチョウの動きも活発で、草藪の中からは『チダケサシ』が抜きんでて淡いピンクの花序を見せています。花の色は個体差が有り白に近いものから濃いピンクまで様々です。
チダケサシの名前の由来は、食用キノコの「チチタケ」を持ち帰る際にこの草の茎に通したと云う地方の習慣がそのまま「乳茸刺」となったと云われています。
「梅雨明け10日」で、しばらくは晴天で暑い日が続くらしい。


今日は皆さんと梅雨明け直後の里山を覗いて来ました。30℃を超えるしたたかな暑さですが時折の涼風が癒してくれます。
セリの花が咲く小さな湿地のそばではトンボやチョウの動きも活発で、草藪の中からは『チダケサシ』が抜きんでて淡いピンクの花序を見せています。花の色は個体差が有り白に近いものから濃いピンクまで様々です。
チダケサシの名前の由来は、食用キノコの「チチタケ」を持ち帰る際にこの草の茎に通したと云う地方の習慣がそのまま「乳茸刺」となったと云われています。
「梅雨明け10日」で、しばらくは晴天で暑い日が続くらしい。
2010年07月17日 Posted by 松ぽっくり at 21:15 │Comments(1) │観察会
張り付くように
クルマバザクロソウ
アリと比べると花の大きさがおおよそ見当が付きます。
道端の乾いた所に張り付くように『クルマバザクロソウ』が小さな花をいくつも付けています。白い花弁の様に見えるのはガク片で花弁は有りません。
熱帯アメリカの原産で明治の頃に新潟で見つかり、今では全国の道ばたなどで普通に見られるようです。
名前はザクロに似た葉が輪生する事から「車葉柘榴草」となったようですが・・・
明日からの予報は
 マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。
マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。

アリと比べると花の大きさがおおよそ見当が付きます。

道端の乾いた所に張り付くように『クルマバザクロソウ』が小さな花をいくつも付けています。白い花弁の様に見えるのはガク片で花弁は有りません。
熱帯アメリカの原産で明治の頃に新潟で見つかり、今では全国の道ばたなどで普通に見られるようです。
名前はザクロに似た葉が輪生する事から「車葉柘榴草」となったようですが・・・

明日からの予報は

 マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。
マークが並んでいます。雨の季節もどうやら幕が引かれるようだ。
タグ :植物
2010年07月16日 Posted by 松ぽっくり at 22:25 │Comments(0) │近所
上を向いて
ヒメヤブラン

背の高い草の隙間で『ヒメヤブラン』が花を付けています。花茎の高さは10~15㌢程しか有りませんので普通に歩いているとほぼ気付きません。
横につる枝を延ばして増え、所々葉がかたまって出る。子房上位の花は上を向いて咲きます。
西日本での豪雨による被害が連日報道されていますが、こちらでは注意報や警報は出るものの雨もそれほどでは無く助かります。


背の高い草の隙間で『ヒメヤブラン』が花を付けています。花茎の高さは10~15㌢程しか有りませんので普通に歩いているとほぼ気付きません。
横につる枝を延ばして増え、所々葉がかたまって出る。子房上位の花は上を向いて咲きます。
西日本での豪雨による被害が連日報道されていますが、こちらでは注意報や警報は出るものの雨もそれほどでは無く助かります。
タグ :植物
2010年07月15日 Posted by 松ぽっくり at 22:09 │Comments(0) │フィールド
偽の・・・
コマツナギ

いよいよクマゼミが鳴き始めました。まだ単発的で暑さを増幅する所まではいっていませんが、これが梅雨明け間近のサインで有れば嬉しい・・・
『コマツナギ』が大分増えてきました。名前の由来は前回取り上げた時に書きましたが、やや乾き気味の所が好きと云う事で河原には多く見られます。
話は少し飛びますが、ジーンズなどを藍色に染める染料の「インディゴ」はコマツナギの仲間(ティンクトリア)を栽培して作られて来ましたがコマツナギ自体は染料にはなりません。
ただ姿形はよく似ているので学名には「偽のティンクトリア」と云う名が付けられました。

いよいよクマゼミが鳴き始めました。まだ単発的で暑さを増幅する所まではいっていませんが、これが梅雨明け間近のサインで有れば嬉しい・・・

『コマツナギ』が大分増えてきました。名前の由来は前回取り上げた時に書きましたが、やや乾き気味の所が好きと云う事で河原には多く見られます。
話は少し飛びますが、ジーンズなどを藍色に染める染料の「インディゴ」はコマツナギの仲間(ティンクトリア)を栽培して作られて来ましたがコマツナギ自体は染料にはなりません。
ただ姿形はよく似ているので学名には「偽のティンクトリア」と云う名が付けられました。

タグ :植物
2010年07月14日 Posted by 松ぽっくり at 23:01 │Comments(0) │フィールド
線香花火
アゼガヤツリ

白い糸状は雌しべの先端
近所の田んぼのイネも大分背丈が伸びて来ました。畦の草も歩調を合わせて伸びています。
そんな中に『アゼガヤツリ』も線香花火の様な姿でアクセントを付けています。でももうすぐ抜かれる定めでは有るのですが・・・名前は畔に多いカヤツリグサと云う事で「畔蚊帳吊」となりました。
「カヤツリグサ」「コゴメガヤツリ」と並んで休耕田や畔などに最も多い種です。
今日も一日雨の予報でしたが、午後になるとひとしきり青空が出て夜はまた雨。この所こんな荒っぽい日が続きます。

白い糸状は雌しべの先端

近所の田んぼのイネも大分背丈が伸びて来ました。畦の草も歩調を合わせて伸びています。
そんな中に『アゼガヤツリ』も線香花火の様な姿でアクセントを付けています。でももうすぐ抜かれる定めでは有るのですが・・・名前は畔に多いカヤツリグサと云う事で「畔蚊帳吊」となりました。
「カヤツリグサ」「コゴメガヤツリ」と並んで休耕田や畔などに最も多い種です。
今日も一日雨の予報でしたが、午後になるとひとしきり青空が出て夜はまた雨。この所こんな荒っぽい日が続きます。
タグ :植物
2010年07月13日 Posted by 松ぽっくり at 22:47 │Comments(0) │田んぼ
秋に限らず
アキノタムラソウ
花には白い長毛が生えています
土手の斜面の下の方に『アキノタムラソウ』が咲いているのに気が付きました。
野山で普通に見られる野草ですが、このフィールドでは案外少ない。
名前は「秋の田村草」と付いていますが、秋に限らず7月頃から11月頃まで見る事が出来ます。
ちなみに「春の田村草」「夏の田村草」もありますが、これらは地域にもより中々お目にかかれません。
ただなんで「田村草」なのか?わかりません シソ科サルビア属
シソ科サルビア属
降ったりやんだり日が照ったり目まぐるしく変わるへんな天気の一日でした。

花には白い長毛が生えています

土手の斜面の下の方に『アキノタムラソウ』が咲いているのに気が付きました。
野山で普通に見られる野草ですが、このフィールドでは案外少ない。
名前は「秋の田村草」と付いていますが、秋に限らず7月頃から11月頃まで見る事が出来ます。
ちなみに「春の田村草」「夏の田村草」もありますが、これらは地域にもより中々お目にかかれません。
ただなんで「田村草」なのか?わかりません
 シソ科サルビア属
シソ科サルビア属降ったりやんだり日が照ったり目まぐるしく変わるへんな天気の一日でした。
タグ :植物
2010年07月12日 Posted by 松ぽっくり at 22:44 │Comments(2) │フィールド
いつ見ても
ノブドウ

花弁が落ちた後の花盤は蜜を分泌する(白っぽいのが蕾)
午後は雨の確率が高いと云う事なので、参院選を早めに済ませ、そのままフィールドへ
河原のグランドは日曜とあってGGの大会らしく人と車であふれている。
カラタチに絡みついた『ノブドウ』の蕾の集まりはいつ見ても蕾のままの様に見える。しかし近づいてよく見ると蕾と開花したものが混在している。
花弁は開花後間もなく落ちてしまい、蕾とほぼ同じ位の基部だけ残るのでいつまでも蕾のままの様に見えるようだ。ただ色は少し黄みを帯びるのでよく見るとわかる。
土手の草むらで「チョン、ギース」「チョン、ギース」と早くもキリギリスが鳴き始めた。しばらく立ち止まって姿を探したが・・・見つからない。

花弁が落ちた後の花盤は蜜を分泌する(白っぽいのが蕾)

午後は雨の確率が高いと云う事なので、参院選を早めに済ませ、そのままフィールドへ
河原のグランドは日曜とあってGGの大会らしく人と車であふれている。
カラタチに絡みついた『ノブドウ』の蕾の集まりはいつ見ても蕾のままの様に見える。しかし近づいてよく見ると蕾と開花したものが混在している。
花弁は開花後間もなく落ちてしまい、蕾とほぼ同じ位の基部だけ残るのでいつまでも蕾のままの様に見えるようだ。ただ色は少し黄みを帯びるのでよく見るとわかる。
土手の草むらで「チョン、ギース」「チョン、ギース」と早くもキリギリスが鳴き始めた。しばらく立ち止まって姿を探したが・・・見つからない。

タグ :植物
2010年07月11日 Posted by 松ぽっくり at 13:37 │Comments(0) │フィールド
色が淡い
マルバツユクサ
雄しべは6本あるが3本は短く1本が中ぐらい2本が長い、
ナスがいくつもぶら下がっている畑の横に『マルバツユクサ』がひとむら花を付けていた。
花は「ツユクサ」より小さめで花弁の色も淡い。葉は幅が広く丸みを帯び、
ヘリが波打つなどの点で見分けられる。そしてマルバツユクサは土中に閉鎖花を作る事でも知られています。
ツユクサ程何処にでも有るわけではないが、畑のそばなどで出会う事は意外と多い。
関東以西~沖縄、小笠原、アジア~アフリカの熱帯まで分布しているようです。
前線が南に下がって梅雨の晴れ間。午前中に一回りしてきたが汗もかかず、気持ちがよかった。

雄しべは6本あるが3本は短く1本が中ぐらい2本が長い、

ナスがいくつもぶら下がっている畑の横に『マルバツユクサ』がひとむら花を付けていた。
花は「ツユクサ」より小さめで花弁の色も淡い。葉は幅が広く丸みを帯び、
ヘリが波打つなどの点で見分けられる。そしてマルバツユクサは土中に閉鎖花を作る事でも知られています。
ツユクサ程何処にでも有るわけではないが、畑のそばなどで出会う事は意外と多い。
関東以西~沖縄、小笠原、アジア~アフリカの熱帯まで分布しているようです。
前線が南に下がって梅雨の晴れ間。午前中に一回りしてきたが汗もかかず、気持ちがよかった。
タグ :植物