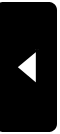メインフラワーの
カワラナデシコ
ナデシコ科は花弁の先が裂けるものが多い
意外と風がサラッとしていて気持がいい日です。
フィールドのメインフラワーのひとつ『カワラナデシコ』が咲き始めました。
去年も一日違いの7日に取り上げていますので、寸分違わず開花した事になります。
異常気象?かどうか、他の花が遅かったり早かったりする中、きっちり同季に開花するこの花は日の長さを基準にしているのでしょうか?
天気予報は と
と のマークがズラッと並んでいます、梅雨明けはいつになる事やら
のマークがズラッと並んでいます、梅雨明けはいつになる事やら

ナデシコ科は花弁の先が裂けるものが多い

意外と風がサラッとしていて気持がいい日です。
フィールドのメインフラワーのひとつ『カワラナデシコ』が咲き始めました。
去年も一日違いの7日に取り上げていますので、寸分違わず開花した事になります。
異常気象?かどうか、他の花が遅かったり早かったりする中、きっちり同季に開花するこの花は日の長さを基準にしているのでしょうか?
天気予報は
 と
と のマークがズラッと並んでいます、梅雨明けはいつになる事やら
のマークがズラッと並んでいます、梅雨明けはいつになる事やら
タグ :植物
2010年07月08日 Posted by 松ぽっくり at 17:55 │Comments(0) │フィールド
離れていて
ヒメガマ
上下の穂が離れているのが確認できます。
今日は小暑 『梅雨も明け本格的な暑さが始まる頃』と云う事に24節気ではなっているが暑さはすでに本格的?そして梅雨明けはまだ先が見えてこない。
水路の横にある小さな水たまりの『ヒメガマ』がソーセージの様な穂を付けました。
ガマやコガマは上に付く雄花の穂と下の雌花の穂がくっ付いていますが、ヒメガマは少し離れていて見分けられます。
ガマに比べると葉は細く、細い分丈夫で堅い。
花粉を乾燥させたものを漢方で「蒲黄」と呼び、止血剤や利尿剤として使われる。
「因幡の白ウサギ」もこれで傷を癒したとされる。

上下の穂が離れているのが確認できます。

今日は小暑 『梅雨も明け本格的な暑さが始まる頃』と云う事に24節気ではなっているが暑さはすでに本格的?そして梅雨明けはまだ先が見えてこない。
水路の横にある小さな水たまりの『ヒメガマ』がソーセージの様な穂を付けました。
ガマやコガマは上に付く雄花の穂と下の雌花の穂がくっ付いていますが、ヒメガマは少し離れていて見分けられます。
ガマに比べると葉は細く、細い分丈夫で堅い。
花粉を乾燥させたものを漢方で「蒲黄」と呼び、止血剤や利尿剤として使われる。
「因幡の白ウサギ」もこれで傷を癒したとされる。
タグ :植物
2010年07月07日 Posted by 松ぽっくり at 18:27 │Comments(0) │フィールド
新規参入
ワルナスビ

バナナの様な葯と葉裏の刺が、
一時の雨も上がり晴れ間ものぞく昼下がり、水路側の土手の斜面に去年は未確認の
『ワルナスビ』が新規参入していました。
驚異的繁殖力をもつ北アメリカ原産のこの草はしばしば畑地や草地に入り込んで問題を起こしている。
全体に刺が多く、葉の裏にまで有るのでうっかり掴むと痛い思いをする。
花はアップで見ると小さな「バナナ」の様な葯が可愛いのだが・・・
水路のアシの葉陰に「ハグロトンボ」が休んでいました。


バナナの様な葯と葉裏の刺が、

一時の雨も上がり晴れ間ものぞく昼下がり、水路側の土手の斜面に去年は未確認の
『ワルナスビ』が新規参入していました。

驚異的繁殖力をもつ北アメリカ原産のこの草はしばしば畑地や草地に入り込んで問題を起こしている。
全体に刺が多く、葉の裏にまで有るのでうっかり掴むと痛い思いをする。
花はアップで見ると小さな「バナナ」の様な葯が可愛いのだが・・・

水路のアシの葉陰に「ハグロトンボ」が休んでいました。

タグ :自然
2010年07月06日 Posted by 松ぽっくり at 17:49 │Comments(0) │フィールド
ゆり動く
ヤマユリ

お地蔵さんの下、生茂った木々の元の薄暗い斜面に今年も『ヤマユリ』が咲いた。
周囲の草や笹の圧力で少々いびつな形ではあるが・・・。
野の花として、際立つ大輪と強い芳香は「荘厳」と云う花言葉に説得力を持たせるのに十分だ。
明治6年オーストリアの万国博に展示されるとヨーロッパの人々はその迫力に驚嘆したと云う。
和名は山に生える百合で「山百合」そのユリの意味は茎の割に花が大きく、ゆり動く事に由来するらしい。

お地蔵さんの下、生茂った木々の元の薄暗い斜面に今年も『ヤマユリ』が咲いた。
周囲の草や笹の圧力で少々いびつな形ではあるが・・・。
野の花として、際立つ大輪と強い芳香は「荘厳」と云う花言葉に説得力を持たせるのに十分だ。
明治6年オーストリアの万国博に展示されるとヨーロッパの人々はその迫力に驚嘆したと云う。
和名は山に生える百合で「山百合」そのユリの意味は茎の割に花が大きく、ゆり動く事に由来するらしい。

タグ :植物
2010年07月05日 Posted by 松ぽっくり at 17:16 │Comments(2) │フィールド
異形
ハナイカダ

昨夜のひどい雨はきれいに上がって青空ものぞく様になったが、その分暑さと湿度は半端無い。

そんな中、仲間と山道を彷徨しました。
山肌にマタタビの白い葉が目を引き、林縁では『ハナイカダ』の実が黒く色付き始めていました。
「ハナイカダ」は若芽を山菜として利用したり、茶花に用いたり生活色豊かな植物で
ヨメノナミダ、イボナ、ママコナなど方言名も多いようです。
県内で云われる「ツキンダシ」は木の髄を突き出して、灯心に使った事によるもの。
それにしても葉の上に花や果実がチョコンと乗った異形は一度見たら忘れません。

昨夜のひどい雨はきれいに上がって青空ものぞく様になったが、その分暑さと湿度は半端無い。


そんな中、仲間と山道を彷徨しました。
山肌にマタタビの白い葉が目を引き、林縁では『ハナイカダ』の実が黒く色付き始めていました。
「ハナイカダ」は若芽を山菜として利用したり、茶花に用いたり生活色豊かな植物で
ヨメノナミダ、イボナ、ママコナなど方言名も多いようです。
県内で云われる「ツキンダシ」は木の髄を突き出して、灯心に使った事によるもの。
それにしても葉の上に花や果実がチョコンと乗った異形は一度見たら忘れません。

タグ :植物
2010年07月04日 Posted by 松ぽっくり at 23:15 │Comments(0) │下見
西部に
ヌマトラノオ

今日はタイミングがずれて外に出そびれてしまいましたので、昨日湿地で出会った
『ヌマトラノオ』を取り上げます。
沼や湿った草地が好きで、地下茎で殖えるので群生する事が多く、県内ではどちらかと云うと西部に多いようです。
花の作りは「オカトラノオ」とよく似ていますが、花序は直立して虎の尾状にはなりません。
和名は「沼虎の尾」となり、茶花にも用いられるようです。

今日はタイミングがずれて外に出そびれてしまいましたので、昨日湿地で出会った
『ヌマトラノオ』を取り上げます。
沼や湿った草地が好きで、地下茎で殖えるので群生する事が多く、県内ではどちらかと云うと西部に多いようです。
花の作りは「オカトラノオ」とよく似ていますが、花序は直立して虎の尾状にはなりません。
和名は「沼虎の尾」となり、茶花にも用いられるようです。
タグ :植物
2010年07月03日 Posted by 松ぽっくり at 17:57 │Comments(0) │花見
11日目
ハンゲショウ

花序は初め垂れているが花弁の無い花が下から咲き上がると真直ぐになる

夏至から数えて11日目、今日は「半夏生」
そんな訳でドクダミ科の『ハンゲショウ』を見に行って来ました。
名前の由来は「半夏生」の頃、葉が白くなるから。あるいは葉が全部白くならないので「半化粧」の意味と云う説も有ります。
水辺や湿地に生え根茎は泥の中を横に這って広がり、高さは1m程になる。
蕾が出始めると上部の葉、2~3枚が白くなり始め、そして盛夏には緑に戻る。
古名は「片白草」でこちらも白くなる葉からの命名のようです。
それにしても湿地は蒸し暑く、汗が目にしみました。

花序は初め垂れているが花弁の無い花が下から咲き上がると真直ぐになる

夏至から数えて11日目、今日は「半夏生」
そんな訳でドクダミ科の『ハンゲショウ』を見に行って来ました。
名前の由来は「半夏生」の頃、葉が白くなるから。あるいは葉が全部白くならないので「半化粧」の意味と云う説も有ります。
水辺や湿地に生え根茎は泥の中を横に這って広がり、高さは1m程になる。
蕾が出始めると上部の葉、2~3枚が白くなり始め、そして盛夏には緑に戻る。
古名は「片白草」でこちらも白くなる葉からの命名のようです。
それにしても湿地は蒸し暑く、汗が目にしみました。
タグ :植物
2010年07月02日 Posted by 松ぽっくり at 17:50 │Comments(2) │花見
ほぼ直立
エゾミソハギ
ガクの先の付属体がまっすぐ立っている。

整然と並ぶ早苗、きれいに草取りの済んだ畦に『エゾミソハギ』の花が目を引く。
名前に「エゾ」と付いているが、日本全土の「ミソハギ」と同じような所に生えている。
ミソハギに比べ全体に毛が多く、ガクの付属体は開出せずにほぼ直立する。そして葉の基部は茎を抱くような感じになる。などの点で識別できる。
いよいよ7月に入り、今年も半分終わった。云いたくは無いがこのスピードは何とかならないものだろうか!

ガクの先の付属体がまっすぐ立っている。

整然と並ぶ早苗、きれいに草取りの済んだ畦に『エゾミソハギ』の花が目を引く。
名前に「エゾ」と付いているが、日本全土の「ミソハギ」と同じような所に生えている。
ミソハギに比べ全体に毛が多く、ガクの付属体は開出せずにほぼ直立する。そして葉の基部は茎を抱くような感じになる。などの点で識別できる。
いよいよ7月に入り、今年も半分終わった。云いたくは無いがこのスピードは何とかならないものだろうか!
タグ :植物