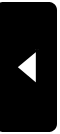初見!ヤツガシラ
こんな陽気のせいで土手のソメイヨシノはほぼ満開をまだ保っています。
土手を下りて茶畑の横を行くと足元から縞模様の大き目の鳥が飛び立って10㍍程先、まだ新芽が出始めたばかりのエノキの枝にとまりました。エッ『ヤツガシラ』!
こちらを見ながら、頭の冠羽を開いたり閉じたりしています。まさしく「ヤツガシラ」です。
これは何としても証拠写真を撮らなくては、しかし手元にあるのはコンデジのみ、う~ん
近づきたいのは山々ですが、他の鳥の時も何度も飛び立たれているので安易に動けません。
ゆっくりとあまり目を合わせない様にして1㍍程近づいてなんとか種名が解りそうな画像が・・・この写真では頭の冠羽を閉じていますが、これを開くと『ヤツガシラ』の名前が何となく腑に落ちます。
この鳥はユーラシア大陸やアフリカなどに分布して、日本ではおもに春と秋、旅鳥として時々観察されています。
ちょっと緊張した一瞬でした。
 ヤツガシラ
ヤツガシラ
土手を下りて茶畑の横を行くと足元から縞模様の大き目の鳥が飛び立って10㍍程先、まだ新芽が出始めたばかりのエノキの枝にとまりました。エッ『ヤツガシラ』!

こちらを見ながら、頭の冠羽を開いたり閉じたりしています。まさしく「ヤツガシラ」です。
これは何としても証拠写真を撮らなくては、しかし手元にあるのはコンデジのみ、う~ん

近づきたいのは山々ですが、他の鳥の時も何度も飛び立たれているので安易に動けません。

ゆっくりとあまり目を合わせない様にして1㍍程近づいてなんとか種名が解りそうな画像が・・・この写真では頭の冠羽を閉じていますが、これを開くと『ヤツガシラ』の名前が何となく腑に落ちます。
この鳥はユーラシア大陸やアフリカなどに分布して、日本ではおもに春と秋、旅鳥として時々観察されています。
ちょっと緊張した一瞬でした。
 ヤツガシラ
ヤツガシラ タグ :野鳥
2010年04月09日 Posted by 松ぽっくり at 16:13 │Comments(4) │フィールド
銀色の
予想に反して河原の風は強くない、ただその質は4月のものではなく厚めの上着が離せない。
河原の『アキグミ』の小さく地味な花が満開になった。数え切れない程の数でそばに寄ると説明の難しい香りがする。
葉や花柄などに銀色の鱗状毛が有るので、満開の花が咲いていると木全体が薄いクリーム色に見える。
グミ属は根粒菌によって空気中の窒素を固定出来るので、荒れた地でも生育出来るようです。
さて今年は無事に秋、実を付ける事が出来るでしょうか?
アキグミ


銀色の鱗状毛で葉が白っぽく見えます。

河原の『アキグミ』の小さく地味な花が満開になった。数え切れない程の数でそばに寄ると説明の難しい香りがする。

葉や花柄などに銀色の鱗状毛が有るので、満開の花が咲いていると木全体が薄いクリーム色に見える。
グミ属は根粒菌によって空気中の窒素を固定出来るので、荒れた地でも生育出来るようです。
さて今年は無事に秋、実を付ける事が出来るでしょうか?
アキグミ


銀色の鱗状毛で葉が白っぽく見えます。
タグ :植物
2010年04月08日 Posted by 松ぽっくり at 16:33 │Comments(0) │フィールド
ミカン科の
所用で帰りが遅くなり、フィールドに行けませんでした。
そんな訳で昨日浜石で見たミカン科の『ミヤマシキミ』を取り上げて見ました。
低山の林内に生える常緑の低木で高さは1.5㍍程にしかならず、雌雄別株です。
名前は「シキミ」に似ていて山にあるので「深山樒」となったようです。
葉にアルカロイドを含み有毒ですが、傷つけると花と共に良い香りがします。
写真は雄株の方です。
ミヤマシキミ


雄花の集まり、4本の雄しべが確認できます。
そんな訳で昨日浜石で見たミカン科の『ミヤマシキミ』を取り上げて見ました。

低山の林内に生える常緑の低木で高さは1.5㍍程にしかならず、雌雄別株です。
名前は「シキミ」に似ていて山にあるので「深山樒」となったようです。
葉にアルカロイドを含み有毒ですが、傷つけると花と共に良い香りがします。
写真は雄株の方です。

ミヤマシキミ


雄花の集まり、4本の雄しべが確認できます。
タグ :植物
2010年04月07日 Posted by 松ぽっくり at 22:11 │Comments(0) │下見
由比、浜石
今日は由比の浜石へ行って来ました。
昼食に「サクラエビのかきあげ」蕎麦なんぞをいただいてから出発です。
空模様は予報と大違い、雲がかなり厚く浜石の頂上に至ってはガスが出て肌寒ささえ感じる程でした。
今年は天候が不順だったようでクロモジやキブシの花芽や葉芽が寒さにやられて枝先にその躯をさらしていました。
草達も少し遅いように思われます。その中でスミレは7種を数え「タチツボスミレ」「ナガバノスミレサイシン」の個体数はかなり多く確認出来ました。

ナガバノスミレサイシン、花のうしろ(距)が丸くなっているのがスミレサイシンの仲間の特徴です。
昼食に「サクラエビのかきあげ」蕎麦なんぞをいただいてから出発です。

空模様は予報と大違い、雲がかなり厚く浜石の頂上に至ってはガスが出て肌寒ささえ感じる程でした。

今年は天候が不順だったようでクロモジやキブシの花芽や葉芽が寒さにやられて枝先にその躯をさらしていました。

草達も少し遅いように思われます。その中でスミレは7種を数え「タチツボスミレ」「ナガバノスミレサイシン」の個体数はかなり多く確認出来ました。


ナガバノスミレサイシン、花のうしろ(距)が丸くなっているのがスミレサイシンの仲間の特徴です。
タグ :植物
2010年04月06日 Posted by 松ぽっくり at 21:53 │Comments(2) │下見
春の陽に
雨の一日、
先日(4/3)『イタドリ』の若葉が春の陽に透けて見事な色合いを見せていました。
新芽はどれもみずみずしくて可愛いものですが、殊更美しかった。
光は万能の演出家です、若葉にしても紅葉にしても・・・ただそれをそのまま表現出来ない未熟さが残念です
明日は回復して気温も上がりそうです。仲間と浜石へ行って来ます。 イタドリ若葉

先日(4/3)『イタドリ』の若葉が春の陽に透けて見事な色合いを見せていました。

新芽はどれもみずみずしくて可愛いものですが、殊更美しかった。
光は万能の演出家です、若葉にしても紅葉にしても・・・ただそれをそのまま表現出来ない未熟さが残念です

明日は回復して気温も上がりそうです。仲間と浜石へ行って来ます。 イタドリ若葉

タグ :植物
2010年04月05日 Posted by 松ぽっくり at 18:05 │Comments(2) │フィールド
何段にも
諸岡山と河原の接する所、アラカシ、ヤマザクラ、タブノキ、ヤナギ等が混生する小さな河原林が有る。
その中にある『イヌシデ』はあらゆる蔓(フジ、ツルウメモドキ、アケビ、フユヅタ等)に絡まり着かれて苦渋の様相を呈しているが今年も花を付けた。
雄花は何段にも重なってぶら下がり、雌花は少し遅れて枝先に葉と一緒に出るが花には見えない。
「犬四手」の名前は果穂の形が、しめ縄などに付ける「四手」に似ているという事で付けられました。
土手の桜は満開、行く先々で花見の宴が開かれていた。
イヌシデ

イヌシデ雄花 ↓

イヌシデ雌花 ↓

その中にある『イヌシデ』はあらゆる蔓(フジ、ツルウメモドキ、アケビ、フユヅタ等)に絡まり着かれて苦渋の様相を呈しているが今年も花を付けた。
雄花は何段にも重なってぶら下がり、雌花は少し遅れて枝先に葉と一緒に出るが花には見えない。
「犬四手」の名前は果穂の形が、しめ縄などに付ける「四手」に似ているという事で付けられました。

土手の桜は満開、行く先々で花見の宴が開かれていた。
イヌシデ

イヌシデ雄花 ↓

イヌシデ雌花 ↓

タグ :植物
2010年04月04日 Posted by 松ぽっくり at 17:12 │Comments(2) │フィールド
かすり傷が
時折の強風に絡まり合った枝をゆすりながら今年も『カラタチ』の花が咲きました。
花は先日の嵐で出来たと思しきかすり傷が目立つ。被写体用に傷の無いものを探して見たが皆無だった。
この花をみるといつも写実画の様な白秋の詩が頭に浮かびます。

からたちの花が咲いたよ。白い白い花が咲いたよ。
からたちのとげは痛いよ。青い青いとげだよ。
からたちは畑の垣根よ。いつもいつもとほる道だよ。

この刺が防犯に役立ったとは思いかねるが、昔はよく生垣に使われたようだ。
花は先日の嵐で出来たと思しきかすり傷が目立つ。被写体用に傷の無いものを探して見たが皆無だった。
この花をみるといつも写実画の様な白秋の詩が頭に浮かびます。

からたちの花が咲いたよ。白い白い花が咲いたよ。
からたちのとげは痛いよ。青い青いとげだよ。
からたちは畑の垣根よ。いつもいつもとほる道だよ。

この刺が防犯に役立ったとは思いかねるが、昔はよく生垣に使われたようだ。
タグ :植物
2010年04月03日 Posted by 松ぽっくり at 17:13 │Comments(0) │フィールド
低木に
春の嵐が足早に去った後、川は濁流となって音を立てている。
水路の脇とか河原の藪などで『クサイチゴ』の白い花が目立つようになった。野の花にしては割と大きい花です。
名前に「クサ」と付いていますが、バラ科の低木に区分されます。
昨年の5月頃、赤くて甘いイチゴを何度も味わったのを思い出します。刺が有りますので焦って手を出すと痛い目に合います。
土手の下の四方八方から丸見えのカラスの巣、昨夜の暴風にも耐えて親鳥は座り続けている。
クサイチゴ


水路の脇とか河原の藪などで『クサイチゴ』の白い花が目立つようになった。野の花にしては割と大きい花です。
名前に「クサ」と付いていますが、バラ科の低木に区分されます。
昨年の5月頃、赤くて甘いイチゴを何度も味わったのを思い出します。刺が有りますので焦って手を出すと痛い目に合います。
土手の下の四方八方から丸見えのカラスの巣、昨夜の暴風にも耐えて親鳥は座り続けている。
クサイチゴ


タグ :植物
2010年04月02日 Posted by 松ぽっくり at 15:49 │Comments(0) │フィールド
銀色を帯びて
新年度も朝から雨、したがってフィールドはお休みです。
そこで3/30に水路の脇で出会った『ナツグミ』の花を取り上げます。
この木は昨年、実が付いたときにアップしたものです。
グミの仲間の特徴ですが、全体に「鱗状毛」や「星状毛」と呼ばれる変わった毛?が有ります。そのため葉が銀色を帯びて見えます(ナツグミの場合は葉裏が)
夏に実がなるから「ナツグミ」と云う事になっていますが、5月の末にはもう色付き始めます。細かい事を言わせてもらえば「初夏グミ」と云う所でしょうか。
河原の「アキグミ」はまだ蕾です。こちらは若葉と蕾で木全体が白っぽく見えています。
どうやら明日も一日雨のようです
ナツグミ


そこで3/30に水路の脇で出会った『ナツグミ』の花を取り上げます。
この木は昨年、実が付いたときにアップしたものです。
グミの仲間の特徴ですが、全体に「鱗状毛」や「星状毛」と呼ばれる変わった毛?が有ります。そのため葉が銀色を帯びて見えます(ナツグミの場合は葉裏が)
夏に実がなるから「ナツグミ」と云う事になっていますが、5月の末にはもう色付き始めます。細かい事を言わせてもらえば「初夏グミ」と云う所でしょうか。

河原の「アキグミ」はまだ蕾です。こちらは若葉と蕾で木全体が白っぽく見えています。
どうやら明日も一日雨のようです

ナツグミ


タグ :植物