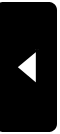クヌギ林の
ニリンソウ
仲間と池の周囲を歩いて来ました。クヌギ林の下で『ニリンソウ』が咲き始めていました。この花も今年は少し遅れているようです。
「二輪草」の名前からは2つ一緒に花が咲くように思われがちですが、先に1個が咲いて少し遅れて2つ目が咲き、ここで2つ並んで「二輪草」となります。ただ2個以上の事もたまに有ります。
そして似た植物には花が1個の「一輪草」、花が3個の「三輪草」も存在します。
本日も快晴、この所しばらく雨がなく、どこもかしこも乾ききって一雨ほしい所です。

仲間と池の周囲を歩いて来ました。クヌギ林の下で『ニリンソウ』が咲き始めていました。この花も今年は少し遅れているようです。
「二輪草」の名前からは2つ一緒に花が咲くように思われがちですが、先に1個が咲いて少し遅れて2つ目が咲き、ここで2つ並んで「二輪草」となります。ただ2個以上の事もたまに有ります。
そして似た植物には花が1個の「一輪草」、花が3個の「三輪草」も存在します。
本日も快晴、この所しばらく雨がなく、どこもかしこも乾ききって一雨ほしい所です。
タグ :植物
2011年04月06日 Posted by 松ぽっくり at 23:48 │Comments(0) │下見
野性化
ツタバウンラン
出先の道端で『ツタバウンラン』が小さな花を沢山付けて目を引いていました。
地中海原産のこの草は大正時代に鑑賞用として入ったものが逃げ出して野生化したようです。
丸い果実には長い柄が有って暗い所に向かって延びる性質が有るので、石垣の隙間や側溝の隙間などでよく生え出します。
本日は24節季の「清明」草木の花が咲き始め、万物に清朗の気が溢れて来る頃とか。
はたして今日の天気図は日本列島北から南までお日様マークが並び、お堀の桜も咲き始めていました。

出先の道端で『ツタバウンラン』が小さな花を沢山付けて目を引いていました。
地中海原産のこの草は大正時代に鑑賞用として入ったものが逃げ出して野生化したようです。
丸い果実には長い柄が有って暗い所に向かって延びる性質が有るので、石垣の隙間や側溝の隙間などでよく生え出します。
本日は24節季の「清明」草木の花が咲き始め、万物に清朗の気が溢れて来る頃とか。
はたして今日の天気図は日本列島北から南までお日様マークが並び、お堀の桜も咲き始めていました。
タグ :植物
2011年04月05日 Posted by 松ぽっくり at 17:36 │Comments(0) │出先で
釣り糸を
ウラシマソウ
それ程気温は低い訳ではないが今ひとつ春の暖かさが実感出来ない。
それでも土手の「ソメイヨシノ」はチラホラ咲き始め、お地蔵さん下の藪では「ヤマブキ」も蕾をほどき始めた。
『ウラシマソウ』は昨年に比べると、10日程遅れたがその釣り糸を延ばしています。このムチ状のものは苞の中にある花の付属体で、長いものは50㌢にもなります。
これを浦島太郎の釣り糸にたとえて「浦島草」の名が付きました。それにしても何のためにこんなに長く延ばす必要があったのでしょう???

それ程気温は低い訳ではないが今ひとつ春の暖かさが実感出来ない。
それでも土手の「ソメイヨシノ」はチラホラ咲き始め、お地蔵さん下の藪では「ヤマブキ」も蕾をほどき始めた。
『ウラシマソウ』は昨年に比べると、10日程遅れたがその釣り糸を延ばしています。このムチ状のものは苞の中にある花の付属体で、長いものは50㌢にもなります。
これを浦島太郎の釣り糸にたとえて「浦島草」の名が付きました。それにしても何のためにこんなに長く延ばす必要があったのでしょう???
タグ :植物
2011年04月04日 Posted by 松ぽっくり at 17:54 │Comments(0) │フィールド
アルカロイドを含み
ハシリドコロ
昨日は仲間と『ハシリドコロ』を確認しに行って来ました。何年か前、沢筋の斜面に群生している所を見ていますが、そのまま残っているか多少心配しながらの出発です。
例年の30%にも満たないと云う少雨で最初の沢筋はほとんど水が無く、地表の緑もまばらで心配がつのります。それでも少し下った沢に行くと此処は多少流れが有り、お目当ての「ハシリドコロ」が水々しい緑を見せています。花は丁度咲き始めた所の様で数は多く有りませんが、取りあえず見る事が出来ました。
この一風変わった名前は、地下茎に数種のアルカロイドを含み、誤って食べると苦しさのあまり走り回る事から付けられたと云われています。しかしこの毒も使いようによっては薬となり「ロート目薬」とか「ロート胃腸薬」などはこの毒から抽出した薬です。
周囲を見渡すと「アブラチャン」「ダンコウバイ」「バッコヤナギ」「ミツマタ」「クロモジ」などが控えめな花を付けて山の春を演出していました。
ミツマタ

昨日は仲間と『ハシリドコロ』を確認しに行って来ました。何年か前、沢筋の斜面に群生している所を見ていますが、そのまま残っているか多少心配しながらの出発です。
例年の30%にも満たないと云う少雨で最初の沢筋はほとんど水が無く、地表の緑もまばらで心配がつのります。それでも少し下った沢に行くと此処は多少流れが有り、お目当ての「ハシリドコロ」が水々しい緑を見せています。花は丁度咲き始めた所の様で数は多く有りませんが、取りあえず見る事が出来ました。

この一風変わった名前は、地下茎に数種のアルカロイドを含み、誤って食べると苦しさのあまり走り回る事から付けられたと云われています。しかしこの毒も使いようによっては薬となり「ロート目薬」とか「ロート胃腸薬」などはこの毒から抽出した薬です。
周囲を見渡すと「アブラチャン」「ダンコウバイ」「バッコヤナギ」「ミツマタ」「クロモジ」などが控えめな花を付けて山の春を演出していました。

ミツマタ

タグ :植物
2011年04月03日 Posted by 松ぽっくり at 16:17 │Comments(0) │花を訪ねて
日本的で
スミレ

4月に入ったからと云う訳では無いだろうが、土手の斜面で急に『スミレ』が目立つようになった。
私達が「スミレ」と云う名前を聞いて思い浮かべるのは、濃い紫色の花とヘラ型の葉を持ったこのスミレでは無いでしょうか?その姿形はどことなく日本的で、日本特産の様な気さえします。しかし分布の中心は大陸で、日本はその一部でしか有りません。
それでは日本で一番目に付くスミレは?と云うと「タチツボスミレ」の様です。タチツボスミレは中国や済州島、台湾などにも分布するものの、分布の中心は日本列島で、海岸近くの道端から亜高山まで広く見る事が出来ます。


4月に入ったからと云う訳では無いだろうが、土手の斜面で急に『スミレ』が目立つようになった。
私達が「スミレ」と云う名前を聞いて思い浮かべるのは、濃い紫色の花とヘラ型の葉を持ったこのスミレでは無いでしょうか?その姿形はどことなく日本的で、日本特産の様な気さえします。しかし分布の中心は大陸で、日本はその一部でしか有りません。
それでは日本で一番目に付くスミレは?と云うと「タチツボスミレ」の様です。タチツボスミレは中国や済州島、台湾などにも分布するものの、分布の中心は日本列島で、海岸近くの道端から亜高山まで広く見る事が出来ます。
タグ :植物