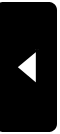腺毛が
ミヤマウグイスカグラ 各部に腺毛が多い

花の基部の腺毛が確認できます
好天、行楽日和、と云う訳でもありませんが、河口湖の近くに行って来ました。
さすがGW、すごい車の数です、大幅に予定が狂い12時過ぎにやっと目的地に付きました
そしてその目的地も観光化が進み、10数年前の豊かな植相は大分失われておりました。
それでもスミレが数種、ハイキングコース沿いにポツポツと咲き、今回の目的の一つで有った『ミヤマウグイスカグラ』の花もなんとか少しだけ見る事が出来ました。
名前は「深山鶯神楽」と書くようですが、その由来はよく解っていません。
外人観光客も多く、富士山はひたすら輝いていました。


花の基部の腺毛が確認できます

好天、行楽日和、と云う訳でもありませんが、河口湖の近くに行って来ました。
さすがGW、すごい車の数です、大幅に予定が狂い12時過ぎにやっと目的地に付きました

そしてその目的地も観光化が進み、10数年前の豊かな植相は大分失われておりました。

それでもスミレが数種、ハイキングコース沿いにポツポツと咲き、今回の目的の一つで有った『ミヤマウグイスカグラ』の花もなんとか少しだけ見る事が出来ました。

名前は「深山鶯神楽」と書くようですが、その由来はよく解っていません。
外人観光客も多く、富士山はひたすら輝いていました。

2010年05月01日 Posted by 松ぽっくり at 22:16 │Comments(0) │下見
浜石、スミレ③
ヒゴスミレ

まー風の冷たい事!寒さに怖気づいてフィールドは止めました。
と云う事で、浜石のスミレその③にさせて頂きます。
とかく識別の難しいスミレの中にあって、『ヒゴスミレ』は比較的楽に見分ける事が出来ると思います。画像で分かる様に葉が非常に細かく切れ込んでいるので、葉さえ有れば「ヒゴスミレ」と分かります。
他に葉の切れ込むスミレは「エイザンスミレ」が有りますが、ここまで細かく有りません。
それと花の色が、エイザンは紅みを帯びますが、ヒゴスミレはどちらかと云うと花の中心が黄色みを帯びます。
昔から浜石はスミレで名が通っていますが、芝広場から野外センターまでの林道沿いに見ただけですが10種を確認出来ました

まー風の冷たい事!寒さに怖気づいてフィールドは止めました。

と云う事で、浜石のスミレその③にさせて頂きます。
とかく識別の難しいスミレの中にあって、『ヒゴスミレ』は比較的楽に見分ける事が出来ると思います。画像で分かる様に葉が非常に細かく切れ込んでいるので、葉さえ有れば「ヒゴスミレ」と分かります。

他に葉の切れ込むスミレは「エイザンスミレ」が有りますが、ここまで細かく有りません。
それと花の色が、エイザンは紅みを帯びますが、ヒゴスミレはどちらかと云うと花の中心が黄色みを帯びます。

昔から浜石はスミレで名が通っていますが、芝広場から野外センターまでの林道沿いに見ただけですが10種を確認出来ました

タグ :植物
2010年04月16日 Posted by 松ぽっくり at 16:46 │Comments(0) │下見
ハイセンスな
フモトスミレ、斑入りタイプ

4月も半ばと云うのにまたまた寒さがぶり返して、厚手の上着が中々しまえません。
本日はフィールドに行けませんでしたので、先日浜石で出会った『フモトスミレ』を取り上げます。小型ですが端正な顔立ちの私の好きなスミレです。
名前は「フモト」ですが、海岸近くの山地から2000㍍付近の高原まで広く見る事が出来ます。
スミレのプロに「地味ながらもハイセンスな逸品 」と言わしめたスミレです。
」と言わしめたスミレです。
ただ、生えている場所によっても個体差が有りますので容姿のすぐれた個体にいつも会えるとは限りません。
明日は更に寒くなるらしい

4月も半ばと云うのにまたまた寒さがぶり返して、厚手の上着が中々しまえません。

本日はフィールドに行けませんでしたので、先日浜石で出会った『フモトスミレ』を取り上げます。小型ですが端正な顔立ちの私の好きなスミレです。

名前は「フモト」ですが、海岸近くの山地から2000㍍付近の高原まで広く見る事が出来ます。
スミレのプロに「地味ながらもハイセンスな逸品
 」と言わしめたスミレです。
」と言わしめたスミレです。ただ、生えている場所によっても個体差が有りますので容姿のすぐれた個体にいつも会えるとは限りません。

明日は更に寒くなるらしい

タグ :植物
2010年04月15日 Posted by 松ぽっくり at 16:40 │Comments(0) │下見
ミカン科の
所用で帰りが遅くなり、フィールドに行けませんでした。
そんな訳で昨日浜石で見たミカン科の『ミヤマシキミ』を取り上げて見ました。
低山の林内に生える常緑の低木で高さは1.5㍍程にしかならず、雌雄別株です。
名前は「シキミ」に似ていて山にあるので「深山樒」となったようです。
葉にアルカロイドを含み有毒ですが、傷つけると花と共に良い香りがします。
写真は雄株の方です。
ミヤマシキミ


雄花の集まり、4本の雄しべが確認できます。
そんな訳で昨日浜石で見たミカン科の『ミヤマシキミ』を取り上げて見ました。

低山の林内に生える常緑の低木で高さは1.5㍍程にしかならず、雌雄別株です。
名前は「シキミ」に似ていて山にあるので「深山樒」となったようです。
葉にアルカロイドを含み有毒ですが、傷つけると花と共に良い香りがします。
写真は雄株の方です。

ミヤマシキミ


雄花の集まり、4本の雄しべが確認できます。
タグ :植物
2010年04月07日 Posted by 松ぽっくり at 22:11 │Comments(0) │下見
由比、浜石
今日は由比の浜石へ行って来ました。
昼食に「サクラエビのかきあげ」蕎麦なんぞをいただいてから出発です。
空模様は予報と大違い、雲がかなり厚く浜石の頂上に至ってはガスが出て肌寒ささえ感じる程でした。
今年は天候が不順だったようでクロモジやキブシの花芽や葉芽が寒さにやられて枝先にその躯をさらしていました。
草達も少し遅いように思われます。その中でスミレは7種を数え「タチツボスミレ」「ナガバノスミレサイシン」の個体数はかなり多く確認出来ました。

ナガバノスミレサイシン、花のうしろ(距)が丸くなっているのがスミレサイシンの仲間の特徴です。
昼食に「サクラエビのかきあげ」蕎麦なんぞをいただいてから出発です。

空模様は予報と大違い、雲がかなり厚く浜石の頂上に至ってはガスが出て肌寒ささえ感じる程でした。

今年は天候が不順だったようでクロモジやキブシの花芽や葉芽が寒さにやられて枝先にその躯をさらしていました。

草達も少し遅いように思われます。その中でスミレは7種を数え「タチツボスミレ」「ナガバノスミレサイシン」の個体数はかなり多く確認出来ました。


ナガバノスミレサイシン、花のうしろ(距)が丸くなっているのがスミレサイシンの仲間の特徴です。
タグ :植物
2010年04月06日 Posted by 松ぽっくり at 21:53 │Comments(2) │下見
樹木園
友人と県立美術館に行って来ました。と言っても中には入らず周辺を歩いただけですが、
梅は少し咲き始め、一本だけある「マンサク」もよく見ると2,3咲き始めていました。
寒さも今日は落ち着いて、ぶらぶら歩きには好適です。
県立大学の薬用植物園温室裏の落ち葉の中からは「フキノトウ」が顔を出し、蕾が開き始めています。
隣設の樹木園では「シナマンサク」「ミツマタ」「オガタマノキ」などが咲き始め、「ムクロジ」の大木は数えきれないほどの実をぶら下げていました。ムクロジの果皮はサポニンを含み、良く泡立つので昔は洗濯や洗髪に使われたとの事。分布は西南日本が中心の様です。
久々に尋ねた美術館周辺、この季節としては思いの他Goodでした。
 ムクロジ
ムクロジ

ムクロジ実

梅は少し咲き始め、一本だけある「マンサク」もよく見ると2,3咲き始めていました。
寒さも今日は落ち着いて、ぶらぶら歩きには好適です。

県立大学の薬用植物園温室裏の落ち葉の中からは「フキノトウ」が顔を出し、蕾が開き始めています。
隣設の樹木園では「シナマンサク」「ミツマタ」「オガタマノキ」などが咲き始め、「ムクロジ」の大木は数えきれないほどの実をぶら下げていました。ムクロジの果皮はサポニンを含み、良く泡立つので昔は洗濯や洗髪に使われたとの事。分布は西南日本が中心の様です。
久々に尋ねた美術館周辺、この季節としては思いの他Goodでした。

 ムクロジ
ムクロジ
ムクロジ実
タグ :植物
2010年02月08日 Posted by 松ぽっくり at 20:07 │Comments(0) │下見
旅立ち間近
伊東の地震も葵区ではほとんど感じませんでした(震源が浅いせいでしょうか)
今日もフィールドに行けませんでしたので昨日小坂で撮った、旅立ち間近の『テイカカヅラ』の種子を載せてみました。
裂ける前の果実はよく目にするんですが、毛を付けた種が見える状態のものには中々出会えなくて、出会えても遠くだったりでしたが、やっと近くで撮れました。
この後大部分は風と共に飛んで行きました。
花は初夏の頃、少しねじれたような白い花を付けますが、芳香が有り優しい感じが愛されて江戸時代から栽培もされたようです。
今日も寒い一日でした。


裂ける前の果実(06,12、撮影)
今日もフィールドに行けませんでしたので昨日小坂で撮った、旅立ち間近の『テイカカヅラ』の種子を載せてみました。
裂ける前の果実はよく目にするんですが、毛を付けた種が見える状態のものには中々出会えなくて、出会えても遠くだったりでしたが、やっと近くで撮れました。

この後大部分は風と共に飛んで行きました。
花は初夏の頃、少しねじれたような白い花を付けますが、芳香が有り優しい感じが愛されて江戸時代から栽培もされたようです。
今日も寒い一日でした。


裂ける前の果実(06,12、撮影)
タグ :植物
2009年12月18日 Posted by 松ぽっくり at 18:30 │Comments(3) │下見
透き通るような
寒い一日でした。土曜日にかけて更に寒さが増すようです。
今日は撮りたいものが有って、先日行った小坂にもう一度行って来ました。
ついでに少し歩いてみると農道の脇に『ヒヨドリジョウゴ』の赤い実がぶら下がっていました。
透き通るような赤い実は花の少ないこの季節にアクセントを付けて、私たちを楽しませてくれます。
「鵯上戸」の名前はこの実を鵯が好んで食べるので付けられたと言われますが、まだ鵯が食べている所を見た事が有りません 。
。
全体に軟毛を密生しているので、同じような実を付ける「マルバノホロシ」などから識別できます。
「冬至10日前」の諺が有りますが、日暮れはまさしく「ツルベ落とし」です。
ヒヨドリジョウゴ


今日は撮りたいものが有って、先日行った小坂にもう一度行って来ました。
ついでに少し歩いてみると農道の脇に『ヒヨドリジョウゴ』の赤い実がぶら下がっていました。
透き通るような赤い実は花の少ないこの季節にアクセントを付けて、私たちを楽しませてくれます。
「鵯上戸」の名前はこの実を鵯が好んで食べるので付けられたと言われますが、まだ鵯が食べている所を見た事が有りません
 。
。全体に軟毛を密生しているので、同じような実を付ける「マルバノホロシ」などから識別できます。
「冬至10日前」の諺が有りますが、日暮れはまさしく「ツルベ落とし」です。
ヒヨドリジョウゴ

タグ :植物
2009年12月17日 Posted by 松ぽっくり at 22:26 │Comments(0) │下見
ウチワの様な翼
朝から雨、結局 巣ごもりの一日になってしまいました。
と云う事で今日は昨日小坂で見つけた『オトコエシ』の果実を取り上げてみました。
小さなソウ果の周りに付いているウチワの様な翼は小苞が大きくなったもので、散布に役立つようです。
「女郎花」と書くオミナエシに対しオトコエシは「男郎花」と書きます。オミナエシに比べ強く丈夫そうに見える事からそうなったようです。
春先のオトコエシは根元から匐枝を何本も出してその先に新苗を作り、花時の姿とは別物のように見えます。
最近静岡の野山ではオミナエシを見る事が少なくなりましたが、オトコエシはよく見かけます。外見同様繁殖力も強いようです
巣ごもりのおかげで年賀状の支度が大分進みました。
オトコエシのそう果

と云う事で今日は昨日小坂で見つけた『オトコエシ』の果実を取り上げてみました。
小さなソウ果の周りに付いているウチワの様な翼は小苞が大きくなったもので、散布に役立つようです。
「女郎花」と書くオミナエシに対しオトコエシは「男郎花」と書きます。オミナエシに比べ強く丈夫そうに見える事からそうなったようです。
春先のオトコエシは根元から匐枝を何本も出してその先に新苗を作り、花時の姿とは別物のように見えます。
最近静岡の野山ではオミナエシを見る事が少なくなりましたが、オトコエシはよく見かけます。外見同様繁殖力も強いようです
巣ごもりのおかげで年賀状の支度が大分進みました。
オトコエシのそう果

タグ :植物
2009年12月11日 Posted by 松ぽっくり at 17:03 │Comments(0) │下見
コショウに似て
師走に入ったからと云う訳ではありませんが何かと・・・(+_+) フィールドが遠くなっています。
ミカンで知られた「小坂」を今日は覗いて来ました。石垣や樹木に『フウトウカヅラ』が沢山絡まって、小さなブツブツの赤い実を付けています。
この蔓はコショウの仲間で赤い果実はコショウによく似ていますが辛みは無く香辛料にはなりません。
しかし葉や茎は風呂に入れて薬湯にすると、神経痛、打撲や骨折に効果があると云われ、主に九州南部や南西諸島で利用されるようです。
海岸に近い林内が好きなようで静岡では割と普通に見られます。
明日はどうやら天気は のようです。
のようです。
フウトウカヅラ

ミカンで知られた「小坂」を今日は覗いて来ました。石垣や樹木に『フウトウカヅラ』が沢山絡まって、小さなブツブツの赤い実を付けています。
この蔓はコショウの仲間で赤い果実はコショウによく似ていますが辛みは無く香辛料にはなりません。
しかし葉や茎は風呂に入れて薬湯にすると、神経痛、打撲や骨折に効果があると云われ、主に九州南部や南西諸島で利用されるようです。
海岸に近い林内が好きなようで静岡では割と普通に見られます。
明日はどうやら天気は
 のようです。
のようです。フウトウカヅラ

タグ :植物
2009年12月10日 Posted by 松ぽっくり at 21:18 │Comments(0) │下見
キチジョウソウ
朝から本降り、警報まで出る始末。
と云う事でフィールドはお休み、その代わり先日7日、谷津山を覗いた時に出会った『キチジョウソウ』を紹介します。
暖地の林下など少し暗めの所に生え、地表をはう茎で増えて群落を作りますが、花を付ける株は割と少ない。
果実は翌年の花の頃に赤く熟しますが食べられません
名前は吉事が有ると開花すると云う伝説に由来して『吉祥草』と付けられたようです。
谷津山ではシイの実が沢山落ちていたので少々頂いて来て、フライパンで炒っていただきました
 キチジョウソウ
キチジョウソウ

と云う事でフィールドはお休み、その代わり先日7日、谷津山を覗いた時に出会った『キチジョウソウ』を紹介します。

暖地の林下など少し暗めの所に生え、地表をはう茎で増えて群落を作りますが、花を付ける株は割と少ない。
果実は翌年の花の頃に赤く熟しますが食べられません

名前は吉事が有ると開花すると云う伝説に由来して『吉祥草』と付けられたようです。
谷津山ではシイの実が沢山落ちていたので少々頂いて来て、フライパンで炒っていただきました

 キチジョウソウ
キチジョウソウ タグ :植物
2009年11月11日 Posted by 松ぽっくり at 15:48 │Comments(2) │下見
千代みどりの森
千代みどりの森をのぞいて来ました。花の季節と云うには少々早すぎますが、それでもアオイスミレとヤマネコノメソウが咲き始めていました。どこの世界にもセッカチな仲間ははいるものです。
ヤブランとジャノヒゲは宝石の様な種を付けています(実のように見えますが種です、こちらの仲間は少々特異体質のようです)
ヤマトリカブトも幼葉を出し始めました、夏の草刈を潜り抜ければ秋に花が見れるのですが・・・
草も木もみんな春が待ち切れない様子でした。




左からヤマネコノメソウ、ジャノヒゲ、ヤブラン、ヤマトリカブト
ヤブランとジャノヒゲは宝石の様な種を付けています(実のように見えますが種です、こちらの仲間は少々特異体質のようです)
ヤマトリカブトも幼葉を出し始めました、夏の草刈を潜り抜ければ秋に花が見れるのですが・・・
草も木もみんな春が待ち切れない様子でした。




左からヤマネコノメソウ、ジャノヒゲ、ヤブラン、ヤマトリカブト
タグ :植物
2009年02月07日 Posted by 松ぽっくり at 18:20 │Comments(2) │下見
季節は最終章へ
小春日和の土曜日、観察会の下見に。と思ったら、デジカメが不調、 リペアセンターに問い合わせると早くて一週間との事、仕方ないのでとりあえずヤマダに出向く、年末の土曜日とあって大いに賑わっている。一応予算の範囲内のものがあったので購入、そのまま観察地に向かう。
リペアセンターに問い合わせると早くて一週間との事、仕方ないのでとりあえずヤマダに出向く、年末の土曜日とあって大いに賑わっている。一応予算の範囲内のものがあったので購入、そのまま観察地に向かう。
野山は季節の最終章に向かい、多様な表情を見せている。実を付けるもの、彩りを添えるもの葉を落としたもの、様々な時が流れている。カラスザンショウにメジロ、シジュウカラ、コゲラの混群がやって来て、ひとしきり私を楽しませて去って行った。ゆっくりと歩を進める、葉を落としたイヌビワが数え切れないほど実を付け、ガマズミの赤い実は冬の日を受けて輝いている。フユイチゴも大豊作のようだ、甘酸っぱい小さな実を堪能させて頂いた。今月のテーマは「冬へ 」




左から シジュウカラ、イヌビワ、ガマズミ、フユイチゴ、 写真クリックで大きくなります。
 リペアセンターに問い合わせると早くて一週間との事、仕方ないのでとりあえずヤマダに出向く、年末の土曜日とあって大いに賑わっている。一応予算の範囲内のものがあったので購入、そのまま観察地に向かう。
リペアセンターに問い合わせると早くて一週間との事、仕方ないのでとりあえずヤマダに出向く、年末の土曜日とあって大いに賑わっている。一応予算の範囲内のものがあったので購入、そのまま観察地に向かう。野山は季節の最終章に向かい、多様な表情を見せている。実を付けるもの、彩りを添えるもの葉を落としたもの、様々な時が流れている。カラスザンショウにメジロ、シジュウカラ、コゲラの混群がやって来て、ひとしきり私を楽しませて去って行った。ゆっくりと歩を進める、葉を落としたイヌビワが数え切れないほど実を付け、ガマズミの赤い実は冬の日を受けて輝いている。フユイチゴも大豊作のようだ、甘酸っぱい小さな実を堪能させて頂いた。今月のテーマは「冬へ 」




左から シジュウカラ、イヌビワ、ガマズミ、フユイチゴ、 写真クリックで大きくなります。
タグ :植物
2008年12月13日 Posted by 松ぽっくり at 23:10 │Comments(0) │下見
照葉樹
昨日、久能山を登って照葉樹を見て来ました。今回が初めてではありませんが、巨木の多さに感嘆します。
クスノキ(実)、タブノキ、ヤブニッケイ(実)、スダジイ、クロガネモチ(実)、ホルトノキ、アラカシ(実)、シロダモ(雄花)、トベラ(実)、などが見られました。
季節もありますが、手入れも良くされていて草本はほとんど見られません。ただ、野生化したハナカタバミは入口付近に点在しています。
コショウの仲間のフウトウカズラは非常に多く、あらゆる所にからみついていて、オレンジ色の粒々の実をつけているモノもあります。

左ヤブニッケイ、右フウトウカズラ
クスノキ(実)、タブノキ、ヤブニッケイ(実)、スダジイ、クロガネモチ(実)、ホルトノキ、アラカシ(実)、シロダモ(雄花)、トベラ(実)、などが見られました。
季節もありますが、手入れも良くされていて草本はほとんど見られません。ただ、野生化したハナカタバミは入口付近に点在しています。
コショウの仲間のフウトウカズラは非常に多く、あらゆる所にからみついていて、オレンジ色の粒々の実をつけているモノもあります。
左ヤブニッケイ、右フウトウカズラ
タグ :樹木