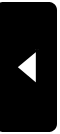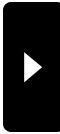どちらが先?
ホタルブクロ
内側の小さな斑点がわかる
午後になって雨がパラついたり止んだりを繰り返しているが、濡れる程ではない。
突き当たりの崖で『ホタルブクロ』が咲き始めている。この草については「夏の草」と云う思い込みがあるので随分早く感じる。
ホタルブクロの学名は「小さな鐘で花の内側に紫の斑点があるもの」と云う意味らしい。
一方和名の「蛍袋」はこの花に子供たちが蛍を入れて持ち帰ったからと云われるが、
この遊びがこの名を生んだのか、それともこの名が子供たちに遊び方を教えたのか?私は後者のような気がしてならない。
県内には「キツネノチョウチン」「チョウチンバナ」「ツリガネグサ」などの方言名があり、この草が昔から親しまれてきた事がうかがえる。

内側の小さな斑点がわかる

午後になって雨がパラついたり止んだりを繰り返しているが、濡れる程ではない。
突き当たりの崖で『ホタルブクロ』が咲き始めている。この草については「夏の草」と云う思い込みがあるので随分早く感じる。
ホタルブクロの学名は「小さな鐘で花の内側に紫の斑点があるもの」と云う意味らしい。
一方和名の「蛍袋」はこの花に子供たちが蛍を入れて持ち帰ったからと云われるが、
この遊びがこの名を生んだのか、それともこの名が子供たちに遊び方を教えたのか?私は後者のような気がしてならない。
県内には「キツネノチョウチン」「チョウチンバナ」「ツリガネグサ」などの方言名があり、この草が昔から親しまれてきた事がうかがえる。
タグ :植物
2011年05月22日 Posted by 松ぽっくり at 20:59 │Comments(0) │フィールド
2つ並んで
アリドオシ
短枝の変化した鋭い刺
今日は皆さんと林道を歩いて来ました。気温は高かったのですが、適当な木陰と青葉若葉に気持ちの良いひと時を過ごす事が出来ました。
道筋では「ガクウツギ」や「ヤブデマリ」の花が見ごろを迎え、林床では杉の落ち葉に埋もれながら『アリドオシ』の真っ白な花が2個づつ並んで咲いていました。全体に葉より長い刺が目立ち、この鋭く長い刺は短枝の変化したもの。そしてその鋭さはアリさえも刺し通してしまいそう!。と云う事で「蟻通し」の名が付きました。
垂れ下った「サルナシ」のツルに付く沢山の蕾を横目に、ウグイスの谷渡りを聞きながら帰って来ました。

短枝の変化した鋭い刺

今日は皆さんと林道を歩いて来ました。気温は高かったのですが、適当な木陰と青葉若葉に気持ちの良いひと時を過ごす事が出来ました。
道筋では「ガクウツギ」や「ヤブデマリ」の花が見ごろを迎え、林床では杉の落ち葉に埋もれながら『アリドオシ』の真っ白な花が2個づつ並んで咲いていました。全体に葉より長い刺が目立ち、この鋭く長い刺は短枝の変化したもの。そしてその鋭さはアリさえも刺し通してしまいそう!。と云う事で「蟻通し」の名が付きました。
垂れ下った「サルナシ」のツルに付く沢山の蕾を横目に、ウグイスの谷渡りを聞きながら帰って来ました。
タグ :植物
2011年05月21日 Posted by 松ぽっくり at 23:29 │Comments(2) │観察会
神話で
テイカカズラ

今日も気温は上がって夏日。帽子をかぶっていても日差しが気になるようになってきました。
突き当たりの林縁で『テイカカズラ』が咲きだした、ツルも細くまだ花の数は少ないが、顔を近づけるといい香りがする。
話は飛びますが、「天の岩戸」の神話で「天のうずめの女命」が岩戸の前で面白おかしく踊った際、「ヒカゲノカズラ」をタスキに、「マサキノカズラ」を髪に飾り、笹の葉を手に持っていたといいます。この時の「マサキノカズラ」が現在の「テイカカズラ」だろうと云われています。
茎や葉を乾燥し、煎じて「解熱」や「強壮」などに使用されるようです。


今日も気温は上がって夏日。帽子をかぶっていても日差しが気になるようになってきました。
突き当たりの林縁で『テイカカズラ』が咲きだした、ツルも細くまだ花の数は少ないが、顔を近づけるといい香りがする。
話は飛びますが、「天の岩戸」の神話で「天のうずめの女命」が岩戸の前で面白おかしく踊った際、「ヒカゲノカズラ」をタスキに、「マサキノカズラ」を髪に飾り、笹の葉を手に持っていたといいます。この時の「マサキノカズラ」が現在の「テイカカズラ」だろうと云われています。
茎や葉を乾燥し、煎じて「解熱」や「強壮」などに使用されるようです。
タグ :植物
2011年05月20日 Posted by 松ぽっくり at 16:32 │Comments(0) │フィールド
有毒植物
クララ

今年も『クララ』が咲き始めた。フィールド内には何ヶ所か有るが、突き当たりの崖の下が一番早かった。
マメ科のこの草は有毒植物で、なめるとクラクラする程苦いと云われる根は駆虫薬に使われる。
漢方では「苦参」と云い、健胃、利尿薬に用いられるようだ。
近くでは伸び始めた「カラムシ」の若葉が穴だらけになっている。よく見ると
『ラミーカミキリ』が何匹か見つかった。軟らかい若葉をお食事中の様だった。
このカミキリは元々我国に居たものではなく、明治の初め中国大陸から輸入されたラミー(イラクサ科)にくっ付いて入って来た、と云われている。



今年も『クララ』が咲き始めた。フィールド内には何ヶ所か有るが、突き当たりの崖の下が一番早かった。
マメ科のこの草は有毒植物で、なめるとクラクラする程苦いと云われる根は駆虫薬に使われる。
漢方では「苦参」と云い、健胃、利尿薬に用いられるようだ。
近くでは伸び始めた「カラムシ」の若葉が穴だらけになっている。よく見ると
『ラミーカミキリ』が何匹か見つかった。軟らかい若葉をお食事中の様だった。
このカミキリは元々我国に居たものではなく、明治の初め中国大陸から輸入されたラミー(イラクサ科)にくっ付いて入って来た、と云われている。

タグ :自然
2011年05月19日 Posted by 松ぽっくり at 18:31 │Comments(0) │フィールド
真弓
マユミ
昨日の雷雨がうそのようにカラッと晴れて気持がいい!
竹林のふちの『マユミ』の花もそろそろピークを過ぎようとしている。
この小さくて地味な花もよく見ると2つのタイプがありこの木は「雄しべが長くて雌しべが短い」タイプ。
秋の紅葉や果実が美しいので公園などに植えられる事がある。実付きの良い木は木全体が赤く見える程沢山の実を付けて中々見事です。
普通葉は無毛ですが、葉裏の脈上に突起状の短毛が密生するものを「カントウマユミ」と云う。これはやや標高の高い所に生えます。

昨日の雷雨がうそのようにカラッと晴れて気持がいい!
竹林のふちの『マユミ』の花もそろそろピークを過ぎようとしている。
この小さくて地味な花もよく見ると2つのタイプがありこの木は「雄しべが長くて雌しべが短い」タイプ。
秋の紅葉や果実が美しいので公園などに植えられる事がある。実付きの良い木は木全体が赤く見える程沢山の実を付けて中々見事です。
普通葉は無毛ですが、葉裏の脈上に突起状の短毛が密生するものを「カントウマユミ」と云う。これはやや標高の高い所に生えます。
タグ :植物
2011年05月18日 Posted by 松ぽっくり at 18:03 │Comments(0) │フィールド
対照的です
ゴンズイ

緑が広がりを増してきた河原に白い島を幾つも幾つも盛り上げて「ノイバラ」が盛りを迎えた!
突き当たりの林縁では『ゴンズイ』が小さな目立たない花を開き始めた。開き・・・と云っても黄緑色のガクも花弁も平開せず、直立したままです。
秋には赤と黒の毒々しいまでに派手な果皮と種のコントラストを見せるのに、花は対照的です。
「ゴンズイ」の名は材がもろくて役に立たないので同じように役に立たない魚「ゴンズイ」の名がつけられたと云う説がある。所がその役に立たないと云われた魚が最近見直されているようだ、毒を持つ刺さえ取ってしまえば煮つけにしろ何にしろかなり美味いらしい。
なんでも「ゴンズイの汚名を晴らす会」なる会を作っている方々さえあると云う。
世間は広い!そして面白い。


緑が広がりを増してきた河原に白い島を幾つも幾つも盛り上げて「ノイバラ」が盛りを迎えた!
突き当たりの林縁では『ゴンズイ』が小さな目立たない花を開き始めた。開き・・・と云っても黄緑色のガクも花弁も平開せず、直立したままです。
秋には赤と黒の毒々しいまでに派手な果皮と種のコントラストを見せるのに、花は対照的です。
「ゴンズイ」の名は材がもろくて役に立たないので同じように役に立たない魚「ゴンズイ」の名がつけられたと云う説がある。所がその役に立たないと云われた魚が最近見直されているようだ、毒を持つ刺さえ取ってしまえば煮つけにしろ何にしろかなり美味いらしい。
なんでも「ゴンズイの汚名を晴らす会」なる会を作っている方々さえあると云う。
世間は広い!そして面白い。

タグ :植物
2011年05月16日 Posted by 松ぽっくり at 17:32 │Comments(0) │フィールド
国際的に
スイカズラ

土手下の生垣に絡んだ『スイカズラ』が満開になっていた。この花に関しては例年通りと云うかフィールドでは若干早い気がする。
「すいかずら二花づつのよき香り」(素十)と詠まれる様にクチナシに似た香りが有る。
この香りを楽しむ為に花を焼酎に漬けて「忍冬酒」としたりする。
日本で栽培される事はあまりないが、欧米などでは鑑賞用に植えられたりするようです。
ある大学の先生の話では遠く離れたケニアの首都ナイロビの街角に植えられているを目にした事があるそうです。
昔の子供のおやつ代わりだった「スイカズラ」も随分国際的になってきた。


土手下の生垣に絡んだ『スイカズラ』が満開になっていた。この花に関しては例年通りと云うかフィールドでは若干早い気がする。
「すいかずら二花づつのよき香り」(素十)と詠まれる様にクチナシに似た香りが有る。
この香りを楽しむ為に花を焼酎に漬けて「忍冬酒」としたりする。
日本で栽培される事はあまりないが、欧米などでは鑑賞用に植えられたりするようです。
ある大学の先生の話では遠く離れたケニアの首都ナイロビの街角に植えられているを目にした事があるそうです。
昔の子供のおやつ代わりだった「スイカズラ」も随分国際的になってきた。
タグ :植物
2011年05月15日 Posted by 松ぽっくり at 18:12 │Comments(0) │フィールド
一番軽い
キリ
土手の脇に1本だけ有る『キリ』、恐らく自然に生えたものだと思うが、今年は昨年に比べ花の数が少し増えたようだ。
その花も葉も強い西風に千切れんばかりにしなっている。
元々中国原産だが平安時代、紫は高貴な色とされ、桐はその花の色から宮中にも植栽され、「枕草子」は紫に咲く、風情ある花と記している。
そしてその材は比重0,3以下と云われ、日本で一番軽く、木目も美しく狂いも少ないのでタンスや琴、金庫の内張りなどに重用される事はご承知の通りです。
キリはゴマノハグサ科キリ属に分類されているが、研究者の間では「ノウゼンカズラ科」に入れる考えも有ったようです。ただ、最近の新分類法では「キリ科」として独立しています。

土手の脇に1本だけ有る『キリ』、恐らく自然に生えたものだと思うが、今年は昨年に比べ花の数が少し増えたようだ。
その花も葉も強い西風に千切れんばかりにしなっている。
元々中国原産だが平安時代、紫は高貴な色とされ、桐はその花の色から宮中にも植栽され、「枕草子」は紫に咲く、風情ある花と記している。
そしてその材は比重0,3以下と云われ、日本で一番軽く、木目も美しく狂いも少ないのでタンスや琴、金庫の内張りなどに重用される事はご承知の通りです。
キリはゴマノハグサ科キリ属に分類されているが、研究者の間では「ノウゼンカズラ科」に入れる考えも有ったようです。ただ、最近の新分類法では「キリ科」として独立しています。
タグ :植物
2011年05月14日 Posted by 松ぽっくり at 17:27 │Comments(0) │フィールド
白く見える程
ガマズミ

よく降りました、でもその割に川の水量は多くない?
強い南よりの風が吹いて気温は急上昇、昨日より10℃以上あがって暑い!
突き当たりの林縁で『ガマズミ』は木全体が白く見える程沢山の花や蕾を付けています。直径5~8ミリ程の小さな花は沢山集まり10センチ程のかたまりになっている。花にはにおいが有り、その匂いで虫を呼び寄せるようだ。
秋になると真っ赤な酸っぱい実を沢山付けますが、この実をアルコールに漬けると赤いきれいな「ガマズミ酒」が出来ます。
そばで「ダイミョウセセリ」が翅を休めていました。



よく降りました、でもその割に川の水量は多くない?
強い南よりの風が吹いて気温は急上昇、昨日より10℃以上あがって暑い!
突き当たりの林縁で『ガマズミ』は木全体が白く見える程沢山の花や蕾を付けています。直径5~8ミリ程の小さな花は沢山集まり10センチ程のかたまりになっている。花にはにおいが有り、その匂いで虫を呼び寄せるようだ。
秋になると真っ赤な酸っぱい実を沢山付けますが、この実をアルコールに漬けると赤いきれいな「ガマズミ酒」が出来ます。
そばで「ダイミョウセセリ」が翅を休めていました。

タグ :植物
2011年05月13日 Posted by 松ぽっくり at 17:04 │Comments(0) │フィールド
好感が
チガヤ
この季節、フィールドは日々表情を変えていきます。
今日は朝から荒れた天気、「チガヤ」の穂が方向の定まらぬ風に波打って、「ノイバラ」の白い花もあちこちで目に付くようになってきました。
空は明るいのに雨がパラパラしていますが、7月なみの気温で気になりません。
昨日は仲間と林道を少し歩いて来ました。山は「ウツギ」や「ガクウツギ」「ヤブウツギ」「ヤブデマリ」と云った木の花で賑やかです。
水気の有る木陰では『クルマムグラ』が白い花を一斉に咲かせていました。花は直径2.5ミリと小さいですが、並んで咲いている姿は楚々として好感が持てます。
名前は葉が普通6輪生して車輪状になる事と茎がツル状になるので「車葎」となった。
草も木も生気溢れるよい季節です。
クルマムグラ

この季節、フィールドは日々表情を変えていきます。
今日は朝から荒れた天気、「チガヤ」の穂が方向の定まらぬ風に波打って、「ノイバラ」の白い花もあちこちで目に付くようになってきました。
空は明るいのに雨がパラパラしていますが、7月なみの気温で気になりません。
昨日は仲間と林道を少し歩いて来ました。山は「ウツギ」や「ガクウツギ」「ヤブウツギ」「ヤブデマリ」と云った木の花で賑やかです。
水気の有る木陰では『クルマムグラ』が白い花を一斉に咲かせていました。花は直径2.5ミリと小さいですが、並んで咲いている姿は楚々として好感が持てます。
名前は葉が普通6輪生して車輪状になる事と茎がツル状になるので「車葎」となった。
草も木も生気溢れるよい季節です。
クルマムグラ

タグ :植物
2011年05月10日 Posted by 松ぽっくり at 17:03 │Comments(0) │下見
ブラシの様な
ウワミズザクラ

風が強い、南西の風で気温も上がって汗ばむほどです。
土手もイネ科の葉が背丈を伸ばし、「ウラジロチチコグサ」「チチコグサモドキ」といった外来種も一気に数を増して雑然として来ました。
こうなるとそろそろ草刈りのタイミングが気にかかります。
畑地の境に植えられている『ウワミズザクラ』、大小取り混ぜて4本ほど有りますが花のタイミングが少しづつずれていて今一番最後の木が盛りを迎えています。
小さな花が密集した花序は沢山の雄しべが付き出て、ビンを洗うブラシのようです。この沢山の雄しべは「バラ科」の特徴の一つでも有ります。
材は床柱や器具材。樹皮は桜皮細工。根は染料と上から下までかなり用途は広いようです。


風が強い、南西の風で気温も上がって汗ばむほどです。
土手もイネ科の葉が背丈を伸ばし、「ウラジロチチコグサ」「チチコグサモドキ」といった外来種も一気に数を増して雑然として来ました。
こうなるとそろそろ草刈りのタイミングが気にかかります。
畑地の境に植えられている『ウワミズザクラ』、大小取り混ぜて4本ほど有りますが花のタイミングが少しづつずれていて今一番最後の木が盛りを迎えています。
小さな花が密集した花序は沢山の雄しべが付き出て、ビンを洗うブラシのようです。この沢山の雄しべは「バラ科」の特徴の一つでも有ります。
材は床柱や器具材。樹皮は桜皮細工。根は染料と上から下までかなり用途は広いようです。
タグ :植物
2011年05月08日 Posted by 松ぽっくり at 17:24 │Comments(0) │フィールド
おびただしい数の
ツルウメモドキ雄花

雌花
草むらに「クサイチゴ」が真っ赤に熟れて微笑んでいました。今季の初物です、早速、一つ、二つ、三つ、と云う事で、5月の旬物、大変美味しくいただきました。
空地の一画、アカメガシワに絡んだ『ツルウメモドキ』がおびただしい数の雄花を付けています。近くに雌花も有りますが、その数は随分と少ない。
フィールドにはあちこちにこのツルが有りますが場所によって結構開花日に差が有ります。
名前は「ウメモドキ」に似てツル性なので「蔓梅擬」となったらしいが、葉は梅の葉によく似ている。

雌花

草むらに「クサイチゴ」が真っ赤に熟れて微笑んでいました。今季の初物です、早速、一つ、二つ、三つ、と云う事で、5月の旬物、大変美味しくいただきました。

空地の一画、アカメガシワに絡んだ『ツルウメモドキ』がおびただしい数の雄花を付けています。近くに雌花も有りますが、その数は随分と少ない。
フィールドにはあちこちにこのツルが有りますが場所によって結構開花日に差が有ります。
名前は「ウメモドキ」に似てツル性なので「蔓梅擬」となったらしいが、葉は梅の葉によく似ている。
タグ :植物
2011年05月07日 Posted by 松ぽっくり at 17:04 │Comments(0) │フィールド
この一画
ミミナグサ
今日は「立夏」、だからと云う訳ではないが、「ノイバラ」や「ノアザミ」の花が目に付くようになって、土手の景色に変化が見えてきた。
突き当たりの斜面の下で『ミミナグサ』が小さな花を付けた。大分前から「オランダミミナグサ」の攻勢に後塵を拝しているが、この一画だけは毎年テレトリーを守っている。
「耳菜草」の名前は対生して毛の多い葉がネズミの耳に似る事と、若葉が食用になる事から付いたようだ。
小さな花弁は真中から少し切れ込んで「握り鋏」の様に見える。



今日は「立夏」、だからと云う訳ではないが、「ノイバラ」や「ノアザミ」の花が目に付くようになって、土手の景色に変化が見えてきた。
突き当たりの斜面の下で『ミミナグサ』が小さな花を付けた。大分前から「オランダミミナグサ」の攻勢に後塵を拝しているが、この一画だけは毎年テレトリーを守っている。
「耳菜草」の名前は対生して毛の多い葉がネズミの耳に似る事と、若葉が食用になる事から付いたようだ。
小さな花弁は真中から少し切れ込んで「握り鋏」の様に見える。


タグ :植物
2011年05月06日 Posted by 松ぽっくり at 17:13 │Comments(0) │フィールド
へばり付いて
ペラペラヨメナ
水路の縁、コンクリの壁にへばり付いて『ペラペラヨメナ』が今年も見事に咲きました。
確かに水だけは充分に有るが、土のかけらも無いような所でよくもまあー、と感心する。
同時に「ペラペラヨメナ」などと付けた名前が気の毒に思えたりもします(写真は上から撮っています)
しかし、これはこの草の一面で有って、環境によっては茎がだらしなく伸びてかなりの「ペラペラ感」も見せます。
中央アメリカ原産で鑑賞用に導入されたようですが、しっかり逃げ出して関東以西の河川や道路の石垣の間などでしたたかに存在感を見せています。

水路の縁、コンクリの壁にへばり付いて『ペラペラヨメナ』が今年も見事に咲きました。
確かに水だけは充分に有るが、土のかけらも無いような所でよくもまあー、と感心する。
同時に「ペラペラヨメナ」などと付けた名前が気の毒に思えたりもします(写真は上から撮っています)
しかし、これはこの草の一面で有って、環境によっては茎がだらしなく伸びてかなりの「ペラペラ感」も見せます。
中央アメリカ原産で鑑賞用に導入されたようですが、しっかり逃げ出して関東以西の河川や道路の石垣の間などでしたたかに存在感を見せています。
タグ :植物
2011年05月05日 Posted by 松ぽっくり at 19:05 │Comments(0) │近所
妖しさ
オオバウマノスズクサ

午後は様子見に林道を走って来ました。こちらは「ウツギ」が丁度盛り。至る所で白く輝いていた。
少し上に上がると林縁に「ツルカノコソウ」、水の流れる側溝には「ヒメレンゲ」が見える。
若葉は目に優しく、いい季節です。
帰りみち、垂れ下った『オオバウマノスズクサ』の中を覗くと花が有った。この花は何度も見ているが、最初にこの花を見たとき「どうして!」と思った、ズングリした「サキソフォン」の様な形もさることながらそのラッパ部に浮き出た血筋の様な模様に何か妖しさの様なものを感じたのだ。
県内では割と普通に見られる、落葉つる性の木本です。
「ウツギ」の花のアップ、花糸に肩が有るのが確認できる。平開しない花の形も!



午後は様子見に林道を走って来ました。こちらは「ウツギ」が丁度盛り。至る所で白く輝いていた。
少し上に上がると林縁に「ツルカノコソウ」、水の流れる側溝には「ヒメレンゲ」が見える。
若葉は目に優しく、いい季節です。
帰りみち、垂れ下った『オオバウマノスズクサ』の中を覗くと花が有った。この花は何度も見ているが、最初にこの花を見たとき「どうして!」と思った、ズングリした「サキソフォン」の様な形もさることながらそのラッパ部に浮き出た血筋の様な模様に何か妖しさの様なものを感じたのだ。
県内では割と普通に見られる、落葉つる性の木本です。
「ウツギ」の花のアップ、花糸に肩が有るのが確認できる。平開しない花の形も!

タグ :植物
2011年05月04日 Posted by 松ぽっくり at 19:01 │Comments(0) │下見
夏の気配
マルバウツギ

「セッカ」や「ヒバリ」の声が絶え間なく聞こえる午前のフィールド。
「ニワゼキショウ」や「コマツヨイグサ」は徐々にその数を増して、夏の気配が次第に広がりつつある。
突き当たりの疎林縁では『マルバウツギ』が満開になっていた。何処にでも有る木だが花の数が多いので満開になると結構明るく目立つ。
「ウツギ」とよく似ているが、雄しべの花糸に肩が無いのと花が平開する事で識別出来る。
ガマズミの若葉の上では「コミスジ」が日光浴をしていた、今季初見。



「セッカ」や「ヒバリ」の声が絶え間なく聞こえる午前のフィールド。
「ニワゼキショウ」や「コマツヨイグサ」は徐々にその数を増して、夏の気配が次第に広がりつつある。
突き当たりの疎林縁では『マルバウツギ』が満開になっていた。何処にでも有る木だが花の数が多いので満開になると結構明るく目立つ。
「ウツギ」とよく似ているが、雄しべの花糸に肩が無いのと花が平開する事で識別出来る。
ガマズミの若葉の上では「コミスジ」が日光浴をしていた、今季初見。

2011年05月04日 Posted by 松ぽっくり at 17:32 │Comments(0) │フィールド
蛍蔓
ホタルカズラ
曇り空のうえにひどい黄砂でドンヨリとしています。スッキリしません。
急に思い出して少し離れた土手斜面に『ホタルカズラ』を訪ねてみましたが、やっぱり盛りは過ぎていて状態の良い花は見つかりません。それと前回に比べ、個体数もかなり減っているのが気になります。
「蛍蔓」は鮮青色の花の色で人気が有り、それ故持ち去られる事もしばしばの様です。
今年はしっかり走出枝を延ばして殖えてくれる事を祈りたい。
名前を「蛍草」と呼んだりしますが、俳句の方では「蛍草」と云うと「ツユクサ」の事なので気を付けたい。

曇り空のうえにひどい黄砂でドンヨリとしています。スッキリしません。
急に思い出して少し離れた土手斜面に『ホタルカズラ』を訪ねてみましたが、やっぱり盛りは過ぎていて状態の良い花は見つかりません。それと前回に比べ、個体数もかなり減っているのが気になります。
「蛍蔓」は鮮青色の花の色で人気が有り、それ故持ち去られる事もしばしばの様です。
今年はしっかり走出枝を延ばして殖えてくれる事を祈りたい。
名前を「蛍草」と呼んだりしますが、俳句の方では「蛍草」と云うと「ツユクサ」の事なので気を付けたい。
タグ :植物
2011年05月03日 Posted by 松ぽっくり at 17:33 │Comments(0) │フィールド
忽然と
タツナミソウ

遥か大陸からの嬉しくない届け物、黄砂で山はぼんやりとしている。
一昨日まで気配も無かった斜面に『タツナミソウ』が忽然と現れた!と云うより青紫の色が出るまでは20㌢程の草丈では気付かなくて当然かもしれない。
昨年も全く同じ日に取り上げているが、今年の方が少し咲き始めは遅いようだ。
花をアップで見ると下唇をベロンとした口が沢山集まったような愉快な花です。
しかし見る人が見ると打ち寄せる波頭を連想する、との事で「立浪草」の名が付きました。


遥か大陸からの嬉しくない届け物、黄砂で山はぼんやりとしている。
一昨日まで気配も無かった斜面に『タツナミソウ』が忽然と現れた!と云うより青紫の色が出るまでは20㌢程の草丈では気付かなくて当然かもしれない。
昨年も全く同じ日に取り上げているが、今年の方が少し咲き始めは遅いようだ。
花をアップで見ると下唇をベロンとした口が沢山集まったような愉快な花です。
しかし見る人が見ると打ち寄せる波頭を連想する、との事で「立浪草」の名が付きました。
タグ :植物
2011年05月02日 Posted by 松ぽっくり at 16:51 │Comments(0) │フィールド
雨なので
ヤセウツボ
花にも腺毛が多い
5月のスタートは朝から一日雨、と云う事で昨日の「アマドコロ」のそばに生えていた
『ヤセウツボ』をアップします。
昨年の今頃も家の近くの草地に現れたのを取り上げていますが、外国産の寄生植物で他の植物の根に自分の根を食い込ませて、そこから養分をいただいて生活しています。
同じような寄生植物でも海岸や河原などに出る「ハマウツボ」はヨモギ属の「カワラヨモギ」を主に寄生すると云う律儀さを持っていますが、この「ヤセウツボ」はマメ科、セリ科、キク科など様々な植物にとり付いて少々節操に欠ける。
明日は八十八夜、夏の立つ日も近い!

花にも腺毛が多い

5月のスタートは朝から一日雨、と云う事で昨日の「アマドコロ」のそばに生えていた
『ヤセウツボ』をアップします。
昨年の今頃も家の近くの草地に現れたのを取り上げていますが、外国産の寄生植物で他の植物の根に自分の根を食い込ませて、そこから養分をいただいて生活しています。
同じような寄生植物でも海岸や河原などに出る「ハマウツボ」はヨモギ属の「カワラヨモギ」を主に寄生すると云う律儀さを持っていますが、この「ヤセウツボ」はマメ科、セリ科、キク科など様々な植物にとり付いて少々節操に欠ける。
明日は八十八夜、夏の立つ日も近い!
タグ :植物
2011年05月01日 Posted by 松ぽっくり at 22:53 │Comments(0) │フィールド
稜が有る
アマドコロ

誰かに呼ばれた訳ではないが、いつもと逆の川下に向かって行ってみようと、土手の斜面をチャリのブレーキを思いっきり握りながら半分程おりた時、懐かしげな草姿が目に入った。
このフィールドでは姿を消したと思っていた『アマドコロ』が群生していた。
背丈は40cm程と大きくはないが株数は結構有る。嬉し懐かしい出会いでした。
「ナルコユリ」と似た姿をしているが、茎に稜が有る事や葉の幅がやや広い事などで識別できる。
円柱形の地下茎が横に延び毎年その先に一本の茎を立てるが、その地下茎がヤマノイモ科の「オニドコロ」に似ていて、甘味が有るので「甘野老」の名が付いたようです。
明日は雨になるらしい。


誰かに呼ばれた訳ではないが、いつもと逆の川下に向かって行ってみようと、土手の斜面をチャリのブレーキを思いっきり握りながら半分程おりた時、懐かしげな草姿が目に入った。
このフィールドでは姿を消したと思っていた『アマドコロ』が群生していた。
背丈は40cm程と大きくはないが株数は結構有る。嬉し懐かしい出会いでした。
「ナルコユリ」と似た姿をしているが、茎に稜が有る事や葉の幅がやや広い事などで識別できる。
円柱形の地下茎が横に延び毎年その先に一本の茎を立てるが、その地下茎がヤマノイモ科の「オニドコロ」に似ていて、甘味が有るので「甘野老」の名が付いたようです。
明日は雨になるらしい。
タグ :植物